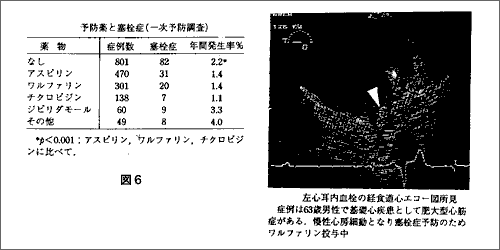| NO.17 |
心臓血管病と薬の正しい知識を得るために
(7−7)
危険因子を是正して再発を防ぎましょう
最後に、実際の病気の話をします。狭心症というのは心臓の血管が細くなったため、心臓自体に流れる血液が乏しくなる病気です。一定以上運動をすると心臓に必要な血液が十分流れないため生じます。そ血管が完全に詰まって、血液が止まってしまうと、そこの心筋は死んでしまいます。これが心筋梗塞です。硬塞というのは「血液が途絶した結果、その一部が死んだ状態」という意味ですね。脳だったら脳硬塞となります。ですから、梗塞になる前に、あるいは狭心症のうちに治すということが重要です。狭心症の薬だけでもたくさんあります。心臓の血管を広げる作用のある硝酸薬、カルシウム拮抗薬やベータ遮断薬が重要です。とても多くの種類があります。たとえば硝酸薬は舌下薬、スプレー、錠剤、テープ薬、そして点滴用まであり、これをすべてその患者さんの病態に合わせてに使い分けます。薬の種類、剤形、量、他の薬とどういう組み合わせが良いのか、ということは患者さんひとりひとりの状態にあわせて選んでいきます。1人1人異なります。前にもでてきたように、再発予防(2次予防)も重要です。心筋梗塞に1度なったのでもうだめか、ということは決してありません。きちんと仕事したり、社会で活躍したりする方はたくさんいます。2回目の心筋梗塞は当然死亡率が高いですから、予防が大事です。やはり危険因子の是正が最も重要で、より厳密に管理する必要があります。また、再発予防できる薬−アスピリンなどの血小板の機能を抑制する薬や、ベータ遮断薬−も好んで使用します。
「心不全」という言葉は有名ですが、その実態は意外と理解しにくいものです。つまり、心不全をごく簡単にいうと「心臓の働きが悪い(不全)」という意味で、病名ではありません。皆さんよく「心不全で死んだ」なんて言いますけど、心不全をおこしたもともとの原因が重要です。日本人で1番多い病気は高血圧ですが、これが原因になり得ます。もちろん、狭心症や心筋梗塞は心不全の原因として最も重要で、数的にも最多でしょう。心不全にも軽いものから重症なものまであります。治療の基本は、塩分制限、水分制限、運動制限です。そのうえで、原因である疾患の治療やその誘引となる病気を治療します。たとえば、心筋梗塞による心不全では、心不全治療と同時に、心筋梗塞に対する治療をすぐ開始します。そしてその2次予防に進みます。心筋梗塞の背景として糖尿病、高血圧、高脂血症があればその治療を行うことが、2次予防としても重要になります。
不整脈とは、心臓のリズムの異常です。心臓は電気的に動いていますが、そこに障害が生じると、不規則なリズムとなって不整脈になります。これも、やはり原因が重要です。皆さんも「不整脈」と言われたことがあるかもしれません。これ自体はとても頻度の多い病気で、不整脈が見つかったらすぐ薬ということには、必ずしもなりません。むしろ、治療が必要でないことの方が数的には多いくらいです。ただし、一部の患者さん−たとえば、症状が強い、頻度が多い、もともと心臓病がある、あるいは心臓の働きが悪い、めまいや失神を起こしたことがある−では、詳しく不整脈の種類と原因を調べる必要があります。そういう方は不整脈の治療をすべきかどうか慎重に検査をします。最重症の不整脈では、放っておいたら致死的になりますので、より積極的な治療が選択されます。これまででてきた、生活習慣病はいずれも不整脈の背景、基礎疾患になり得ます。このことに注意して、検査や治療の必要性を決めていきます。
脳卒中の1つで脳血栓症という言葉を聞いたことがあると思います。図6は心臓超音波の画像です。白い矢印は血が固まった塊です。これは血栓(血の塊)で、心臓の左心房というところにあります。これがもし剥がれたらどうなると思いますか。左心房ですから次は左心室へ行き、左心室から大動脈へ行きます。大動脈からもし頭の血管(頸動脈)に上がって、脳に行くと、脳にひっかかりますね。脳卒中(正確には脳塞栓症)の発症です。そこの脳の一部が死んでしまったら脳硬塞です。障害部位と範囲によって、軽い症状(口がもつれるなど)から半身麻痺や意識障害など、重症なものまであり、時に死亡することもあります。これが、もし首に行く血管ではなく下半身に行ったらどうなるか。どこにこの血栓がひっかかるか分かりませんが、腎臓の血管に詰まったら腎硬塞になります。これも恐ろしい病気です。さらそこを通り過ぎて、足の血管に詰まったらどうなるか。これは急性動脈閉塞といって6時間以内に治療しないと足が腐ってしまいます。ひどければ、切断することもあります。
このような血栓を予防することが重要であることは容易に理解できますね。では血栓の原因は何かというと、ひとつは動脈硬化(比較的太い動脈の壁に血栓ができる)、それからもうひとつは心房細動という不整脈です。こうした場合、血栓を予防する薬というのを良く使います。たとえば血小版を抑えるアスピリンや、凝固因子を抑えるワーファリンという薬です。こういう薬は、血栓(血の塊)ができないように、血の流れがスムーズにいくようにする作用があり、脳梗塞、心筋梗塞、心房細動、人工弁、肺梗塞など、血栓症のリスクが高い場合に使用します。特にアスピリンはすごく安いうえに、効果がありますから非常に良い薬といえます。この薬が正式に使ってよく成ったのはごく最近です。
話は生活習慣病から少しそれますが、最近よく聞くものにエコノミー症候群があります。これも血栓が原因です。長い時間飛行機に乗っている(狭い空間で、長い時間、同じ体位を取っている)と足の静脈内に血流の停滞ができ、これが血栓をつくり、はがれて飛んでしまいます。すると足の静脈ですから、流れ着く先は肺で、肺血栓塞栓症から肺硬塞になります。肺硬塞というのは、小さいものは無症状ですが、大きな肺硬塞では致命的になることもあります。ですから、そういう既往、肥満、下肢静脈瘤のある人、心房細動のある人など、リスクの高い方では予防が重要になります。以上のような病態ではいずれもアスピリンやワーファリンが有効です。
「納豆禁止」はワーファリンだけ
最後に、良く聞かれる、あるいは誤解されている、「ワーファリンと納豆」の話を付け加えます。ワーファリンという薬は特殊な薬で、すこし使い方がむずかしいため、一般内科の先生はあまり使用しないと思いますが、ビタミンKの多い食品で効果が消えてしまいます。納豆が最も有名ですが、ほかに緑茶(煎茶)、海草、ブロッコリー、キャベツ、パセリなどの緑黄色野菜があります。したがって、納豆は禁止、それ以外は注意してたべる必要があります。ただし、それはワーファリンという薬だけで、その他の薬(−アスピリン、チクロピジン、ジピリダモールを含め)では心配いりません。とくに納豆を強調するのは、ビタミンKが納豆に豊富に入っているからだけではなく、納豆菌がたくさんビタミンKを造るためです。納豆菌自体がビタミンKを作る能力を持っているのです。
以上いろいろお話してきましたが、正しい知識を持っていれば、生活習慣病を予防し、治し、最終的には生活習慣病から身を守る方法を自ら知って、実行できるはずです。このことは、必要最低限の薬を有効に効かせるためにも重要です。今日のお話で、薬を飲む理由あるいは飲まなくてもよい理由、正しく飲まなければならない理由、我々が色々工夫し、考えながら薬を出している理由、が少しでも御理解していただけたらありがたいと思います。
講演会での質疑応答
Q.調子の良いとき、不整脈の薬を自分の判断で止めていますが問題ありませんか?Q.これから北海道は冬になりますが、特に注意しなければならないことはありますか。すぐいきなり外に出ないとか…。
Q. 納豆について質問します。STVの「みのもんた」の番組でやっていたのですが、納豆は1回80g以上食べないと効果がないと言う話があったんですが…。
A. (先生:効果と言うのは何の効果ですか?)ビタミンでも何でも、大量にとれば良いということはなく、どんな食品もバランス良く摂ることが一番大事です。