| No62 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート
(4/5)

板本 孝治氏
手稲渓仁会病院脳神経外科主任医長
札幌市では、渓仁会病院のリハビリ部長がすばらしいパスをつくりました。およそ2,000項目にわたる情報データについていろいろな職種ごとにやりとりができるものをつくりました。
札幌市全体で脳卒中の病院を中心に、そして、脳卒中の回復期を担う病院を中心に集まって、脳卒中地域連携パスネット協議会を2008年につくりました。代表は、現在、北海道大学、当時札幌医科大学の寳金脳外科教授がやっております。
これによって、急性期病院と回復期病院をクリニカルパスで結ぶことができるようになりました。
また、退院された患者についても、急性期病院からでも回復期病院からでも退院情報提供書により情報が送られることになっております。
このような脳卒中地域連携パスは、全道の13地域で行われており、そのうち、6カ所で札幌のパスと同じものを使っています。現在、全道で3,000例から4,000例ぐらいの数になっています。
ところが、ここで問題が起きてきました。それは、急性期、回復期の病院間は非常に充実しているが、在宅でかかりつけ医になると、その後にどうなっているのかを把握できなくなりました。
そこで新たに循環するものを考えました。患者がかかりつけ医から急性期病院へ行ったり回復期病院へ行ったり、あるいは、リハビリ施設でも患者がパスを持って回れることができないかと考え、それが循環型連携パスという形になりました。
この目的は、再発予防です。それまでの連携パスは、急性期と回復期の間で患者の機能回復を目指すものですが、新しい循環型パスは、再発を予防することが第一義的な目的になり、「脳卒中あんしん連携ノート」として2011年に誕生いたしました。(図6)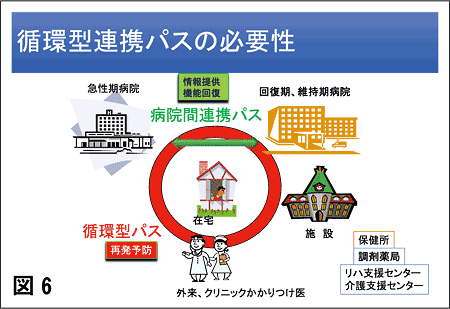
やはり、代表は、寳金教授です。そのほか、三浦哲嗣先生や札幌医大の三國先生、私などが運営委員をしています。道庁、厚生労働省からの補助金で運営され立派なホームページもあります。
このホームページを見たい方は、「あんしん連携ノート」と検索していただければ一番最初に出てきます。それはなぜかというと、日本全国で一番最初につくっているからです。熊本県の「くまモンの脳卒中ノート」もこのノートを参考にしています。さらには香川県も「脳卒中あんしん連携ノート」という名前で参考にしているとのことです。
では「脳卒中あんしん連携ノート」について簡単に説明していきます。
脳卒中の場合、再発予防を第一義的な目的とします。そのため、退院時の患者の情報と、退院した後、かかりつけ医、あるいは、脳外科の専門病院での通院情報をきちんと記載して、共有することです。そのため、患者自身がノートを持って歩き、かかりつけ医と専門医の間を循環します。そして、そのデータをウェブ上に登録し、電子データにします。
ノートには血圧手帳や糖尿手帳、心房細動手帳、診察カードなどを入れる内張りの袋がついて、これ一つを持っていればいつでも病院に行けるようになっています。
ノートの基本構成は半分ぐらいは患者のための教育的内容です。疾患の理解や予防治療薬の理解、危険因子についてです。
つぎに連携パスの部分について説明します。退院情報、患者情報、外来に通院して、薬をちゃんと飲んでいるか、検査しているかを記載します。そして退院した後の予定表には、外来のかかりつけ医の先生のところに行って、身長、体重はどうだ、ヘモグロビンA1cの値がどうか、血液検査の値がどうか、たばこを吸っているか、吸っていないか、薬をちゃんと飲んでいるかどうかというようなことをチェックしていただきます。
そして、これを6カ月ほどためて、脳卒中専門医、あるいは、心筋梗塞の専門医のところに行って評価をしてもらいます。それと同時に専門的な検査をします。これでかかりつけ医の日常の生活管理と専門医の専門的な検査を合体させることができます。

