| No62 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート
(5/5)

板本 孝治氏
手稲渓仁会病院脳神経外科主任医長
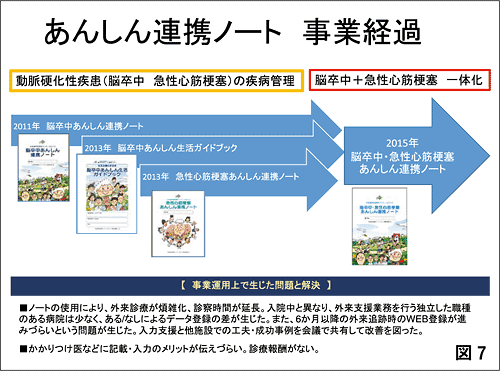
つぎに「あんしん連携ノート」の事業経過について説明します。(図7)
「脳卒中あんしん連携ノート」は、2011年に始まり、ガイドブックという副読本もつくりました。これは大変評判がよく、売ってくれないかという人もいますので検討しています。そして、2013年から「心筋梗塞のあんしん連携ノート」が始まりました。ただ、この二つは、やることもほとんど同じで、基礎疾患が同じだからまとめることになりました。そこで、2015年に「脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノート」ができ上がりました。
では、このノートが実際に効果があったのか説明します。このノートのデータには、脳卒中の場合、1,700症例ぐらいが既に登録されています。その中で危険因子保有率を見てみると、高血圧が圧倒的に多く、ついで動脈硬化性疾患、そして、脂質異常が多いことがデータからわかります。
また、脳梗塞予防薬をちゃんと飲んでいるかも知ることができます。退院6カ月の時点では、不良、つまり、飲んでいないという人が0.36%です。1年の時点で1.4%ですから、飲まない人が100人に1人です。これはどれぐらいの値かというと、通常、きちんとフォローされていないと半年、1年で飲まなくなる人は20〜30%いるといわれています。これは、かかりつけ医との連絡不備など、いろいろなことがあります。例えば、歯の治療をするときにやめてしまってそのままなどです。ノートを使って、循環すると、1年でわずか1.4%という数字まで落とすことができます。
抗凝固薬、納豆を食べてはいけないワーファリンや新しいノアックという薬はもっと厳密にコントロールされ、退院半年で0%、1年で1.4%、1年から2年が経過した人でも0%と、完璧にコントロールされています。このような利点があります。
実際に脳梗塞を再発したかどうかを見るものがこれです。(表1)退院半年で438人の人がノートを持ってきています。そのうち、3%の人が脳梗塞の再発、もしくは、ステント治療を受けています。半年後で3%です。1年後で0%でした。道内のある地域で、医師の人口が高いところですが、あそこで数年前にやった調査のデータは1年間の脳梗塞の再発率は8%から10%でした。だから、この数値はかなり低いと言えます。
もちろん、バイアスがかかっていまして、ノートを持っている人は大体自宅に帰っていますから、元気な人が多く、理解力もあります。しかし、それでも1年間で3%以内であるという数値は非常に効果があったということになるだろうと思います。
一方で、肺炎や骨折の入院が年とともに増えます。こういうことも患者の在宅の生活においては気をつけなければいけないということがわかります。また、循環連携パスが終了して、やめてしまったという数は、最初の半年でかなり多くなっております。こういった客観的なデータを見ることもできるというメリットがあります。
「脳卒中あんしん連携ノート」を使用するメリットは、心筋梗塞もそうですが、専門医と患者とかかりつけ医を信頼で結ぶということです。一つの形になるものがあるとちょっと違うのだということだと思います。
基礎疾患のコントロールを共有して、良好な状態を維持できる可能性があり、結果として、通院、服薬の自己中断がなくなり、それによって脳卒中の再発予防効果が期待できます。実際に少なくなっているようだというようなことがわかりました。
先ほどから言ってきましたが、脳卒中、あるいは、心筋梗塞でも予防、再発予防の一番のかなめは、きちんとかかりつけ医を持つことです。そして、専門医と密に連絡して、全身状態の管理をしっかりすることが一番の近道だということを申し添えておきます。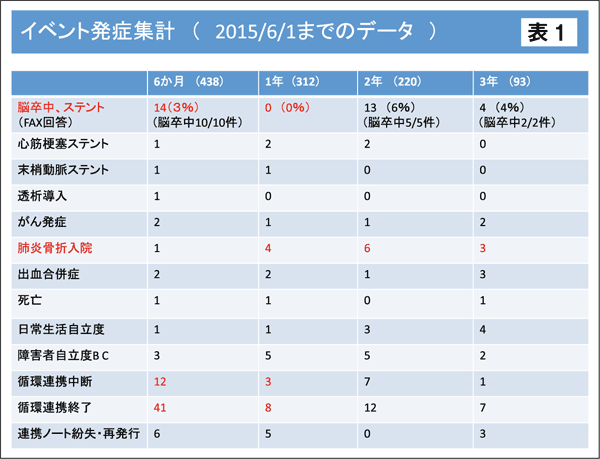
座長・長谷部直幸先生(旭川医科大学 循環・呼吸・神経病態内科学教授)
脳卒中は心筋梗塞と同じく危険因子をしっかりコントロールしていかなければならないそうです。最近血液をサラサラにするお薬がたくさん使われ脳梗塞を予防しておりますが、場合によっては出血が止まらないという合併症の恐れがあります。まずは血圧をしっかりコントロールすることが大事だとお話しいただきました。

