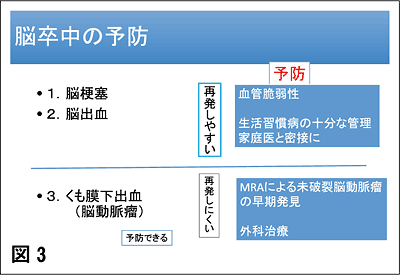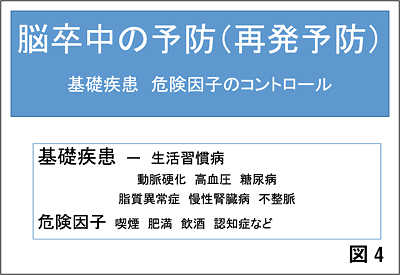| No62 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
脳卒中の再発予防とあんしん連携ノート
(3/5)

板本 孝治氏
手稲渓仁会病院脳神経外科主任医長
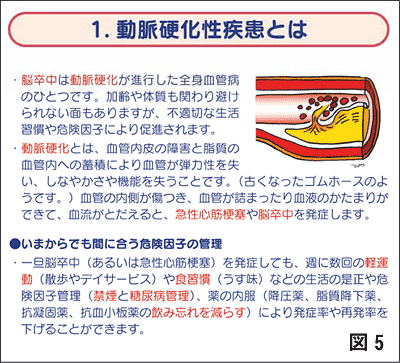
もう一度おさらいしますと、脳梗塞、脳出血は全身の病気ですから、再発しやすい病気です。
原因が血管脆弱性によるため生活習慣病の十分な管理、家庭医と密接に治療していかなければなりません。くも膜下出血は、発見することがポイントです。その結果、治療するかしないはまた別な問題となります。(図3)
今言った脳卒中の予防、特に梗塞と出血に関して、基礎疾患、危険因子について説明します。(図4)
危険因子としては高血圧、糖尿病、脂質異常、コレステロールが高いというものです。LDLという悪玉コレステロール、中性脂肪などがあります。
また、腎臓病も脳卒中、心筋梗塞に大いに関係があります。もちろん、喫煙もそうです。
さらに大事な危険因子があります。それは、心房細動という不整脈です。普通、心臓は同じリズムを刻みますがリズムが全くばらばらになる不整脈のことを心房細動と言います。心房細動によって心臓の中でできた血栓が脳の血管に行って詰まる脳塞栓症の原因になります。
予防するためには、直接、動脈硬化とは関係のない薬を使います。以前によく使っていたものでワーファリンという抗凝固薬です。納豆を食べてはいけない薬と言えばわかりますね。ビタミンKが入った納豆や緑黄色野菜などを食べると薬の効果がなくなります。しかも受診のたびに血液検査をして、薬の効きを調べなければならず不便な薬です。
今は、それを改善した、全く違うノアック(NOAC)という新しい薬の集団が出てきました。これは、食べ物の影響を受けません。さらに血液検査をする必要がありません。ワーファリンに多かった出血の合併症が少ない大変いい薬で、今、かかりつけ医の先生は検査する必要がなくなるので、どんどん使い始めています。
一方、動脈硬化、血管脆弱性による脳梗塞にはどういう治療をするか、あるいは、予防治療をするかといいますと、抗血小板薬を使います。(図5)こういう動脈硬化性のものに対して、抗血小板薬が、主に3種類が使われています。昔はほとんどアスピリンが使われておりましたが、現在はシロスタゾール、プラスグレル、クロピドグレルという薬が使われております。ジェネリック医薬品もたくさん出ています。
これは、血液をさらさらにする薬と表現されるものです。でも、本体は、血管の内膜がどんどんと厚くなっていくのを防ぐ薬です。さらさらになるのは若干の副作用と言わなければいけません。
脳梗塞の治療方法は、二つの違う種類の薬を使い分けなければなりません。心臓から行くのか、脳の血管自体が弱くなって起こるのかによるということです。
先ほど言いましたが、一次予防、つまり、なっていない人の発症を抑える、それから、二次予防、なった人の再発を予防するということです。一次予防でも二次予防でも、脳卒中の場合は、ほとんど同じです。
脳卒中になった場合に心臓と違うのは、体に障害が残ることです。だから、機能回復を行わなければなりません。また、再発予防もしなければならず、やることが増えてきます。そのため、発症してすぐ急性期の病院に行って、急性期の治療をします。脳卒中専門の病院では、大体1週間から3週間ぐらいでその病院を退院することになります。その後、機能障害が残っていれば回復期リハビリに行きます。そしてリハビリをしても、家に帰らず療養型病院に行かなければならない場合もあります。
こういう経過を経て、急性期と回復期や療養型を結ぶ地域連携クリニカルパスが開発されました。
このクリニカルパスのかなめというのは、治療や機能回復の標準化、高品質化、どこでも同じ高い程度の医療を受けられるということです。そのために、共通の用語、共通の評価基準を使うことが重要です。同時に、その結果をフィードバックしてうまくいったのかどうかを検証します。