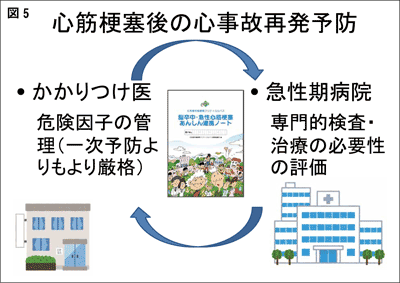| No61 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
心筋梗塞の予防と再発予防
(4/5)

三浦 哲嗣氏
札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 教授
北海道地域連携クリティカルパス運営協議会とは
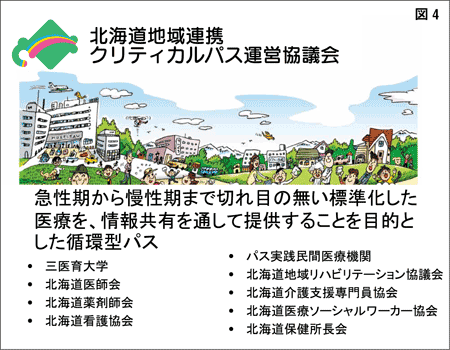
平成22年に北海道の医療計画に沿って北海道地域連携クリティカルパス運営協議会が設立されました。(図4)
設立の目的は急性期から慢性期まで切れ目のない、どこに住んでいても標準化された、同じレベルの医療を提供するためです。リハビリあるいはかかりつけ医、専門医など、それぞれの職種で情報を共有することができます。そしてかかりつけ医と専門医の間を患者が行ったり来たりいわば循環型の医療を提供しています。
この協議会に参加している病院の患者さんは、「脳卒中・急性心筋梗塞あんしん連携ノート」とアイディー番号を受け取ります。この中には病気や薬、検査の説明がありまして、患者がこのノートを持ってかかりつけ医と専門医を循環することになります。
現在、多くの医療施設が参加しており、札幌が一番多く、急性心筋梗塞が22医療施設、脳卒中が25医療施設です。そして各三次医療圏に少なくとも一つの施設が参加しております。
具体的には、まずかかりつけ医の先生には先ほどご説明した危険因子を管理してもらい、あんしんノートに記載してもらいます。メタボリックシンドロームのコントロールの具合はどうか、高血圧の具合はどうかなどです。
しかし、残念ながら、患者が心筋梗塞を起こすと、救急車を呼ばなければいけません。119番をすると、まず、向こうから火事ですか、救急ですかと聞いてきます。救急ですと答えてください。次に、何丁目何番地と聞いてきますから、今電話しているところの住所を答えてください。そして、どうしましたかということについて説明すると同時に、救急車がくる前に救急処置をしなければいけません。
急性心筋梗塞の場合は、発症、つまり胸が痛くなってから詰まった血管を開かせるまでの時間が短ければ短いほど、死亡率を低くすることができます。
約6時間以内に病院にたどり着き、詰まった血管を再疎通させるのが理想です。病院にたどり着けば、死亡率は10%以下となりますが、全体では病院にたどり着く前に半分ぐらいの方が亡くなっています。それを防ぐため、街角にあるAEDを使った除細動が行われています。
それでは、北海道ではどれぐらいの時間で救急車がやってくるか。平成21年、平成22年データによると、急性心筋梗塞を起こし、救急要請があった357名の場合、119番をしてから救急車が病院に到着する時間は、平均で3.5時間です。中央値は80分であり、1時間半足らずですから、北海道の救急隊というのは非常に優秀です。
ところが救急要請をしない場合、中央値で305分、平均で半日ぐらいになりますから、救急車を呼ばないと確実に手遅れになります。
先ほどAEDの話をいたしましたが、ああいう命を失うような悪性の不整脈に対する治療として、最近では埋め込み型の除細動器があります。ショックを体の中からかけることができる機器も急性期病院で入れられるようになっております。急性期病院では、心筋梗塞に対して閉塞した冠動脈を再び疎通させます。
あるいは心不全が起きればその治療をして、慢性期の合併症の予防方針を決定します。心不全をどうしていこうか、不整脈については除細動器を入れなければいけないか、リハビリテーションをするか、ここまでを急性期病院で行います。次の段階ではリハビリテーションをして、社会復帰に向けての治療をします。
その後はかかりつけ医の出番となります。最新のデータによると、心筋梗塞に一旦なった人を5年間フォローした場合には5年間で死亡率が2割ぐらい、心臓による死亡率が1割ぐらいになります。この成績は、海外と比べてもかなり良好ですが、これでわかることは、心臓ばかりを見ていてもだめです。心臓以外の死亡率が10%ということは半分の患者さんが心臓以外で亡くなっているのです。
ですからかかりつけ医の役割が非常に大きくなります。心筋梗塞に一旦なりましたら、二次予防ということで、一次予防よりもより厳格に管理が必要です。もちろん、心筋梗塞以外の病気についても適切に管理することが必要になります。
急性期病院では、専門的な検査、治療の必要の評価を心筋梗塞後の半年あるいは9カ月、1年後にチェックします。つまり、あんしん連携ノートの中に患者の情報がたくさんありますので、これを持ってかかりつけ医に診てもらい、定期的に急性期病院で診てもらうという循環型の連携パスが北海道で行われています。(図5)