| No61 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
心筋梗塞の予防と再発予防
(3/5)

三浦 哲嗣氏
札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 教授
クリティカルパスとは何か
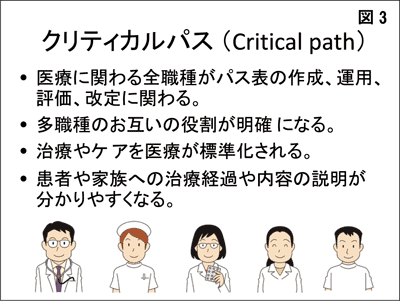
危険因子を管理すること、急性期の治療をすること、リハビリテーション、二次予防、つまり再発予防することは、たった一人の医師、看護師、栄養士ではとてもできないことがよくお分かりいただけると思います。そのため、クリティカルパスあるいはクリニカルパスと呼ばれているものが必要なのです。(図3)
まずはじめにスケジュール表を作成します。検査あるいは診療の手順内容を最適化し、一番いい形を決めます。表を一旦つくってしまうと、その結果が良かったか、もうちょっと良くしなければいけないかなど、医療の質を向上させるための一つの方法論ができ上がります。
これを作成するのは、医師一人ではなく、医療にかかわる医師、看護師、栄養士、あるいは、リハビリテーションの人など、みんなでつくります。
このスケジュール表は病院の中で使うもの、あるいは、紹介したり逆紹介したりなど、病院との連携で使うもの、さらに、地域全体で使うものがあります。
たとえばカテーテル検査のスケジュール表をつくるとします。入院した最初の日にはアレルギーをチェックする、薬を点検する。検査の当日には検査結果や点滴の量はどれくらいか、検査が終わった後にどういうことをチェックするか、薬は何を使うかという表をあらかじめつくっておきます。
そうすると医師が何をしようとしているか、看護師が完璧にわかるわけです。また、手順に落ち度がないか確認できます。
最近、マンションのくい打ちが届いていなかったというニュースがありましたが医療の場合でも、医師が看護師に指示をしたつもりでも、それがうまく行われていなかったというのでは大変です。そういった意味から、こういう手順表をつくるのは大変有用です。医療安全の上でも、医療の質の上でも大事だということがわかります。
このクリティカルパスは、医師、看護師、薬剤師、栄養士、作業療法士など、医療にかかわる全職種の人が使いますので、全員でつくります。
そうすると、お互いの役割が明確になります。また、Aさんに対する診療とBさんに対する診療が異なるわけではなく、標準化されます。そして、患者や家族への治療内容の説明が非常にわかりやすくなります。こういったメリットがありまして、このパスが大変使われるようになりました。
病院の中のパスのほか、医院から大きな病院への紹介、逆紹介、病院から検査の依頼がある場合など、誰々さん、よろしくという単純なことではなく、こことここ、あるいは、こことここが連携して、先ほどのような手順書をつくってお互いに点検することにより、無駄な検査をなくし、質のいい医療連携をもたらします。

