| No61 |
病院のチームワークで脳卒中・心筋梗塞を予防する取組:北海道地域連携クリティカルパス
心筋梗塞の予防と再発予防
(2/5)

三浦 哲嗣氏
札幌医科大学 循環器・腎臓・代謝内分泌内科学 教授
一次予防と二次予防
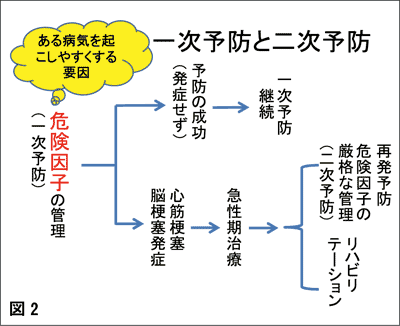
病気に対して、予防するためにはどうしたら良いかです。これには一次予防と二次予防があります。(図2)
今回は、脳梗塞と心筋梗塞を例に挙げますと、まずは一次予防というのは病気にならないようにすることです。そのためには危険因子の管理が必要となります。
危険因子とは、脳梗塞や心筋梗塞を起こしやすくする要因のことを言います。これをちゃんと管理し発症させないのが一次予防です。
次に残念ながら脳梗塞や心筋梗塞を発症してしまった場合には急性期の治療をし、リハビリをして再発しないように危険因子を厳格に管理します。これが二次予防です。
つまりならないようにするのが一次予防で、なってしまったものが再発しないようにするのが二次予防ということです。
では、危険因子について説明します。
病気の成り立ちは、まず危険因子があると血管が不調になり、腎臓、脳、心臓など、各臓器の機能が低下して、そうした臓器の障害が重症になると最後に亡くなります。
心筋梗塞、脳卒中の重要な危険因子は、高血圧、糖尿病、コレステロールや中性脂肪が高いこと、また、喫煙、肥満、それから、慢性腎臓病です。
生活習慣がどれぐらい大事なのかある高齢者の写真を例に説明します。
この写真には一卵性双生児なのに、そこには同じ年齢に見えない二人が写っています。その原因は、喫煙習慣の有無でした。つまり、同じ遺伝子を持って生まれても、喫煙して、不摂生を長期間続けた結果、顔形の老化として表れたのです。
残念ながら、北海道では、女性の喫煙率が全国ナンバーワンです。外来で若い女性にたばこをやめなさいと言っても、たばこをやめると太るからやめないと言うのでその双子の写真を出して「老けるよ」と言うと、ちょっと考えてくれます。
今お話したように、危険因子には、高血圧、糖尿病、脂質異常、たばこを吸っているか吸っていないか、慢性腎臓病があり、それらがあるかを確認します。
次に、大事なのは、発症リスクの評価になります。
例えば、高血圧があったとしても、それがどの程度重大か、心筋梗塞になるにはどの程度危険があるかを測ります。なぜなら同じ程度の高血圧でも、脳卒中や心筋梗塞の危険の度合いは異なります。高血圧は、1度、2度、3度という具合に血圧の高さによって分類しています。しかし、血圧が同じだったら危険が同じかというと、そうではありません。要因によっては、上が160、下が100未満の比較的軽度な高血圧でもリスクが非常に高い人がいます。
なぜかというと同じ高血圧でも、既に動脈硬化による病気がある場合や狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、足の血管が狭くなる末梢動脈疾患だと一度診断されている場合には非常にリスクが高くなります。
そのほか、糖尿病や慢性腎臓病、メタボリックシンドロームの場合にもリスクが非常に高くなります。
比較的軽度の高血圧でも糖尿病、あるいは、狭心症がある場合には、それらがない人とは薬の量が違うことになりますし、あるいは、目標の血圧が違うというのは、再発のリスクが違うからです。
ということで、高血圧、あるいは、コレステロールが高い方でも、こういう病気がある、あるいは、別の危険因子をたくさん持っている場合には心筋梗塞予防のために管理は非常に厳格にしないと十分な予防ができません。逆に言うと、こういうものがなければ、それほど薬をたくさん飲まなくてもよいことになります。
今お話したようなリスクに合わせて危険因子の管理方法を選びます。もしリスクが非常に高ければ速やかに薬を使って早く下げることになりますし、あまりリスクが高くなければ生活スタイルを変えることですみます。
それでは、どうすれば良いかというと、まず減塩です。1日の塩分を6グラム以下にします。今食べている塩分よりも4.6グラム減らしたら血圧がどうなるかというと、上の血圧で4〜5mmHgぐらい下がりますし、体重を5キログラム減らしても同じぐらい下がります。また、毎日、30〜40分の運動をしても4mmHgぐらい下がりますし、お酒を減らしても3mmHgぐらい下がります。ですから、日常生活を工夫していただくと、血圧がかなり下がります。また、こうすることで薬も非常に効きやすくなることがあります。
このように、まず、危険因子があるかないか、そして、高血圧がどれぐらいリスクとして大きいかを踏まえた上で管理方法を選択していきます。最終的には、血圧にしてもコレステロールにしても、どれぐらいの数値に持っていくかが重要なので、その点については主治医の先生によくご確認いただきたいと思います。

