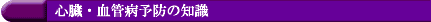 |
NO.18
|
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」
を踏まえた動脈硬化性疾患の予防と運動療法の重要性
(1/3)
国家公務員共済組合連合会斗南病院
副診療部長/循環器内科科長
松井 裕 氏
はじめに
超高齢化社会を迎えたわが国では、動脈硬化性疾患の中でも心筋梗塞等の冠動脈疾患を含む心疾患と脳梗塞等の脳血管障害による死亡は、総死亡の約23%を占め、悪性新生物による死亡と匹敵する主要な死因となっています。また、動脈硬化性疾患は平均寿命と健康寿命の乖離の大きな原因となっています。このような社会背景に基づき、2018年に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(脳卒中・循環器病対策基本法)」が成立し、この基本法によって規定されている「循環器病対策推進基本計画」が2020年に閣議決定され、動脈硬化性疾患の発症、再発予防は喫緊の課題です。日本動脈硬化学会は、1997年に高脂血症ガイドラインを発表して以来、最新のエビデンスを取り入れ5年ごとに改定を重ねてきましたが、2022年7月に「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」が公表されました。そこで、同ガイドラインを踏まえた動脈硬化性疾患の予防と運動療法の重要性について紹介します。
動脈硬化性疾患とは
動脈は、心臓から送り出された血液を全身に運ぶ血管です。酸素や栄養を運ぶ役割を担っており、健常な血管は弾力性があってしなやかですが、加齢やさまざまな危険因子によって硬く、厚く、狭くなります。これが動脈硬化です。血管が硬くなるともろく破れやすくなり、厚く、狭くなると血流が悪くなって必要な酸素や栄養が体のすみずみに届かなくなります。血管が閉塞すると、臓器や組織は細胞が壊死を起こし、心臓であれば心筋梗塞を、脳であれば脳梗塞を発症します。心筋梗塞や脳梗塞は、自覚症状がほとんどなく突然発作が起こることも多くあります。近年は医療技術の進歩により、心疾患、脳血管疾患の死亡率は低下傾向にありますが、その後のQOL(生活の質)の低下や介護をする家族の負担等が問題となっています。
動脈硬化の危険因子
動脈硬化は加齢に伴って起こりますが、危険因子が多くなるほどそのリスクは高まり、進行が早くなります。主な危険因子としては、脂質異常症、高血圧、糖尿病、喫煙、内臓脂肪型肥満などがあり、それら一つ一つの管理が大変重要です。
1 脂質異常症
血液中の脂質には、LDLコレステロール(LDL-C)、HDLコレステロール(HDL-C)、トリグリセライド(TG、中性脂肪)などさまざまな種類があります。LDL-Cが増えすぎると動脈硬化を促進することから、悪玉コレステロールとも呼ばれています。HDL-Cは余分なコレステロールを回収することから、善玉コレステロールと呼ばれています。これらのバランスが崩れた状態が脂質異常症で、LDL-Cの割合が高くなると動脈硬化が進行します。またTGの増加は、肥満を引き起こすほか、悪玉コレステロールの性質を悪化させます。
2 高血圧
血圧が高い状態が続くと、血管内壁を傷つけ、LDL-Cが血管内に入りやすい環境を作り、血管に負担をかけ、動脈硬化を促進します。また、心筋梗塞や脳梗塞を起こす引き金ともなります。
3 糖尿病
高血糖の状態が続くと、インスリンの働きが低下し、血液中の脂質が増えます。とくに食後高血糖は白血球など血管内壁への付着物を増やし、動脈硬化を発症させる原因になります。
4 喫煙
喫煙は活性酸素を増やし、血管内壁に入ったコレステロールの酸化を促進します。また血管を収縮させ、高血圧の原因になります。
5 内臓脂肪型肥満
内臓脂肪が多くなると、血液中のLDL-CとTGが増え、動脈硬化のきっかけとなります。また、内臓脂肪が多い状態を放置すると、高血圧や糖尿病を引き起こし、動脈硬化を促進します。


