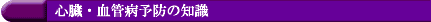 |
NO.18
|
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」
を踏まえた動脈硬化性疾患の予防と運動療法の重要性
(3/3)
国家公務員共済組合連合会斗南病院
副診療部長/循環器内科科長
松井 裕 氏
運動療法の重要性
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」では、動脈硬化性疾患の予防のための運動療法の重要性について各種データを用いて紹介しています。
1 1日合計30分以上を週3回以上(可能であれば毎日)、または週に150分以上、中等度以上の有酸素運動を実施することは、血清脂質を改善します。非運動群と比較して、有酸素運動療法群でHDL-Cが上昇するという報告が多く、LDL-C、TGを低下させることも報告されています。有酸素運動は血清脂質の改善以外にも、血圧をはじめとした他の危険因子を改善することがメタ解析で報告されており、効果は多面的です。一方、心血管疾患の既往者や高リスク者の運動療法については、主治医への確認が必要な場合があります。
2 レジスタンス運動(筋力トレーニング)は血清脂質を改善します。レジスタンス運動には筋力向上だけでなく、糖尿病患者の血糖改善効果などQOLを向上させる可能性や、有酸素運動との併用効果も報告されており、レジスタンス運動が禁忌でないケースでは推奨されます。
3 食事療法に加えて運動療法を併用すると、血清脂質の改善がより期待できます。食事療法はLDL-C、TGの低下に有効ですが、運動療法と併用させると、より大きな効果が期待できます。
4 有酸素運動および身体活動量の増加により動脈硬化性疾患の予防が期待できます。非活動群に対して、有酸素運動を含む身体活動の多い群では、冠動脈疾患、脳卒中、心血管疾患および総死亡数が少ないことが示されています。その効果は、低量、低強度の身体活動でも観察されました。
5 座位時間を減らすと動脈硬化性疾患の予防効果があります。座位行動の時間を減らすこと、座位行動をこまめに中断して、長時間の座位行動継続を避けることで、動脈硬化性疾患の予防が期待できます。
このように、動脈硬化性疾患の予防に対する運動の役割は大きいものと考えられます。加齢とともに動脈硬化は進行していきますが、できるだけ早期から運動を意識的に行い、生活習慣の改善を図ることで、動脈硬化の予防効果を高めることが重要と言えます。
おわりに
「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」をもとに、動脈硬化性疾患とその予防について概説しました。動脈硬化性疾患は、単一の原因で起こるものではなく、脂質異常症、高血圧、糖尿病、喫煙、内臓脂肪型肥満の各々を管理することが基本です。健康診断などで定期的に検査を受け、要精査の場合は病院を受診してください。また、リスクチャートなどを見ながら、この五つのうちどこに自分の発症リスクを高める要因があるかを把握して、対処しやすいところから取り組むことが必要です。動脈硬化性疾患の予防に有酸素運動が有効ということは確かであり、ガイドラインでは、ややきついくらいの強度で週3回以上(可能であれば毎日)30分、または週150分という運動療法の指針を示しています。
なお、日本動脈硬化学会のホームページでは、動脈硬化性疾患について詳細に解説されており、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版」や「動脈硬化性疾患発症予測ツール」もダウンロードできます。


