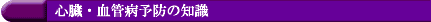 |
NO.15
|
高齢者の服薬
― 必要なお薬をキッチリ飲んで体調をよくしましょう ―
(2/2)
札幌医科大学保健医療学部教授
齋藤 重幸氏
4)服薬のアドヒアランス
アドヒアランスとは「患者が積極的に治療方針の決定に参加し、その決定に従って治療を受けること」を意味します。
元来、服薬は患者が医師の指示に従うこととして考えられていました。これをコンプライアンスといいます。
最近、治療の成功にはより積極的な患者側の関与が必要であることがわかってきました。その薬を飲む必要性や薬の効く仕組みを患者も理解することより、服薬の継続性が増すと考えられます。
しかし、高齢者では認知機能低下がみられる場合がありアドヒアランスの低下は否めないこともあります。表1に高齢者のアドヒアランスをよくするための工夫を示しました。
できるだけ少ない薬剤数にしてもらう。1日1回にする、食事に合わせて服用するなど簡便な服用方法にする。また、飲みやすい薬を選んで使う。あるいは、複数の薬剤を一つにまとめて飲みやすくする(一包化)など医師は服薬の工夫をするようになってきています。患者さんやその家族も残薬を減らすために、医師へ表1のような工夫を依頼してはいかがでしょうか。
ただし、薬によっては服用時間を変えられないもの、まとめられないものもあります。いずれにしろ、現在服用している薬を理解するためにも医師、看護師、薬剤師とのコミュニケーションを十分とることがご自身の服薬アドヒアランスを向上させるために大切です。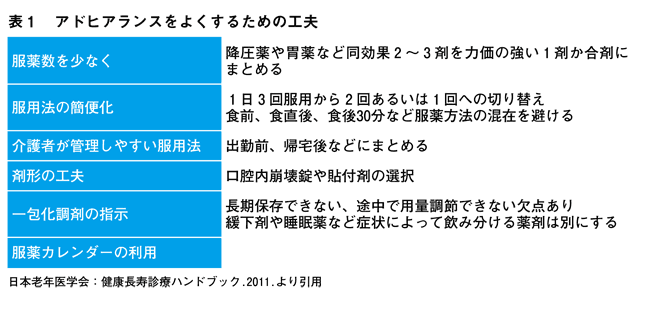
5)高齢者の服薬についての注意
ガイドラインでは全般的な注意点と薬の種類別の注意点が述べられています。全般的な注意では、高齢者で服薬にまつわるトラブルが増加する理由が示されています。
高齢者は複数の疾患を有するために、必然的に多くの診療科を受診することになり、多数の薬を服用するようになります。
また、慢性疾患が多いために薬を長期服用することも問題です。高齢者の病気の症状も定型的でないことが多く、病気の見逃しや、誤診断による誤った薬の投薬などが起こる可能性も高くなります。
さらに病気の本質的な治療というよりは、症状を改善させる対症療法が主となることも多くなります。
こうしたことは、薬の量が多くなることにつながり、薬物の有害事象の出現をもたらすのです。
入院例では高齢者の6〜15%に薬物による有害事象がおこっており、外来例では1年あたり、高齢者の10%以上に薬物による有害事象が発生するといわれ、60歳未満に比較して、70歳以上では1.5〜2倍の出現率となることが知られています。
また高齢者の入院の原因として3〜6%が薬剤を原因とするものとされ、長期入院、多臓器病変、重症化の要因になっています。
体調を良くしようとして出された薬によって、体調が悪くなるのですからまさに本末転倒です。だからと言って医師から処方された薬を勝手に止めてはいけません。それこそ冠履倒易でしょう。6)最近の週刊誌の記事について
上述したようにある一定の頻度で薬物有害事象が発生します。しかしながら服用する全ての人に起こるものではありません。医師は薬の有害事象の事もわかっていて患者さんに服用を勧めています。
最近、週刊誌で数回にわたり『飲んではいけない医者からの薬』などと題して薬の服用を止めるように勧める記事が載せられています。発行部数の多い雑誌ですので皆様の目に触れることがあったと思います。
これらの記事の印象を正直に言いますと、実にいい加減で無責任な内容だと思います。高名な医師へ取材したと記事には書かれていますが、その薬を服用している人には必ず不利益が起こるというような書き方で、有害事象を針小棒大に取り上げています。
適切でない服用を行えば有害事象の発生は増加するかもしれませんが、適切な服用が行われていれば、期待される効果を発揮し健康増進に役立つはずです。
記事を真に受けてお薬を止めることのデメリットの方がはるかに大きいと思えます。
疑問があればとにかく、医師、薬剤師に尋ねて下さい。薬を飲むことの必要性が分かると思います。症状を改善し、心臓病の予防をするための薬なのですから。服薬しなければ効果は出ません。


