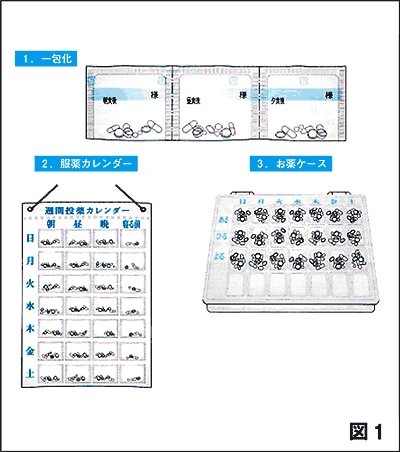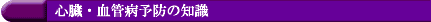 |
NO.15
|
高齢者の服薬
― 必要なお薬をキッチリ飲んで体調をよくしましょう ―
(1/2)
札幌医科大学保健医療学部教授
齋藤 重幸氏
本誌の読者は心臓病の予防や、循環器疾患の予防に関心のある方が多いと思います。心臓血管病(循環器病)は加齢とともに進行し、高齢者では心臓病の方も多くなってきます。
日本老年医学会は最近「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」(ガイドライン)を発刊しました。このガイドラインは医師、薬剤師、看護師などのために作られたものですが、薬を飲む側(患者)にも大切な情報を示しています。
今回はこのガイドラインから高齢者の服薬に関する話題を提供します。1)高齢者の特徴
世界保健機構(WHO)では歴年齢で65歳以上を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と定義しています。
内閣府の発表では平成26年の65歳以上の割合(高齢化率)は日本全体で26%を超え、北海道は28.9%、平成40年には40.7%になると推計されています。
もちろん暦年齢だけではなく老化には個人差が存在します。暦年齢に比較して実際はより若々しい方が多いことも事実です。
しかしながら、65歳を過ぎると健康を害する機会は増えてきます。高齢者では病気であってもはっきりとした症状が出にくく、ご本人が病気であることに気づいていないこともあります。
そして年齢を重ねるごとに病気が発症し、治療の必要の為に薬を飲む機会を増えてきます。わが国での75歳以上の後期高齢者では1日平均4.7種類の薬を服用しているとの報告があります。読者の中にはそれ以上だという方もいるでしょう。2)高齢者での薬の効果
薬剤の効果は、お薬の吸収、体の各臓器への配分、体の中での代謝、体からの排泄などの要因によって変化します。個人差はありますが高齢者ではこのような要因に変調を起こします。
特に問題となるのは体内の水分低下です。これは高齢者では渇きの感覚が低下して飲水量が少なくなるためだとされています。このため熱中症や脱水症になりやすくなります。
また、お薬の多くは血液中のアルブミンというたんぱく質に結合して運ばれますが、高齢者では血液中アルブミンが少なくなることから、お薬の血液中の濃度が変動します。
さらに、腎臓の機能が低下し薬が体の中に残りやすくなり、消化管からの薬の吸収力低下により十分に薬が体に入らないなど相反するような複雑な状態が起こります。
こうした結果、医師や薬剤師が想定した薬の効果とは異なる事が起こることがあります。薬の効果が強く出すぎたり、予期していた効果がでなかったり、想定外の作用で副作用が起こったりするのです。
3)高齢者の服薬状況
一般に高齢者では若年者に比較して薬に対する依存感が強く、医師からの服用の指示にはきちんと従う傾向であるといわれています。
しかしながら、同時に、飲み忘れ、飲み間違いも多くなります。残薬というのは医師から処方された薬を飲み残したり飲み忘れたりして余った薬のことをいいますが、平成27年には医師が処方した薬の15%が残薬となっており、日本全体で年間約3000億円を無駄にしていると報告されています。このためにどれだけ病気の回復が遅れ、また、新たな病気がどれ程発症してしまうことでしょうか。
必要な薬は飲み忘れないことが重要です。ガイドラインには、飲み忘れを防ぐ工夫が記載されています。たとえば数種類の薬を一包化したり、服薬カレンダーやお薬ケースを利用するなどです(図1)。