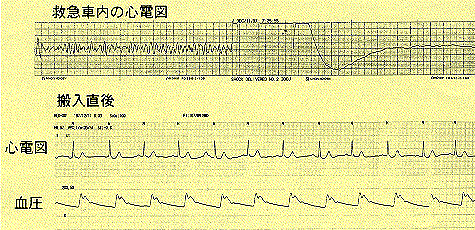| NO.10 |
突然心臓が止まったら(上)
救急蘇生法の知識と方法
(3−2)
迅速な電気的除細動
心臓の拍動が止まってしまう場合には、心電図でみると心臓の電気的活動が全くみられない心静止(図2a)と心臓を構成する心室の筋繊維が統率を欠いてそれぞれ全く勝手な方向に動いている状態で、心電図上は不規則な波がみえる心室細動(図2b)とがあります。
図2
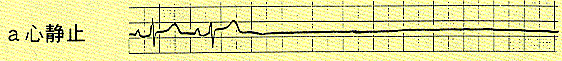
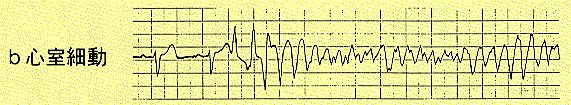
心室細動では心電図は波が見られるものの心臓は統制のとれた動きができなくなるために、細動出現の瞬間より心臓から血液の拍出は全くなくなり、心停止状態になります(図2c)。心静止に対しては一次救命処置を開始し、蘇生薬を投与して心拍再開を期しますが、心室細動に対しては一次救命処置のみでは心拍再開は期待できません。
図2
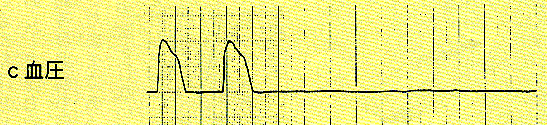
できるだけ速やかに電気的除細動を行なわなくてはなりません。心室細動発症直後に電気的除細動を行なえばほぼ全例で心拍が再開するといわれますが、時間が経過するに従い、除細動されにくくなり、救命の機会は減少します。以前は病院外で心室細動を起こした患者は一次救命処置を受けながら病院まで運ばれ、そこではじめて電気的除細動を行なって救命されていました。
現在は救急救命士にも、心肺停止症例に限ってですが、医師の指示を受けた上で三つの特定救命行為、
1.静脈確保ができるようになりました。
2.食道閉鎖式エアウェイまたはラリンゲルマスクによる気道確保
3.半自動式除細動器による電気的除細動
ただ、発症から119番通報までの遅れ、心電図で心室細動を確認しても心電図を電送して医師の許可を得るまで除細動できずその間の遅れ、除細動後心静止になった時に救命士は救命蘇生薬品を使用できないなどのため、大きな期待の割には救命士による救命率も最初の頃はよくありませんでした。
しかしその後、救命士が除細動して救命された例が身近でも次々に報告されるようになりました。最近札幌市で救命士の電気的除細動により救命された症例を示します。(図3参照)
64歳、男性Aさん。平成9年12月11日朝7時過ぎテレビを観ていた時に突然「うっ」とうめいて倒れ、妻の呼びかけに反応しないため、119番通報されました。4分後、救急救命士到着時には心肺停止状態で、ただちに一次救命処置が開始されました。心電図を記録したら上段に示すように心室細動でした。心電図を電送して確認を受けた後に電気的除細動を施行したところ図に示すように心室細動がとれ、札幌医大救急集中治療部へ到着したときには下段に示すように心拍が再開し、血圧も回復していました。自発呼吸兆候も回復したが意識は消失したままであったので、3日間脳低温療法を行ない、12月17日人工呼吸器を外したところ意識は完全に回復していました。日常生活に復帰しましたが、現在札幌医大病院第二内科に入院して突然の心停止を来した原因を調べています。
図3