| NO.10 |
突然心臓が止まったら(上)
救急蘇生法の知識と方法
(3−1)

札幌医科大学 救急集中治療部 助教授 東海林 哲郎
| 突然意識を失った人を見たら 1.大声で呼びかけ、意識があるかどうか確かめる 2.息をしているか、脈があるかどうか確かめる 3.速やかに119番通報、救命処置を開始する |
心肺停止状態
心臓は昼も夜も休みなく拍動して全身に血液を送っています。もし、この心臓の拍動がいったん止まると、その瞬間から全身へ血液が送られなくなり、脳へも血液は行かなくなります。
脳は酸素を十分含んだ血液がないと働きません。心臓の拍動が数秒間止まると失神し、それ以上続くと意識がなくなり、呼吸が止まり、顔や皮膚の色が土気色になります。4〜5分間以上脳への血流が止まると脳の細胞は死んでしまい、後から再び血液を送っても蘇(よみがえ)らないと言われています。また、突然、ものが咽喉(のど)につまって窒息したりして呼吸が突然停止してしまうと血液が酸素化されないため短時間のうちに脳の働きがとまり、心臓も止まってしまいます。
このように突然心臓や呼吸が止まって意識が失われてしまう状態を心肺停止状態とよんでいます。原因がいかなるものにせよ、止まったままではその場で死んでしまいます。救命のためには、まず、その場に居あわせた人がただちに救命処置、すなわち心肺蘇生術を開始することが必要です。
救命の鎖
突然の心肺停止例の救命蘇生率を向上させるために世界的規模で展開されているキャンペーンで、図1に示すように4つの輪のリンケージが必須、でそのどれが欠けても成功しません。
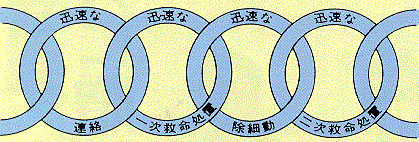
その1番目の輪は救急医療システムヘの速やかな連絡です。突然意識を失って倒れた人を見たら、まず、大声で呼びかけて意識があるかどうかを確かめ、次に、息をしているか、脈があるかどうかを確かめたら、速やかに119番通報すると共にその場でただちに心肺蘇生法の一次救命処置を開始することが必須です。
心肺脳蘇生法
呼吸や血液の循環がなんらかの原因で著しく低下したり、止まってしまった場合、その働きを体外からなんらかの方法で補ってやらないと生命を維持することができません。この手段のことを救急蘇生法といいます。救急蘇生法は一次救命処置と二次救命処置より成り立っています。
一次救命処置とは特殊な器具や薬品を用いることなくできる、医師や看護婦、救急隊員以外でも、その場に居あわせた人だれもが行なってもよいというより、行なうべき基本的な救命処置で、気道確保、人工呼吸、心マッサージからなっています。
だれがみても明らかに死亡している場合を除き、突然呼吸や心拍が止まった場合はその場に居あわせた人が一刻も早く、そして確実に一次救命処置を開始できるように、社会一般の人にこの一次救命処置をよく知って身につけてもらうことが大切です。


