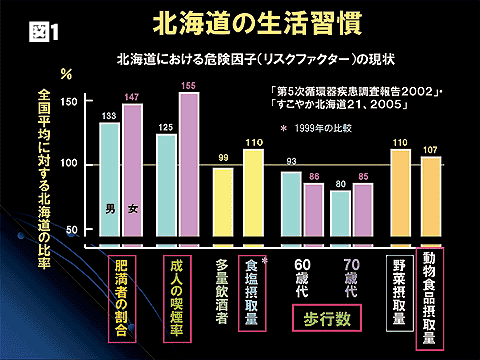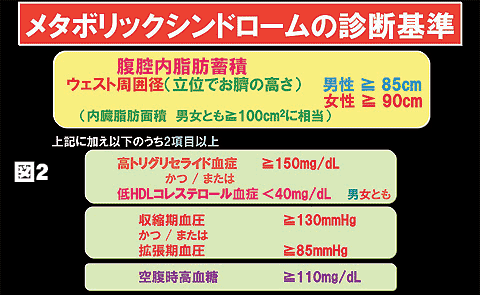| No.41 |
講演「生活習慣病の予防は幼少児期からが大切」
(2/3)
たばこ一服でご破算に
心筋梗塞も少しずつ増えていると申し上げました。心筋梗塞の原因になる危険因子としては、日本人では、高血圧と糖尿病と喫煙が重要です。男女別では、高血圧は男女とも大きな危険因子になっていますが、たばこは特に女性の心筋梗塞に非常に大きく関与し、糖尿病も、男性にもリスクになりますが、女性でより大きなリスクになっています。女性は更年期以降に太る方が多く、その結果、血圧、血糖、血中中性脂肪やコレステロールが高くなり、さらに、たばこを吸っておられますと、心筋梗塞のリスクが非常に高くなります。
★
心筋梗塞の都道府県別、年齢別の発症率を見ますと、男性も女性も、北海道が沖縄と並んで非常に高い地域になっています。これを予防するためには、先程申し上げました危険因子を減らす、つまりは生活習慣を変えなければいけません。まず高血圧の原因になる食塩の摂り過ぎに注意しましょう。食塩は1日6g未満、これは相当厳しい目標です。それから果物と黄緑色野菜、黄色、赤、緑色の野菜をできるだけたくさん摂りましょう。コレステロールや脂肪の多いものは控え目に、特に脂身の多い肉を控え目にし、動脈硬化を予防し、血液をサラサラにする効果のある魚を中心にしましょう。それから運動です。週にできれば2回、1回30分以上、急ぎ足で歩くことが勧められます。食事と運動を組み合わせて、体重が増えないように、目安はBMI(ボディマスインデックス)・体格指数が25以下、できれば22に近づけるようにしましょう。アルコールは適量です。ビール中ビン1本、日本酒1合、ワインは180cc。これらを全部足しても良いのではなくて、どれかひとつです。たばこは絶対だめです。一生懸命に生活習慣を修正しても、たばこを吸っていたら全部帳消しになってしまいます。
★
日本国民の食塩の摂取量は、1975年に14g近くでしたが徐々に減って、87年に最低で11.5gになり、その結果、高血圧が改善し、脳出血による死亡が随分減りました。ところが、その後、食塩摂取量は徐々に増えています。これは外食をする習慣が一般化してきたためとされています。外食で摂る食物は、日持ちをよくするために食塩の含有量が多くなっています。塩辛く感じなくても、食塩の含有量は多くなっています。ファーストフードや多くの冷凍食品にも食塩が多く含まれています。そういうものを多く摂るようになったために、また食塩の摂取量が増えてきたと考えられます。これを何とかしなければということで、医師会などが高血圧学会や厚生労働省にも働きかけ、国民に呼びかけ、最近、食塩の摂取量が徐々に下がってきております。しかし、なお目標の1日6g未満の2倍近くと目標に程遠い状況です。
★
北海道の皆さんの食塩摂取量は全国平均より少し多く、12gを超えています。北海道に住む我々は食塩を摂り過ぎていることを肝に銘じて、その摂取量を減らす工夫をする必要があります。お浸しには醤油はかけないで、小皿にとって付け醤油にする、あるいは、お酢、すだち、かぼす、レモンなどを使って食塩や醤油やソースを少な目にすることが大切です。減塩醤油という、食塩の含有量が少ない醤油も市販されています。このような習慣の徹底は幼小児期からすべきです。40歳を過ぎてから急に変えてといっても、なかなか変えられないことは、私ども、患者さんと接していて痛感しているところです。このような生活習慣は、お子さん、お孫さんたちが小さい時から見直し、習慣づけることが必要です。
食塩の他に、北海道が全国平均よりも多いのは肉類の摂取です。野菜の摂取が多いのは大変よいことです。しかし、喫煙率が男女とも、特に女性が高くなっています。さらに、肥満者の頻度が高く、これには運動不足も関わっています。60歳代、70歳代になると歩く歩数が全国の皆さんより大幅に少なくなっています(図1)。冬が長いせいもあると思いますが、屋内で運動することを考える必要がありますし、休みの日に屋内プール、体育館などを利用することも考えられます。
※CTスキャンなどで内臓脂肪量測定を行うことが望ましい。 ※ウェスト径は立位、軽呼気時、臍レベルで測定する。脂肪蓄積が著明で臍が下方に偏移している場合は肋骨下縁と前上腸骨棘の中点の高さで測定する。 ※メタボリックシンドロームと診断された場合、糖負荷試験が薦められるが診断には必須ではない。 ※高Tg血症、低HDL-C血症、高血圧、糖尿病に対する薬剤治療を受けている場合は、それぞれの項目に含める。 最近、テレビや新聞でよくメタボリックシンドローム(図2)について報道されていますが、これは、お腹の中に脂肪が溜まることが基本病態です。腹囲が男性85cm以上、女性は90cm以上なら不合格です。この数値は日本人のデータから割り出した内臓脂肪の面積が100cm2以上になる目安で、腹囲は立ってお臍の高さで計ります。女性が洋服などを作る時のウエストと場所は違います。お臍の周りです。このほうが大きくなります。女性の90cm以上は、ちょっと甘いという意見もあり、女性は75cmを超えたら要注意、90cmを超えたら赤信号と考えたほうがよいとの研究もあります。
★
まず腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上を満たすことが必須条件になります。その上で(1)血液中の中性脂肪、トリグリセリドが150mg/dlよりも高いか、かつ/または動脈硬化を予防するHDLコレステロールが40よりも低い場合、(2)血圧で上が130mmHg以上、かつ/または下が85mmHg以上、つまり正常血圧よりも少し高くなった場合、(3)空腹時血糖値が110mg/dl以上、つまり糖尿病の基準値126以上よりもっと低い110を超えたら黄色の信号ということで、これら三つの内どれか二つを満たしている場合をメタボリックシンドロームと呼ぼうということになっています。それぞれは軽くても、これらが一緒になると心臓血管病の非常に大きなリスクになるということが知られているからです。
★
先ほど北海道は全国平均より肥満の人が多いといいましたが、これは何とかしないといけません。メタボリックシンドロームは内臓脂肪症候群ともいいますが、この言葉を知っておられるかどうか、30代から50代の男女1,300人に訊きますと、知っていると答えたのは2.9%だけです。しかも、診断基準の腹囲が男性85cm、女性90cm以上と正しく答えた方は0.6%しかおられません。皆さん、この機会に是非覚えていただきたく思います。一方、内臓脂肪という言葉は75%の方がご存知ですし、お腹が出てきて心配している方が8割くらいいます。これらの内、最近1年以内に太ったと感じている人が50%、過去5年間に5kg以上太った人が12.5%です。これは、最近太りつつあるという方が多いことを示しています。
★
札幌医大の島本和明教授の教室が取り組んでおられる端野・壮瞥町の住民調査では、このメタボリックシンドロームに該当する方が男性17.6%、女性5.5%です。全国平均の男性12.5%、女性4.0%より高い数値になります。端野・壮瞥町の研究によりますと、メタボリックシンドロームの基準を満たす方が心臓血管病、心筋梗塞、狭心症、脳卒中の発症などで亡くなるのは、そうでない方の約3倍多いそうです。ちょっと血圧が高い、ちょっと血糖値が高いが糖尿病ではない、中性脂肪もちょっと高いなどと、それぞれは軽くても、これらが重なると大きなリスクになりますので油断してはいけません。ちょっと高いだけだから大丈夫、は通用しないということです。
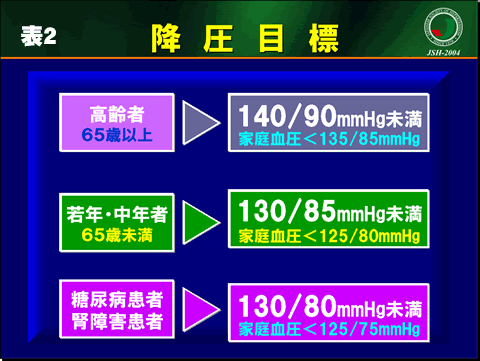
脳卒中、心筋梗塞、腎不全などの臓器障害の発症を防止するための目標とすべき血圧値はだんだん低くなってきています(表2)。65歳以上の高齢の方は、ゆっくり下げて最終的には140/90mmHgよりも低く、65歳未満の方は正常血圧レベルの130/85mmHg未満にしましょう。糖尿病や尿に蛋白が出ていたり、腎機能が少し低下している慢性腎疾患患者さんの場合には、さらに低く130/80mmHg未満にしましょう。ここでいう血圧値は病院や診療所等で測った数値です。家庭で測定した血圧値ではもっと低くなります。家庭血圧ですと、診療所の140/90mmHgに相当するのが135/85mmHgとされております。この辺をお間違えのないようにしていただきたいと思います。
★
もうひとつ問題なことは、ご自分が肥満傾向にあるとは思われても、高血圧であるとか、血糖や中性脂肪がちょっと高目といった、メタボリックシンドロームに該当し、心臓血管病のハイリスク状態にあることを充分に自覚していない方が非常に多いことです。循環器基礎調査によりますと、診断を受けた人の23.7%が高血圧で、その内、降圧薬を毎日きちんと飲んでおられるのは約半分です。10.3%の方が糖尿病と診断されましたが、治療をきちんと受けておられるのは1/3のみでした。約20%の人がコレステロールが少し高いと診断されましたが、その方たちも1/3しか治療を受けていません。高血圧で薬を飲んでいる方でも、130/85未満の目標を達成できているのは僅か1/4です。高血圧といわれても治療をしない方が半分おられ、治療をしてもその1/4しか適切に管理されていない―これは大変重大な問題です。
血圧計をお持ちで、お家で測っておられる方もいらっしゃると思います。私たちの血圧は一日の間に変動し、日中はやや高目で、夜睡眠中は下がり、朝目が覚める頃に上昇してきます。寝ている間は脳や筋肉も休んでいますので血圧は高くなくてもよく、朝起きる頃になると、きょう一日頑張らなければ、と血圧は上がってきます。高血圧の方は正常血圧の人に比べて血圧変動が非常に大きいといわれています。日中でも、昼寝をすると血圧は下がります。最も血圧が上がりやすいのは、朝方、目覚める前後、朝起きて1時間以内です。
★
このような血圧の日内変動から、家庭血圧は原則として1日2回お測りいただきたいと思います。まず朝起きて1時間以内です。起床後、トイレに行ってから、食事をする前に椅子に座って、2、3分してから測ります。もう1回は夜寝る前です。このように家庭血圧を2回測っていただき、かかりつけの先生に持参していただくと、24時間に亘る血圧コントロールに非常に役立ちます。朝飲んだ薬の効果は、翌朝、薬を飲む前頃が一番弱くなります。その時点での血圧を充分にコントロールしておかないと、脳卒中や心筋梗塞を予防できないことが知られておりますので、是非、朝起きて1時間以内と夜寝る前の家庭血圧をお測りいただきたいのです。
★
高血圧の基準は家庭血圧と外来血圧とでは少し違うと申しました。外来では140/90mmHg以上が高血圧ですが、家庭血圧では135/85mmHgを超えたら高血圧です。家庭では外来より低いのが通常とされています。少なくとも家庭で測った血圧は上が135、下は85より低くすべきと考えていただいて結構です。糖尿病や慢性腎疾患を持っている方の家庭血圧はさらに低く、125/75mmHg未満がお勧めです。
★
家庭血圧を測って下さっている患者さんがどれくらいいるのか調べました。昨年9月、高血圧学会を旭川で開催するにあたって、旭川市医師会の先生方にご協力いただき、カルテを全部調べていただき、家庭血圧を測ってそれをきちんと治療に活用されている患者さんはどれくらいいるかアンケートで調査しました。約25,000人の患者さんの内、42%しか家庭血圧を測っていないことがわかりました。高血圧学会が終わった後、もう1回調査したのですが、約5ポイントしか増えておりません。皆さんはどうでしょうか。できれば100%に近い方が、朝と寝る前に血圧を測るようにしていただくことが、脳卒中や心筋梗塞などを予防する上で極めて大切です。どうぞご家庭には血圧計をお備えいただき、測定を励行していただきたいと思います。
★
家庭血圧も含め、血圧をきちんとコントロールしますと、脳卒中や心筋梗塞を予防できるというデータが明示されています。この研究が行われた時の達成血圧レベルは、現在の降圧目標よりも高いレベルでした。ですから、今の血圧レベルでしたら、さらに脳卒中や心筋梗塞、腎不全などの発症を減らすことができます。脳卒中でしたら50%以上、心筋梗塞は30%以上減らすことができると思われます。
高血圧を治療し、認知症を予防
高血圧の患者さんは認知症(痴呆)になりやすいといわれています。それでは、高血圧の治療をすると認知症を予防できるのでしょうか。予防できるのです。60歳以上の高血圧の患者さんに血圧を下げるカルシウム拮抗薬を使いますと、アルツハイマーや脳血管性の痴呆を含め、認知症を半分以下に減らすことができます。高血圧を24時間にわたり厳重に管理することが、認知症を予防するためにも、非常に大事です。そのほかに、認知症の予防には一生懸命に運動すること、特に歩くことが大切です。一生懸命歩く人に比べると、歩く距離が少ない人ほど認知症になりやすいという報告があります。手を使った趣味をされたり、大きな声でカラオケを歌ったり、後で、らく朝師匠からお話がある、声を出して大いに笑うことが認知症の予防に良いというデータもあります。
★
先程メタボリックシンドロームの診断基準をお話しました。総コレステロールが220を超える高コレステロール血症や悪玉LDLコレステロール140超は危険です。善玉コレステロールは40以上にしましょう。善玉を増やすにはどうするか。一生懸命に歩くことと、適量のアルコールが良いとされています。中性脂肪を増やさないためには肥満を是正する、アルコールを飲み過ぎない、お肉、ケーキ、アイスクリームに加え、脂っこいものを控え目にするなどが肝要です。日本人の血中コレステロール値は、生活が豊かになると共にだんだん上がってきて、アメリカ人の男女を追いぬくぐらいになっています。アメリカでは癌よりも心筋梗塞が多く、それを予防するために日本食を見習っていますが、日本では逆にアメリカの食習慣(ファーストフードなど)のマイナス面をどんどん取り入れているようです。血中総コレステロール値や中性脂肪値に加え、悪玉コレステロール値は低く保ち、善玉コレステロール値を高目に維持することが心筋梗塞や脳梗塞になりにくくします。悪玉を減らし善玉を増やすようにすることが大切です。
 |