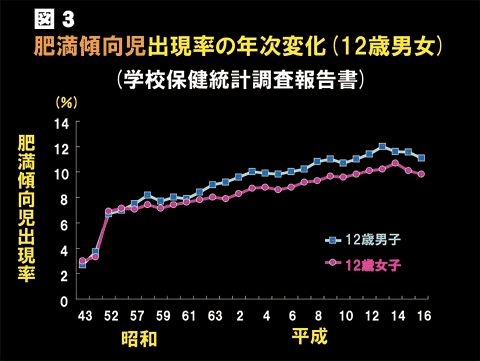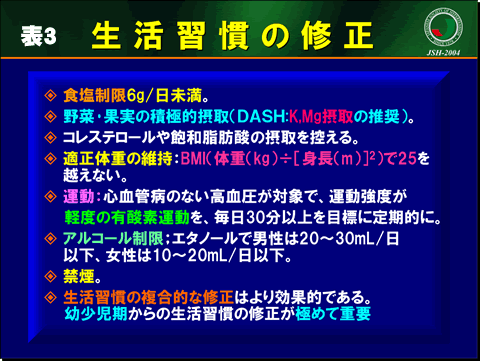| No.41 |
講演「生活習慣病の予防は幼少児期からが大切」
(3/3)
増える子供のリスク
日本の学童の血清コレステロール値が高くなっています。成人では女性は5人に1人(20%)が高脂血症という報告があります。これでよろしいのでしょうか。学童〜思春期にある皆さんのお孫さん、お子さんが成人になった時に、心筋梗塞や脳梗塞あるいは認知症を発症するリスクが非常に高くなることが危惧されます。日本の将来を担う子供たちの生活習慣病のリスクが増大していることをしっかり認識する必要があります。
★
動脈硬化がじわじわ進行しても、なかなかわからないものです。頚動脈に超音波を当てると血管の壁の厚みがわかり、これで動脈硬化があるかどうかを診断することができます。これは頚部の血管造影像ですが、脳にいく頚の血管がもう詰まりそうに、糸のように細くなっています。こちらも細い、ここもちょっと細い、こういう動脈硬化病変を持つ方が増えています。30〜40年前にはこのような患者さんはほとんど見られませんでした。生活が豊かになり、内臓肥満を中心としたメタボリックシンドロームの増加と共に、このような患者さんが急増しています。私たちの血管を輪切りにすると、血液がサラサラ流れるように血管の一番内側に内皮細胞があり、その下に内膜があり、次いで中膜があります。頚動脈のこの内膜と中膜の厚みを超音波で測ります。これをIMT(内膜と中膜の壁厚)といい、大体0.9mmを超えない薄さが正常です。これが厚くなってきたら動脈硬化が始まっているということになります。これは循環器を専門にしている先生方にお願いすれば測定していただけますし、私たちもFAXでその検査の予約をお受けすることを始めています。
★
血管壁にコレステロールが溜まってくるとプラークを形成し、同時に内膜、中膜が厚くなります。そこに血圧が高いといった刺激が加わると、内膜・中膜および被膜の薄い所が破れて、その下にある柔らかい脂肪の塊、ソフトプラークがピューッと飛び出します。これが冠動脈に起こりますと、突然、今まで全く症状がなかった方が、胸が締め付けられるような胸痛が生じ、心筋梗塞になったりします。この内膜・中膜やソフトプラークが厚くなればなるほど心筋梗塞や狭心症を発症しやすくなり、それで亡くなるリスクが高くなります。症状の前兆が全くなくて心筋梗塞になる方が約7割です。階段を上り下りしても、急ぎ足で歩いても、症状がないから大丈夫、というのは全く当てになりません。メタボリックシンドロームの基準を満たしている方は、定期的に精密な検査を受けること、肥満、高血圧、脂質、血糖異常を改善するように日頃より努力することが非常に重要です。
★
糖尿病の患者さんが50倍に増えているというお話をしましたが、糖尿病になりやすいのは内臓肥満の方や中性脂肪が高い方です。太っている方は高血圧があり、中性脂肪が高く、善玉のHDLが低いことが多く、中でも、たくさん食べて運動不足であることが一番大きく影響するといわれています。現在、日本では糖尿病の患者さんは約1,400万人、予備軍も含めるともっと多く、これが急増しています。糖尿病が腎透析導入患者さんの原因疾患の第1位になりました。これも大きな問題です。
日本の学童の肥満(図3)、血中脂質の高値とともに糖尿病が増え、将来が危惧されています。これは親の責任であり、保健・予防行政や私たち医者の責任でもあると思います。脂肪の多いおいしいものを自由に沢山食べて、それに見合った運動をしない生活の結果です。糖尿病になると心筋梗塞、脳血管障害、大動脈瘤、血管が詰まって足を切断、網膜症で失明、腎臓の機能悪化で透析、神経障害などが生じます。糖尿病は血糖が高いというだけではなくて、最終的には全身の血管が障害される病気です。症状が出た時にはもう遅く、そうならないように早期から充分な管理をすることが非常に大事です。子供たちの糖尿病が増え、コレステロールが高くなり、メタボリックシンドロームが増えています。黙って見過ごしていいものでしょうか。保健予防行政、医療従事者はもとより、PTAの立場からも、学校教育に生活習慣病の予防教育を反映させていかなければならないと思います。
★
血管をCTで見ますと、糖尿病の方では大動脈という太い血管にカルシウムが多量に沈着しています(石灰化)。心臓の栄養を司る冠状動脈にも大動脈の弁にも石灰化があります。腹部の太い大動脈にもカルシウムが沈着していて、腎臓の機能が大きく障害されています。糖尿病の方で、管理が悪いとこのようになりやすく、そうならないように予防することが極めて重要です。
★
体重(kg)を身長(m)の2乗で割ったボディマスインデックス(BMI)を25未満にすること以外に、皆さん、ご自分のウエスト(お臍の高さ)を測っていただき、先ほどの基準より低くするよう努力しましょう。女性は90cmになっていないから大丈夫というより、75cmを超えたら要注意です。男性の85cmは結構きつい数値だと思います。
国民栄養調査によると、男性は全ての年齢層で肥満者が増えており、女性は50歳代、60歳代になると増えています。ところが、肥満は大人だけではなく、子供にも及んでいます。食事の摂り方と運動不足のせいと考えられます。摂取総カロリー(総エネルギー)は増えておりません。炭水化物、お米をあまり食べなくなって、脂肪に富んだ肉類を中心とした洋食および間食を多く摂るようになってきました。脂肪の摂取比率が25%を超えますと、摂り過ぎと栄養学上はいわれていますが、幼少児期、学童、思春期の若者の脂肪摂取率は27.9〜28.9%と最も過剰になっています。家庭での料理の仕方、特に脂肪の摂り過ぎを修正するとか、外食では脂肪の多いものを控えるなどの根本的な見直しが不可欠と思います。これと、運動習慣の推進を図らなければ、肥満の子供の増加やメタボリックシンドロームの増加を防止することはできないと思われます。
★
北海道の喫煙率は、全国で男性はトップ、女性も札幌市はダントツでトップです。これも何とかしないといけません。北海道では高校生の喫煙率が高く、両親がたばこを吸う高校生は、約55%が吸うようになります。特にお母さんの喫煙の影響を強く受けやすいというデータが出ています。15歳以下からたばこを吸うと、癌になるリスクはたばこを吸わない人の30倍、26歳から吸うと7倍です。高校3年生の喫煙率は、1996年度の調査で男子25%、女子7%だそうです。これは親にも責任があることになります。日本全体で考える必要があると思います。
★
先ほど岡田基先生が伊藤記念研究助成を受賞された、「温泉に入ると血圧が下がり、動脈硬化の改善に良いようだ」というデータを少しご紹介させていただきます。旭川医大第一内科・長谷部助教授の外来に通われている20人の男性患者さんにご了解を得て、1週間に2回、旭川の隣にある東神楽町の温泉に、朝、晩2回入っていただいて、それを6週間続けました。そうすると、上の血圧(収縮期血圧)が最初152mmHgでしたが、6週間後の入浴前には142mmHgまで下がりました。1回温泉に入るだけでも17mmHgくらい下がります。午前中と午後にも入ると更に下がります。治療は全く変えておりません。食事指導もしているのですけど、6週間では体重や腹囲は変わりませんでしたが、反復して定期的に温泉に入ることによって血圧が下がりました。それと、動脈硬化の指標になる脈波伝搬速度を経時的に測定いたしました。脈波伝搬速度は低くなればなるほど血管のしなやかさが回復してきて、動脈硬化が改善する方向に行くということを示唆しております。血圧の値と関係なく、温泉に入ると血管がしなやかになる可能性を示すデータが得られました。さらに多くの皆さんにご協力いただいて長期間の温泉治療の効果を観察してみようと考えています。
★
最後にきょうの講演内容をまとめてみましょう(表3)。生活習慣の修正はメタボリックシンドロームの予防上、必須で大切なことです。食塩摂取1日6g未満はなかなか難しいことですけれども、皆さんと一緒に努力しましょう。野菜や果物を積極的に摂るようにいたしましょう。脂っこいものはできるだけ少な目に、肉は控え目に、魚を多く摂るようにしましょう。加えて、週2回、1回30分以上の早歩きなどの運動を励行して肥満にならないようにしましょう。お酒は適量、禁煙は極めて重要です。これらのことを組み合わせますと大きな効果が期待できます。
★
このような生活習慣の習得は幼小児期から始めることが極めて重要です。40歳を過ぎた方々の生活習慣の修正とその継続はなかなか難しく、あるいは65歳を過ぎた方から多くの楽しみを奪ってしまうのはクオリティ・オブ・ライフ(人生または生活の質)の観点から問題があります。少子化時代の生活習慣病の予防の視点からも、子供の時からの生活習慣の適正な指導、教育の徹底が図られなければ日本の将来は大変危うくなるのではないかと、危惧されます。行政と医療者(医師会、看護協会、栄養士会)、教育委員会、保育園、幼稚園、小・中・高等学校現場の皆さんに加え、PTAの方々のご協力が不可欠と思われます。
★
女性は、50歳を過ぎ更年期になりますと、骨粗鬆症になりやすいということで、カルシウムを多く摂ることが推奨されています。きょうは時間の関係でお話しできませんでしたが、カルシウムだけを多く摂りますと心筋梗塞になりやすくなるといわれています。マグネシウム摂取量が少ないとメタボリックシンドロームになりやすいことが報告されています。従って、メタボリックシンドロームや心筋梗塞を防止するためには、カルシウムとマグネシウムをバランス良く摂っていただくことが大切です。マグネシウムが多く含まれている食事は日本食です。海藻類、昆布、わかめ、海苔、ひじき、それから穀類、玄米、麦、お芋、大豆製品、本にがりを使った豆腐、カカオなどです。ナッツ類にも多く含まれていますが、これをカロリーオーバーにならないよう少量摂っていただく。カルシウムは牛乳に多く含まれ吸収されやすいのですが、脂肪分を減らす意味では低脂肪牛乳が勧められます。カルシウムとマグネシウムの比は大体1.5から2の間くらいにしていただいたほうが良いとされており、そのような比率の食品も市販されています。
★
冬の間の運動不足の解消については、北海道に住む我々はいろいろ工夫する必要があると思います。食習慣、運動習慣、禁煙などを妊婦さんや若いお母さん方がきちんと身につけ、また、保育園、幼稚園、小学校、家庭で小さい時から習慣づけることが日本の将来には非常に大切だということを改めて強調したいと思います。
笑いを生活習慣に
この後、らく朝師匠からお話がありますが、「笑いと健康学会」という学会が今年の2月16日にできたそうです。落語協会の会長の三遊亭円歌さんですとか上方落語協会の会長の桂三枝さん、喜劇人協会会長の大村昆さん、漫才協会会長の内海けいこさんたちが発起人になって作られました。笑いは健康に良さそうだ、ということは昔からいわれていたのですが、これを科学的な根拠に結びつけるような学会にしようということのようです。笑いは脳の働きにも良いといわれており、今後は笑いを生活習慣に積極的に取り入れていく必要があるのかもしれません。
★
この後のらく朝師匠のお話で大いに笑っていただきたいと思います。ご出席の皆様ご自身ならびにご家族の健康管理、増進、それからお子さんやお孫さんたちの生活習慣病の予防にお役に立てていただければ幸いです。
ご清聴どうもありがとうございました。
*本誌で落語協会の会長・三遊亭円歌さんを三遊亭円花さんと表記しました。お詫び申し上げ、訂正いたします。
 |