| No.41 |
講演「生活習慣病の予防は幼少児期からが大切」
(1/3)
旭川医科大学 内科学第一講座教授
菊池 健次郎さん
らく朝師匠の前座として、生活習慣病の予防についてお話をさせていただきます。
★
日本における主要な死因をみますと、従来、最も多かった脳卒中で亡くなる方が昭和40年から同45年あたりをピークに随分減ってきました。しかし、亡くなる方は減っても、発症率は決して減っていません。これが非常に重要な点です。それと、心臓病が少しずつ増えてきています。これらは私たちの生活習慣と密接な関係があります。日本は世界一の長寿国です。長生きしますと、癌になる確率が高くなり、癌で亡くなる患者さんが増えていますが、脳卒中など脳血管疾患と心疾患を合わせますと、癌に匹敵する数になります。
★
厚生労働省の統計によりますと、日本の医療機関、病院や診療所を訪れる患者さんで、男性、女性ともに最も多いのが高血圧です。次いで糖尿病、脳卒中、癌、コレステロールや中性脂肪が高い高脂血症、喘息、心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患の順になっています。日本における高血圧患者さんの数は約3,500万人とされており、65歳以上の高齢者の50%、つまり2人に1人は高血圧です。糖尿病の患者さんは、戦後50年で、約50倍に増えたといわれています。これは遺伝子の問題ではなく、私たちの生活習慣が原因です。ここに挙げた疾患は、気管支喘息を除くと、全て生活習慣病ですので、生活習慣を変えることによって予防することが可能な病気であるといえます。
★
北海道の状況はどうでしょうか。2005年の死亡率では、全国平均を100とすると、癌107、糖尿病110、心臓、腎臓、高血圧性の疾患が107、心疾患104で、いずれも全国平均よりも高く、脳血管障害は99でほぼ全国平均です。病気の頻度はどうかといいますと、高血圧は、女性は全国平均に近く、男性は少し少ないようです。しかし、動脈硬化性疾患の原因となるコレステロールが220mg/dlを超える高脂血症の方は、男性も女性も非常に多く、女性は全国平均の2.4倍、男性は1.8倍に達しており、これは大きな問題です。この状況は変えなければいけません。
★
脳卒中、心筋梗塞、狭心症などの発症率では、狭心症と心筋梗塞がじわじわと増えています。日本人はもともと脳卒中が多い国民で、前述しましたように脳卒中で亡くなる方は随分減っていますが、発症率はむしろ増加傾向にあり、特に脳梗塞が増えています。脳梗塞は、動脈硬化で脳の血管が詰まる病気です。脳の中の細い血管が詰まるのがラクナ梗塞で、日本人は元来ラクナ梗塞が多かったのですが、生活習慣の欧米化に伴って、動脈硬化を促進させる糖尿病と、前述しました、高脂血症の方が増えたため、比較的太い血管が詰まってかなり広範囲の脳の神経細胞が死んでしまうアテローム血栓性脳梗塞が増えています。
★
また、長生きして高齢になられますと、心房細動という不整脈の出る頻度が高くなります。心房細動になりますと、心臓の中(左心房)に血液の固まり(血栓)ができ易くなり、これが脳の血管に飛んで行って詰まることがあり(脳塞栓症)、この場合も広範な脳梗塞を起こします。心房細動は心電図を撮るとわかります。MRIでみますと、ラクナ梗塞は比較的小さいですが、アテローム血栓性脳梗塞は広範囲です。症状が全く無い方でも、MRIを撮ると脳梗塞が写ることがあります。これは症状の無い脳梗塞、つまり無症候性脳梗塞といい、そのまま放っておくと症状が出る梗塞に移行しやすいといわれています。
★
日本の65歳以上の方の寝たきりになる原因疾患は、約4割が脳血管障害、認知症が1割です。認知症も最近は、アルツハイマーを含めて、脳の血管障害が原因である可能性が指摘されており、そういう意味では、寝たきりの約50%が脳の血管障害に起因していることになります。長生きしても、寝たきりにならないで、元気に老後を過すことが大事です。脳血管障害と認知症にならないようにするのが、大変に重要な課題になります。脳卒中を予防するにはどうしたらよいのでしょうか。原因として最も大きく関わっているのが高血圧です。次いで、コレステロール、血糖が高いこと、心房細動が影響します。これらは生活習慣病の修正によって予防することができます。
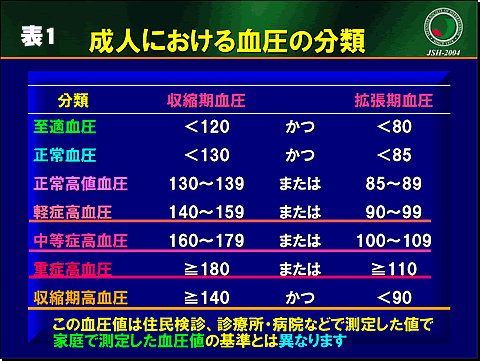
脳卒中には、高血圧が一番大きな因子であると申し上げました。日本高血圧学会が2004年に発表した基準を紹介します(表1)。家庭でではなく、診療所、病院、健診等で測った血圧値が、上が130よりも低く、下が85より低い(130/85mmHg未満)のが正常血圧です。昔は年齢に90を足して、といっていましたが今は全く通用しません。全部お忘れになってください。18歳以上の全ての年齢の方々で最も適切な血圧は、上が120よりも低く、下が80よりも低い値(120/80mmHg未満)で、年々、目標血圧値は低くなってきています。上が140、下が90より、いずれか一方、あるいは両方とも高い場合(140/90mmHg以上)を高血圧と診断します。ただし、これは一度測っただけの値ではなく、診療所やかかりつけの先生、健診で「高い」といわれたら、別の機会にもう一度以上血圧を測っていただき、コンスタントに140/90mmHg以上であることが確認された場合に高血圧ということになります。
 |

