| NO.17 |
心臓血管病と薬の正しい知識を得るために
(7−3)
いくつになっても治療する価値がある
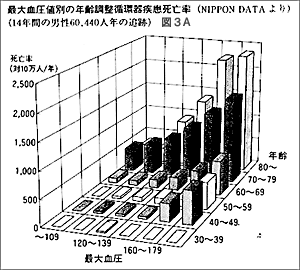
図3Aは血圧と年齢をみたものです。血圧が高い場合、年齢が上になればなるほど、死亡率が高いということを意味しています。ですから、年齢が高い方ほど、血圧をきちんと下げないといけない、ということを意味します。同じ血圧(たとえば160mmHg)でも40歳の方にくらべて、70歳の方の死亡率は3倍位高いですね。"私はもう80歳だから治療しなくても良い"という方もいると思いますけど、無駄だとは思わないで下さい。本人が決めることですけれども、いくつになっても治療する価値はあります。よりリスク(危険性)の高い患者さんを治療するほうが、医療経済からみて効率がよく、そのほうが死亡率低下に貢献できます。
今度は肥満についてです(図3B)。相対危険度(つまり糖尿病のなりやすさ)によって、つまり普通の人を基準(危険度1)にして、ある患者さんの危険度を評価します。相対危険度が10とは、普通の人の10倍危険性が高まった、という意味です。年齢が高くなればなるほど糖尿病になりやすくなり、大体70歳の女性の相対危険度は5くらい、男性だったら8くらいで、糖尿病になりやすいわけです。ところが、ここに肥満が加わった場合はこの相対危険度がジャンプして、女性も男性もその危険度がさらに2倍ぐらい上昇してしまいます。つまり、年齢が進むほど肥満は悪い影響をおよぼし、糖尿病を発症させやすくするということになります。さらに、ここに高血圧が加わると(血圧が20上がっただけで)、危険度は大幅に増加します。
ですから、少しでも肥満を是正し、血圧を下げることによって、相対危険度は大幅に下がることになります。この危険度のカーブも、歳をとるほど急激な弓状になりますから、逆に治療がうまくいった時の危険度の低下も年齢とともに非常に大きくなります。ですから、いくつになっても、そこから治療を始めたら糖尿病や生活習慣病になる可能性が低くできる、ということを意味しています。また、漫然と危険因子を放置していれば、歳を重ねるに従って病気になる可能性は高くなり、また悪くなりますよ、ということも意味しています。
先程、塩分の国際比較みたいな話しをしましたけれど、もう少し例をとって説明します。尿中のナトリウム排泄量といいまして、実際に塩分をどれだけ摂っているかということを比較した研究を紹介します(図4)。すると、高塩食の上位7つは全部、日本か中国か韓国の町です。これは食事を見たら分かりますね。日本料理、ラーメン、うどん、味噌汁とか全部含めてですが、中国料理、それから韓国料理というのは、欧米食に比べて、いかに多く塩分を使っているかということが分かります。「美味しい」と皆さんおっしゃると思いますけど、それはいいことですが、塩分がこんなにたくさん入っているということは知っておく必要があります。ところが1番下の方を見ると、ブラジルとかアメリカです。ハワイ他、いろんな州、大体普通の白人のアメリカ人ですが、実際に尿中に出た塩分は、日本人や中国人の半分以下ですね。つまり、摂っている塩分が半分以下ですから、尿中に出てくる塩分も半分以下です。ハワイは日本人の移民がたくさんいますが、食事は塩分をきちっと控えているものですから、こんなに尿中の塩分が少ない。元々ずっと日本にすんでいる人に比べたら、半分しか塩分を摂っていない、ということです。したがって、遺伝子的には日本人と同じか、きわめて似ているのに、摂取している塩分が半分ということはまさに食習慣そのもの違いを反映しています。入院して減塩食になれた患者さんが、"いままでの食事が塩からく感じる"とよくいいますが、これも塩分をひかえる習慣が身についた証拠で、食習慣を是正できたためです。
先程生活習慣により「病気になります」という話しをしましたが、ではどのように発症するのでしょうか。我々は普通の意味で、生まれた時にはまだ生活習慣はありません。これがいろいろな生活習慣の中で危険因子を身につけていって、生活習慣病に関して"高いリスク"になる。ある意味では自分で危険因子を少しずつ増やしていく。"男性"であること自体、生まれながらの危険因子ですが、女性は50歳を過ぎた更年期以降、危険因子が1つ増えます。それから糖尿病があれば1個増えます。タバコを吸っている人はまた1個増えています。こういうふうに危険性がどんどん高まっていき、ピラミッドの頂上がだんだんこう小さくなっていくように、悪い意味で選ばれた人が最終的に生活習慣病になります。ですから、少しでも健康な方に戻りたかったら、生活習慣を改善して、危険因子を1つずつ取り除くということが、病気の治療、予防につながります。
ここで血圧の話をしたいと思います。先程、だんだん血圧の基準が厳しくなると言いました。例えば、20年前患者さんに「血圧を下げましょう」と治療を勧めたのは、この第2ステージ、160-100mmHg以上の場合には「薬を使って下げましょうか」と言いました。今、国際基準が年々厳しくなっていまして、より下げた方が死亡率も下がるし、脳卒中で倒れて寝たきりになる確率も下がると、この間の10年、15年の研究で分かってきました。そして現在、140-90mmHg以上で高血圧と診断。薬を使うか使わないかは別として、「治療を開始しましょう」という話になります。減塩・運動指導などで治らない方は、やはり「薬を使いますか」ということになります。ですから、10年前あるいは15年前と同じ感覚では、治療は行われていません。病気の理解が進むと、その分予防のための指導も厳しくなってきます。
 |

