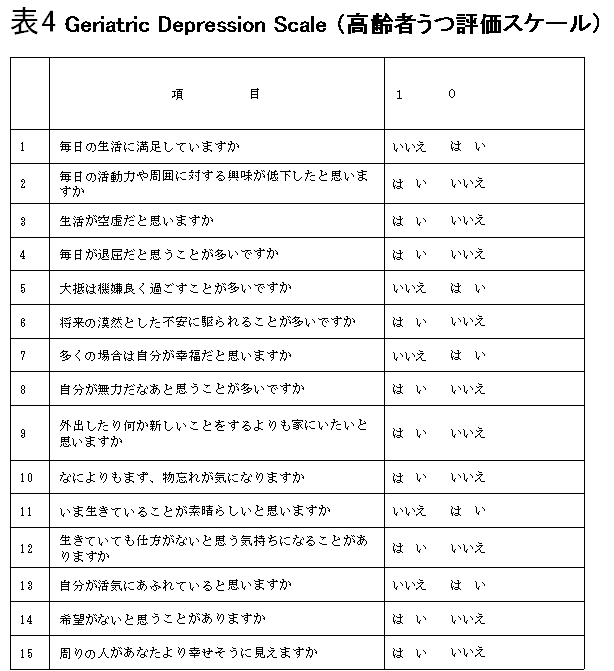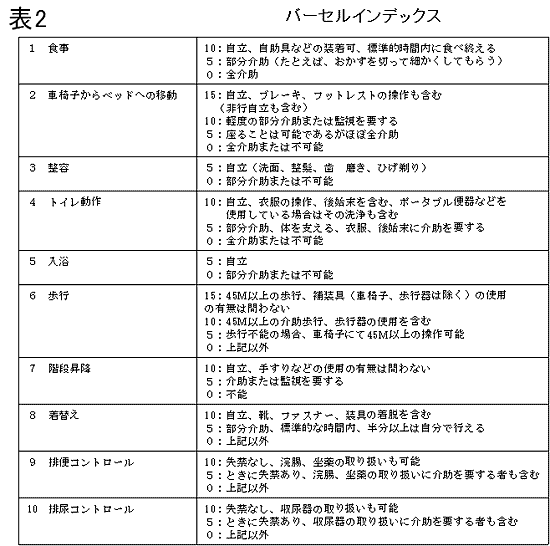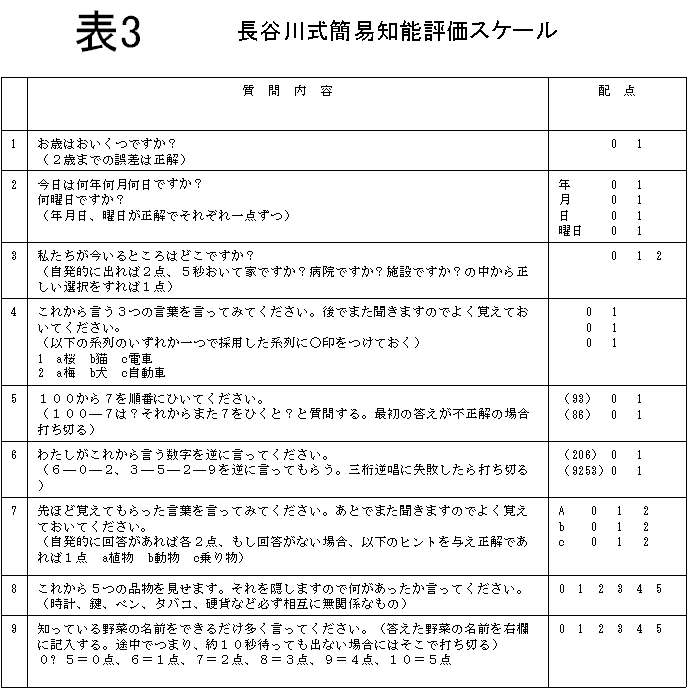| No.35 |
高齢者の体と心〜元気に老(ふ)けたい〜 (5/6 )
とかち健康フェア2004の講演から(平成16年11月21日・帯広市とかちプラザ)
寝たきりについて
寝たきりの方はどんどん増えていきます。寝たきりとは現在起きられない状況で、それが長期間続いていることです。精神的あるいは肉体的な障害がきっかけで、一日中、しかも長期にわたって臥床している状態が寝たきりと言われています。この数が年々増えており、今は150万人くらいですが、2025年には200万人を越えると予測されます。原因は圧倒的に多いのが脳卒中と骨折です。これらの疾患は寝たきりの原因の3割を占めます。全く起きることなく一日中寝込んでしまうと、筋肉の力が3%弱くなります。これは大変なことです。単純計算で、一週間で15〜20%の筋力がなくなってしまいます。さらに筋肉を動かさないことが続くと、関節の動く範囲が段々限られてきて、末期には固まってしまって全く動かなくなります。さらに、寝た状態が続くと脳の中に流れる血の量が普段よりも20%低下すると言われています。また、頭に入ってくる刺激の量が圧倒的に少なくなりその結果、頭の活動が低下します。
廃用症候群
病気になって具合が悪いので寝たきりになるわけなのですが、その寝たきりになることによってさらに体が弱くなり普段の生活に戻れなくなってしまいます。体を動かさないことが原因で起こす症状のことを廃用症候群と言い、その主な症状は次の通りです。筋肉が弱くなる、関節が動かなくなる、立ち上がると血圧が下がりやすくなる。体を動かさないので心臓も働きが落ちてしまい、少し歩いただけで動悸や息切れがするようになってきます。血管に血の固まりが出来やすくなります。エコノミークラス症候群という言葉を聞いたことがあると思いますが、これは、国際線の狭いエコノミークラスの座席に10数時間も同じ姿勢で乗っていると、足の血の巡りが悪くなった結果、静脈の中に血の塊ができやすくなり、その塊が肺に飛んで、ひどい人になるとそれでお亡くなりになります。このエコノミークラス症候群と同様に、寝たきりになった状態でも足の静脈に血の塊ができて、これが肺に飛んで重症になってしまう方がいます。
意欲がないのも廃用症候群の症状の一つです。刺激が少ないので痴呆も進んでしまいます。また床ずれが出来やすくなります。お尻の上の仙骨という骨は横になった時に一番体重がかかりますが、それが続くと血の巡りが悪くなってこの部分がくさってしまい、お尻に穴があいてしまいます。場合によっては細菌が感染して膿が出て広がることがあります。毎日きれいな水で洗って特殊な被覆剤で覆うなどしてケアをします。治療がうまくいくとピンク色をしたみずみずしい良性肉芽というものがが盛り上がってきて、さらにそれがだんだん皮膚に覆われていって最後は治るわけですが、ここまでいくのに非常に時間がかかります。1カ月かかる人もいるし数ケ月かかる人もいます。
国を挙げて寝たきりゼロ作戦を展開中です。「寝たきりゼロへの10カ条」というのがあって、脳卒中や骨折予防をしましょう、どんどんベッドから離れて動くようにしましょうなどと訴えています。大事なのは寝たきりにして動かない状況を続けるのではなく、高齢者には自分でできることがあったら身の回りのことをどんどんさせましょう、車椅子に乗れるのだったら車椅子に乗せてとにかくベッドから離して体を動かすようにしましょう、など高齢者の方に可能な限り自分のことは自分でするようにしましょう、と訴えています。
老年度
最後の話題は老年度についてです。老年度というのは正式には高齢者総合的機能評価といいまして、世界中で採用されています。入院している高齢の方は、人によっては知らず知らずの間にベッドに横になりがちになって、気がついたら寝たきりになってしまっている場合があるのですが、ともするとその変化に医療スタッフが気づかないことがあります。高齢者の患者さんが少しずつうつ状態になっていってもそれが分からないことがあり、少しずつ意欲が低下していった結果、医療スタッフが気づいた時には寝たきりになっていることもあります。そういったことを防ぐために、患者さんの老年度を適切な時期に評価することが推奨されています。当院でも最近始めました。
どうやって高齢者を評価するか。
老年度とは日常生活動作、認知機能、意欲、うつの度合いなどを評価します。日常生活動作とは私たちの日常生活に必要な動作で、歩く、食事をする、トイレに行く、着替える、お風呂に入る、歯を磨く、そういった健康な人が当たり前に行う毎日の動作のことです。具体的にどう評価するかというと「バーセルインデックス」というものがよく使われています。日常生活を10項目に別け、食事、車椅子とベッド間の移動、トイレ、洗面、入浴、歩行、階段の上がり下がり、着替え、排便、排尿などがどの程度できるかチェックします(表2)。合計したものをその人の日常生活度として評価します。
次に認知機能、判断する力です。これは痴呆の度合いとも関係しますが、時間の認識、場所の認識、言語能力、記憶力などを評価します。よく使われるのは「長谷川式簡易知能評価スケール」です(表3)。年齢はいくつですか、今日は何月何日ですか、あなたがいる所はどこですか、などとききます。これによって時間の認知、場所の認知が行われているか確認します。さくら、ねこ、でんしゃと言ってもらって少し間をおいてもう一回言ってもらうことで記憶力を評価します。さらに簡単な引き算をしてもらう、数字を逆に言ってもらう、5つの品物(鉛筆、スプーン、時計、鍵など)を見せたあと、何を見せられたか思い出してもらう、あるいは知っている野菜の名前をできるだけたくさん言ってもらう。評価したあとこれを点数化してその人の認知機能を評価します。
最後にうつの評価です。うつ病になると意欲がなくなってきます。高齢者の場合、うつ病が見逃される機会も多いため、この評価も非常に大事です。これも同じように質問用紙で行います。これは「高齢者うつ評価スケール(Geriatric Depression Scale)(表4)で「はい」か「いいえ」で答えます。毎日の生活に満足しているか、回りのことに対して興味が無くなったと思うか、毎日が退屈だと思うか、今生きていることがすばらしいと思うかなど質問し、「はい」「いいえ」によって点数化します。