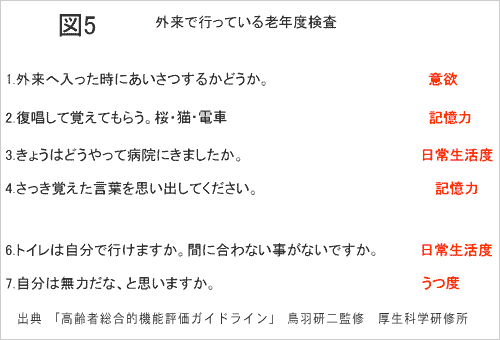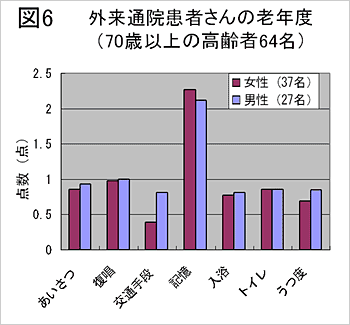| No.35 |
高齢者の体と心〜元気に老(ふ)けたい〜 (4/6 )
とかち健康フェア2004の講演から(平成16年11月21日・帯広市とかちプラザ)
痴呆の症状と介護者の苦悩
周辺症状の物盗られ妄想は女性に多いと言われています。痴呆の男性でよく認められるのは妻盗られ妄想だそうです。外出しようとすると「お前どこへ行く。おれと違う男に会いにいくのだろう。」と言ってしまいます。伴侶が不貞を犯しているのではないかと妄想を抱くわけで、介護している奥さんはたまったものじゃありません。こういう例のように、痴呆の周辺症状に対して介護者は非常に苦痛な気持ちを味わうことが多く、これが問題になります。先日の北海道新聞に掲載されていましたが(平成16年11月8日付北海道新聞)、介護者の心の傷は非常に深刻です。痴呆の高齢者は、介護者に向かっていろいろ攻撃的なことをする場合があります。先ほどあげた、介護者に向かって、おまえが盗人だろう、と決めつけるのはそのいい例です。そうすると、あってはいけないことですが、ついつい介護者の方もそういう高齢者に虐待してしまうことがあるようです。在宅で27%、施設でも20%こういったことがあるとの実態調査結果をその新聞記事は報道していました。痴呆の高齢者が訴える言葉を無視する、暴力を振るう、介護や世話を放棄する。こういうことはやってはいけないことなのですが、実際その場にいるとどうしようもなくなり虐待を行ってしまうようです。虐待をしてしまった介護者はさらに心の傷をおってしまう状況になります。
この新聞記事の中に家庭内虐待の事例があります。この中に今まで私が説明した痴呆についてのキーワードがたくさんあらわされていますので、それを説明します。66歳の女性の事例があります。介護する老人に薬を飲ませても、そのことを忘れてしまい、薬をまだ飲んでいない、と言われるので、「薬は飲ませたよ」と言うと、その方は怒り出して、介護者に向かって手当たり次第ものを投げるので、それ以後恐ろしくて無視するようになった、という話が掲載されています。これは痴呆の初期に見られる記憶障害からくるものだと考えられます。痴呆の人の記憶障害は、ある事柄を忘れるだけでなく、自分が忘れっぽいことも忘れてしまいます。ですから、忘れたことは自分のせいとは考えないで、他人のせいにしてしまいます。買い物に行っていっぱい買い込んだのに、全部忘れて家に帰る。お家の方が、どうしたと聞くと「レジで荷物を詰めていた人が私に渡すのを忘れた」と、ツラッとした顔で言い訳をする。そのため、周りの人は「なんだ、この人は」と困惑する一方です。このように、痴呆の周辺症状というのは、介護者を当惑させさらに怒りを覚えさせることがあります。痴呆の方の症状のありようをよく理解しておかないと、悲しむべき虐待を生む結果になりえます。
先程の新聞記事の続きですが、高齢者の方が同じことを聞いてくると「さっき言ったでしょう。何回も聞くんじゃない」と言ってしまう例が紹介されています。これは記憶障害になった高齢の方に対してとってしまった態度です。高齢者の方が、大きな声を出し、物や金を盗ったなどと介護者に言うため、介護者はついかっとなって高齢者に「出て行け」と言ってしまう例も紹介されています。物や金を盗ったと介護者に言ってしまう、というのは前にも説明した「物盗られ妄想」で、自分を介護してくれる人を盗人と思いこみ激しく攻撃します。どうして自分の世話をしてくれる人にこのようなとんでもないことを考えるのか、非常に不思議です。これについての解釈はいろいろありますが、ここでは長年痴呆老人の治療、ケアにたずさわれていた小澤勲先生の解釈を紹介します(岩波新書、小澤勲著「痴呆を生きるということ」参照)。物盗られ妄想は頼りたい気持ちを素直に表現できない人に現れやすいのだそうです。波乱万丈な人生を自力で乗り切ってきた自負がある人、親分肌でいろいろな人の面倒をみてきた人、そういった方がある年齢にになって介護される状況になった時、私はそういう介護をうけるような人間ではない、というプライドが邪魔をして、頼りたいけれどもそれを素直に表現できない、あるいは「なんで私が嫁の世話にならなきゃならないんだ」と頼りたい気持ちを心の中で拒絶してしまうのだそうです。そういう心の葛藤が介護者に対する攻撃として結果的に現れているのではないか、と言われます。こういう妄想を見せる人は漠然とした人恋しさ、淋しさを抱いていることが多いようです。それが、上手なケアをされて妄想が消失すると、攻撃の対象だった人を今度はとても頼りにするようになるそうです。物盗られ妄想が激しくて精神病院に入れられ、そこでケアを受けた方が、このような妄想が消えて非常に穏やかになり、それまでなじっていたお嫁さんが面会に行くと今度は大変喜んで、お嫁さんが帰る時には「また絶対に来てね」と、本当に頼りにされるような状況になったことを経験された方もいるとのことです。
痴呆になると、もう頭の中は普通ではないのだから、言っていることもやっていることも訳が分からないのではないか、と私たちは思いがちですが、もしかしたら、妄想の背景に何か気持ちの問題がある可能性があります。そこを注意深く見て理解することで、痴呆の方の介護も少しは楽になるかもしれませんし、虐待も減っていく可能性があるかもしれません。
親と子の同居と痴呆の関係
少し話は変わりますが、痴呆の方は日本だけでなく世界中にいますが、日本は先進国の中では多い方にはいります。70歳以上の男性のその後の余命の中で痴呆にならない割合を調べたところ、イギリスやフランスでは90%以上の割合で痴呆にならないで済んでいますが、日本ではそれらの国よりも少なく80%です。なぜ日本は痴呆の方が多いのか。原因のひとつにあげられるのは、日本では高齢の方が自分の息子、娘夫婦と同居する率が高いことです。これはいいことではないかと我々は思いますが、実はそうではない側面もあるわけです。諸外国に比べると高齢者が二世帯以上で同居している割合は日本では約半数ですがアメリカ15%、イギリス10%、スウェーデン、デンマークになると1%〜2%とほとんどの方は子供と同居しないで夫婦、あるいは1人で住んでいます。
日本では高齢者を在宅介護している方が多く、どうしてもマンパワーが不足しますので、具合が悪そうな高齢者を寝たきりにさせやすいのです。高齢の方もまわりにお世話をしてくれる人がいるとどうしても頼ってしまいます。これが痴呆を進ませるひとつの原因ではないかといわれています。このように、日本の在宅介護の問題点は高齢者を家族だけで介護しようとする風潮が強いことです。諸外国ではこういった考えはありません。自分たちで出来ないことはどんどん人に任せようと考えます。外国でよくいわれることは「Love is not enough (愛だけでは十分ではない。)」、愛情だけでは介護は十分にはできない、頼れるものは頼ってどんどん援助してもらおう、そういう発想です。
日本では介護サービスを受けることに抵抗を感じる人が多いのです。親の介護に他人の手を借りるのは親不孝だと思い、高齢者自身も福祉の世話になんかなりたくないと拒絶する風潮があります。しかし、家族だけでの介護は介護サービスを受けている場合よりも痴呆をつくりやすいことが判明しています。世間体だけで自分の親を痴呆にしてはいけません。利用できるものは利用すべきです。介護を受ける側にも意識の変革が必要ではないかと思います。
私の外来での経験
私が外来で行っているのに老年度の簡易検査というのがあります(図5)(出典「高齢者総合的機能評価ガイドライン」鳥羽研二監修 厚生科学研究所)。この検査は外来に患者さんが入ってくる瞬間からはじまります。まず患者さんが入ってきた時にあいさつをするかどうかを見ます。ガラッとドアを開けて「先生こんにちは」と言っていただけるかどうか。ジッと患者さんを見ていますが、私から患者さんへは決してあいさつしません。患者さんが自分から挨拶してくれるかどうか待ちます。はたからみると無愛想な医者だと思われるかもしれませんが、患者さんの評価をするときはあえてそうしています。自分からあいさつしてくれる人は、生きる意欲はまだ充分あると評価されます。あいさつしない人は、意欲にかける人に多く、実際にあいさつをしなくなった高齢者は、その後早くに御寿命を迎えられる、という結果も得られているそうです。私自身も同様な経験をしています。次に私が「さくら・ねこ・でんしゃ」と言い、患者さんに復唱してもらいます。その後、きょうはどうやって病院に来ましたかと質問してちょっと話題を変え、そのやり取りの後に、さっき覚えた三つの言葉を思い出してくださいと改めて質問します。痴呆のない方は大体全部言えますが、痴呆のある方は多くて二つしか言えない方が多いです。その質問の後、一人でお風呂に入れるか、一人でトイレへ行けるか、自分は無力だと思うか、と質問します。どうやって病院に来ましたかという質問では日常生活度を見ます。お風呂とトイレについての質問も日常生活度です。自分が無力だと思うか、という質問は、患者さんがうつ状態かどうかをみるスクリーニングになります。
表1.外来で行っている老年度検査の点数化
(高齢者総合的機能評価ガイドライン 鳥羽研二監修 厚生科学研究所をもとに演者(佐藤)が点数化を盛り込んだ。)あいさつするかどうか。 あいさつする。 1点 あいさつしない。 0点 復唱してもらう。 復唱できる。 1点 復唱できない。 0点 きょうはどうやって病院にきましたか。 自分でバス、タクシー、自家用車、自転車などで来た。 1点 他人に運転あるいは付き添われてきた。 0点 さっき覚えた言葉を答えてください。 3つ全て思い出せた。 3点 2つ思い出せた。 2点 1つ思い出せた。 1点 1つも思い出せない。 0点 お風呂は自分で入れますか。 一人で入ることができる。 1点 介助が必要。 0点 トイレは自分でいけますか。間に合わない事がないですか。 自分で行ける。失禁しない。 1点 上記以外。 0点 自分は無力だな、と思いますか。 無力だと思わない。 1点 無力だと思う。 0点
この7項目を外来で70歳以上の患者さん64名に聞きました。質問の回答内容によって表1のように点数化しました。その結果は図6の通りです。この図では男女に分けて示してみました。男性も女性も挨拶をするし復唱もできますが、病院へどうやって来たか、という質問ではでは女性の得点が少ないです。これは、高齢者の女性の場合、自分で車を運転する方が少なく、家族かご主人の車で来ることが多いせいです。記憶力のテストでは「さくら・ねこ」までは言えるが「でんしゃ」が言えない人が多かったです。
この男女別の比較では大きな違いはないようですので、別な観点で比較してみした。このスクリーニングテスト をしていて、一人で外来に入って来られた方と誰かに付き添われて来た患者さんの間に違いがあるのではないか、と漠然と感じていましたので、その観点で比較してみました(図7)。その結果、外来に一人で来た方と付き添われて来た方の間では全く結果が異なることがわかりました。両者ともほとんどあいさつはしてくれますが、「さくら・ねこ・でんしゃ」の記名力テストで違いが出てきます。誰かに付き添われて来た方は、一度覚えてもらったこれらの言葉をほとんど思い出せません。お風呂とトイレも一人で入れるかたが少ないです。人に伴われて来た方は恐らく痴呆もある程度進んでいて、日常生活にも差しさわりがある状態なのではないかと思われます。一人で病院に来られる方は痴呆がないか、あったとしてもごく軽い症状ではないかと考えました。それで次の段階として、痴呆がないと思われる外来に一人で来られた患者さんに普段の生活はどうされているか聞いてみました。
結果は以下の通りで、非常に興味深い内容です。趣味は将棋で老人クラブに2、3ヶ月に1回は行く。ダンスが趣味で友人が多い。十勝の杜病院は幕別にあるので、パークゴルフをしている人が多いです。毎日友人が遊びに来る。趣味は花いじり。このように多方面な趣味を持っている方が多いです。自分で自動車を運転して来た。デジカメが趣味でパソコンに写真を取り込んで加工している。和裁、折り紙を趣味とされている方。娘夫婦と同居していて、孫の世話で忙しい方。パークゴルフをするし卓球クラブにも入っている方。老人会の会長をしている方。俳句が趣味の方もいらっしゃいます。その方は最近よく辞世の句を作るそうで、そういうものを作られるのはまだ早いのではないですか、とその患者さんに言いましたところ、「先生、呆けちゃったら作れないでしょう」と返されてしまいました。押し花が趣味。子供が近くに住んでいる。日本舞踊をする。仲間内でマージャンをする。囲碁をしている。老人クラブにもよく参加する、などなどです。
お分かりいただけると思いますが、外来に一人で来られる方は自分の趣味をちゃんと持っているし、人とお話する機会を、意識的か無意識か分かりませんが、大事にしています。もしかしたらこのあたりが痴呆の進行を遅らせるひとつの方法かもしれないな、と思いました。