| No57 |
講演 患者さんのための循環器受診ガイド
〜気をつけたい症状とは?〜
(3/6)

筒井 裕之氏
北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学 教授
日本人の死因で一番多いのは悪性新生物、がんですが、そのつぎに多いのが心臓病と脳血管疾患、脳卒中です。この二つを合わせると、30%ぐらいの方が脳と心臓の病気で亡くなっています。この大きな原因の一つが心筋梗塞、心不全です。
では、つぎにその症状についてお話をします。まず狭心症とはどういう症状かというと前胸部から左側の手のひらの大きさ、もしくは胸全体が圧迫される、締めつけられるような感じがします。それが左の腕とか顎に広がっていくのを放散といいます。狭心症は、どういうときに起こるかが非常に重要です。動作時、体を動かしたときに起きるタイプと、じっとしていても起きるタイプの狭心症があります。ただ、痛み方は非常によく似ています。
胸が痛いということで患者さんが来ると、先生たちはどのあたりが痛いですか、どれくらいの範囲ですか、どれくらい広がりますか、どういうふうに感じますか、どんなときにありますか、そういうことを大体聞きます。狭心症は、先ほど申し上げましたように、一時的な心臓の酸欠状態ですから、病院に来たときには症状がないことが多いので、症状がでたときのことを詳しくお尋ねします。そこを詳しく思い出さないと、狭心症かどうか診断できません。したがって、皆さんの中で胸が痛い、これは狭心症かもしれない、心筋梗塞かもしれないと思われたら、どういう場所で、どれくらいの範囲で、どれくらいに広がって、どんな感じの痛みなのか、どういうふうにお感じになるかということをしっかり覚えておいてください。
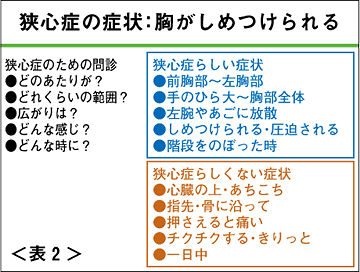
逆に、胸が痛いのですといって来られても、お話を聞いていて、あまり狭心症らしくないと診断することがあります。指で二、三本くらいの範囲ですけれども、心臓のこの上が痛い。胸のいろいろなところが痛い。指先一本とか針の先で突くぐらいのところで骨に沿って痛い。これは狭心症らしくありません。狭心症の場合は押さえたりすると痛みがひどくなることは通常ありません(表2)。それから、狭心症は心臓の酸欠状態ですから、症状は数分から20分ぐらいが通常です。それが、数日ある、一日中あるというのは狭心症らしくありません。しかし、狭心症らしいときもあるし、そうではないときもあるという方も結構おられます。その場合は、狭心症かもしれないということで検査を進めていくことになります。
患者と医師との会話が時々異文化交流だという話をしましたが、対応にちょっと困る患者さんがいます。どのあたりが痛かったかと聞くと、よく覚えていない。どれくらいの範囲かと聞くと、はっきりしない。広がりはどうかと聞くと、洋服を着ていたからわからない。どんな感じですかと聞くと、言葉では言えない。どんなときに痛いですかと聞くと、主人が家にいるときとか、これはどう理解していいのか本当に困ります。
狭心症が疑われるときに、検査としては心電図が非常に重要です。狭心症というのは、心臓が一時的に酸欠状態になりますから、症状がないときに心電図をとっても異常がないことが多いのです。しかし異常がないから狭心症ではないとは言えません。では、発作のときの心電図をどうやってとるのかというと、携帯式心電計を24時間以上装着して、心電図をとる方法があります。これをホルター心電図といいます。あるいは心臓に少し負担をかけるために、階段を上ったり、おりたり、ベルトの上を歩いて心電図をとります。これをトレッドミル負荷心電図といいます。
つぎに心臓の表面を走っている冠動脈という血管に動脈硬化があることになりますので、血管が狭いかどうかの検査をいたします。以前ですと、入院して、心臓の近くまでカテーテルという細い管を入れて、心臓表面の血管を造影しました。しかし最近では体の断層写真を撮るCT検査で心臓の血管を造影するのと同じように見ることができます。これは、入院する必要は全くありません。外来で静脈から造影剤を注射して写真を撮ることで、以前の心臓カテーテル検査、冠動脈造影と同じような検査ができます。冠動脈を全体に評価したり、冠動脈、病変、長さや形態を評価するということができます。ただ、脈があまりに多い場合や老化による血管周辺の石灰化により血管の中がどうなっているかが非常に見にくく、検査で十分にわからないこともあります。また放射線を使う検査ですので、被曝という問題もあります。

