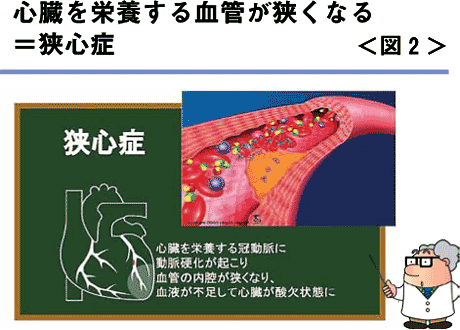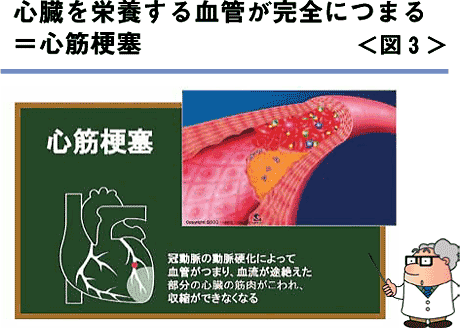| No57 |
講演 患者さんのための循環器受診ガイド
〜気をつけたい症状とは?〜
(2/6)

筒井 裕之氏
北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学 教授
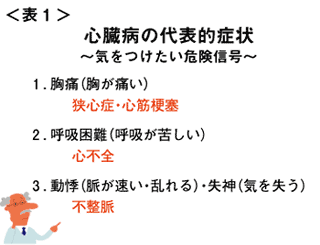
それでは今日具体的にお話ししたいのは、心臓病を疑う重要な三つの症状についてです。1番目は、胸が痛いという胸痛、2番目は、呼吸が苦しいという呼吸困難、3番目は、脈が速くなったり乱れたりという動悸です。そのときに気を失うのは失神と表現しますが、この動悸と失神という症状は関係がある場合があります。心臓病の代表的症状として胸痛を起こすのは狭心症、心筋梗塞という病気です。それから、呼吸困難を起こす病気として心不全、動悸を起こす病気として不整脈があります。ここに書いてある三つの症状、四つの病気は、心臓病の患者のほとんど全てを網羅していると言っても間違いではないぐらい、非常に多い症状です(表1)。
心臓の病気ですから、心臓が何をしているのかをまずお話しします。心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役目をしています。赤いところが動脈で、きれいな血液が頭、手、大動脈を通って、お腹を通って二つに分かれ足の先までつながっています。そして全身で一回使われた血液は、酸素の量が少なくなって、青いところの静脈を通って、また心臓に戻っていきます。酸素の量が少なくなっていますので、肺に運んで、そこでもう一回酸素を血液にたくさん含ませて、心臓に戻します。そして酸素の多い血液をまた全身に送り出しています。このポンプは、生まれてから一度も休むことがなく、80年生きるとすると、1分間に80回、1日に12万回、1年で4,200万回、一生で34億回動くことになります(図1)。その間に心臓自体はどうやって栄養を摂るかというと、心臓の表面に栄養を摂るための血管が走っています。それが先ほどご紹介した冠動脈という血管です。
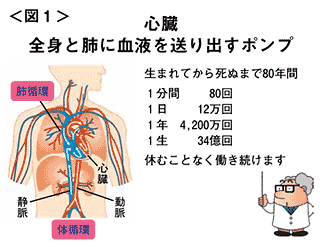
さて、ここに動脈硬化が起こると、血管がだんだん狭くなっていきます。そうすると、普通にじっとしているときはいいが、体を動かして血液がたくさん要る状態になると、酸素が足りなくなってしまう酸欠状態になります。これが狭心症です(図2)。
また、狭心症と関係がある病気に心筋梗塞という病気があります。しかし、心筋梗塞では狭心症のように動脈硬化のために血管が狭くなり、一時的な酸欠を起こすのではありません。この血管が完全に詰まることで血液が流れなくなり、心臓の筋肉が一部分壊れてしまいます(図3)。心臓はポンプですから、一部分でも壊れてしまうと全身に血液をうまく運べなくなり、そうすると全身にいろいろな障害が出てきます。これは心臓がポンプの働きをしているからです。