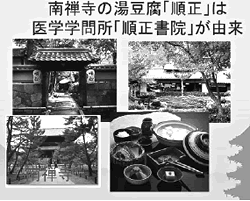| No48 |
京都新発見
〜お寺、診療所そして禁煙〜
(2/6)
先ほど長谷部先生の講演の中で、かかりつけ医の、診療所の話が若干出てきましたね。病院の先生は大変ですよね。病院の先生の負担をなくすという意味で、私たちのような町のかかりつけ医師、診療所、やはりそれを上手に利用していただくということが僕は非常に大事かなと。それはやっぱり何でもかんでも病院へ行くということは、皆さんそれはやめないかんと思いますね。上手に診療所の先生にかかって、診療所と病院を上手に利用する。病診連携といいますけど、それをやはりしていただくことが病院の先生の負担の軽減にもつながるということは、先ほどの講演を聞いて私のほうからぜひ申し上げたいなと思いました。
まず、京都新発見のナンバーワン。お寺の中に診療所がある、そういうお寺が京都にあります。京都名所になるかどうかはわかりませんけど、お近くに来られたら寄っていただいたら、ちょっとおもしろいですよ。これは本当に偶然なんですけど、私の診療所のほんのすぐ50mぐらいですかね。西側へ行ったところに、山脇東洋さんという方が初めて日本で解剖したところがあります。それは六角大宮という場所の壬生屯所。新選組に関してよく観光で来られる四条大宮の壬生寺近くのところなのですけど、その近くに昔から六角獄舎という牢獄があります。勤王の志士なんかはここでかなり惨殺されたり処刑されたりしているのですけど、そこで本当は我が国で一番最初に解剖がされました。したがって、日本近代医学のあけぼのの地という碑も建っています。勤王の志士のお墓もあります。
何でこんなことを言うのか。皆さん解剖言うたら、たしか杉田玄白ちゃうか、「解体新書」という言葉をよくご存じの方はお聞きになったと思うんです。ところが、杉田玄白の解体新書というのはもっと後なんですよ。杉田玄白はこれから後17年ぐらいたってから1771年に初めて解剖をしまして、それから3年たって解体新書という本をつくっています。したがって、私の近くにあるここの山脇東洋さんがこの六角獄舎という、まあ言うたら刑務所ですね。そこで一番最初に解剖されたのが我が国の一番最初。したがって、私の診療所はこの日本近代医学のあけぼのの地、日本で初めて解剖された場所に一番近い診療所ということになるわけですね。これがまた一つの売りであるわけです。
今言いましたように、今日の話を聞いてもらって頭の中に残るのは恐らく二つか三つぐらいしか皆さん残らへんと思うのですが、その中で一つ知ってほしいのは、杉田玄白が一番最初に日本で解剖したんじゃないです。2番目ですわ。
そういう話はどういうこととつながるかといいますと、1754年言うたら江戸の真ん中ぐらいですけど、もう既にそのころ解剖するということは、西洋学的な医学の蘭学とかを含めて、そういう雰囲気がずっと京都であったわけです。それからしばらくたって、やっぱりそういう学問的なことがどんどんどんどん京都で盛んになってきました。南禅寺というのは恐らくご存じやと思いますね。京都の東山にありますお寺です。京都言うたら湯豆腐というのを皆さんご存じですかね。湯豆腐おいしいですよ。南禅寺の湯豆腐というのはわりと有名です。札幌には湯豆腐の名所というのは多分ないですよね。これはわりと京都的な料理で、非常においしくて温かい。湯豆腐で有名なのは、順正というのが南禅寺の門の入り口にあります。京都で観光に来られて南禅寺へ行ったら大抵湯豆腐がコースに入っていることが多いので、観光ルートでも順正というところは載っていることが多いと思います。そこに行かれたら思い出していただきたいのですけど、その順正という湯豆腐屋さんは単なる湯豆腐屋さんじゃなくて、ここは実は解剖がされてから何年かたってから、京都で医学の学問所といって順正書院という、そういう学問所があったところです。この順正書院という学問所の名前をとって順正というのが今料理屋さんになっているということで、三つ目の発見ね。南禅寺で湯豆腐を食べはったら、本当はここは学校やったんでということを。歴史的には皆さんシーボルトってご存じかもしれませんけど、どうもそういう人もここの学問所に寄って勉強されたようであります。
このように、京都というのはこういう医学のことも含めて非常に先進的なことがなされた場所であるわけなのです。そういう歴史的な背景も含めて、私が京大工学部大学院から医学部のほうへもう一遍入り直して勉強を始めたのは、これはお寺で何かするとすればやっぱり医学で人を助けることのほうが、まあ試験管を握っているよりかは性が合うかなということで、府立医大のほうに入り直したのです。その京都府立医大といいますのは、これもまた変わった歴史があります。実は我が国で西洋式の病院として初めて、1872年ですから明治5年に京都府立医大というのは設立されました。鴨川の横に現在府立医大がありまして、川を挟んで東側に京大の病院があるのですね。非常に接近しているのですけど、鴨川の流れの西側に京都府立医大病院があります。
京都府立医大といいますのは、これは1872年に療病院という名前で一番最初にできました。お寺が中心になって病院をつくっているのです。これはどういうことかといいますと、木屋町御池のところに今現在でも「療病院址」という石碑が建っているんですけど、お寺がお金を出して病院をつくったのです。そのころ二十何カ寺ぐらいがお金を出さはって、その出資で病院ができた。これが発祥元です。その発起人になりましたのが我が西山禅林寺派の本山である永観堂という禅林寺の管長さん、東山天華という人が言い出しっぺでした。非常に私自身もご縁があるんですよね。したがって、いまだに府立医大の入学式には、そのときに発起人となった我が本山の永観堂禅林寺から祝電が来るんですよ。大学の入学式でお寺から祝電が来るっておもしろいでしょう。これは京都ならではです。