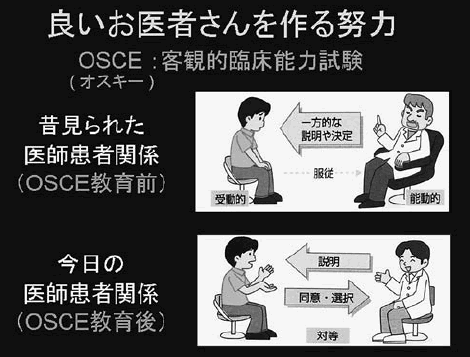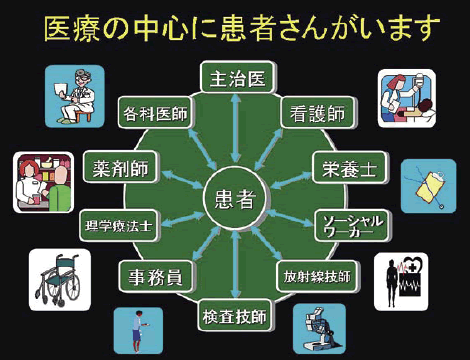| No47 |
あなたの理解が“良いお医者さん”を作ります
〜上手な健康管理と賢い病院のかかり方〜
(2/6)
良いお医者さんとはどのようなお医者さんでしょう。東大医学部の学生に聞いた良いお医者さんのイメージは「うまい、強い、偉い」だそうです。どこかの牛丼屋さんの標語をもじったのかもしれませんが、「うまい」はまだ許されると思います。医療の技術・患者さんを治す技術に優れている。これは医師として望まれる部分でもあります。「強い」は何でしょう。意志や身体が強いということかもしれない。健康で医療に当たるのも大事です。しかし「偉い」とは何事でしょう。結果として皆さんの尊敬の対象になる偉い先生は良いかもしれませんが、自分で偉いと思っている人間にろくなのはいません。高月清司さんという方が、「うまい、強い、偉い」は、患者さんとトラブルを起こす医師の典型像だと危惧しておられます。皆さんが描かれる良いお医者さんはこうではない。もちろん患者さんをきちんと治せるのは当然ですけれども、患者さんに優しい、説明がわかりやすい、あるいは心配を取り除いてくれるようなお医者さんが、多分患者さんから見た良いお医者さんだろうと思います。
実は、そういうお医者さんをつくろうと、私ども大学は努力をしています。ここに昔見られた医師・患者関係の絵がございます(図1)。大変偉そうな先生が、あなたの病気はこうで、この治療を受けなさいと言いますと、患者さんが、はいわかりましたと従う一方通行の関係です。今の医師・患者関係は、お医者さんが患者さんにわかる言葉できちんと説明をして、患者さんが理解し選択して同意するという双方向性の関係、つまり対等なわけです。今の医学部の学生にはこれを徹底指導します。その入り口で大事なのがオスキー(OSCE)、日本語で客観的臨床能力試験という仕組みです。このオスキーが日本に導入されたのは十数年前ですが、私ども旭川医科大学では道内では一番早く、全国的にも非常に早い時期に導入致しました。これとクリニカル・クラークシップという、患者さんを実際に診るときに役立つ仕組みを導入しましたので、うちの卒業生はどこでも大変評判の良いお医者さんが多いと言っていただけます。
今日の医師・患者関係というのは、この教育を受けたお医者さんとの関係です。例えば山田太郎さんという患者さんが来たと想定して学生に練習をしてもらいます。「山田太郎さん、お入りください」とお呼びして「山田太郎さんですね」と確認します。「本日担当させていただきます内科の長谷部と申します。よろしくお願いします」という挨拶から始まります。「どうぞおかけください」と座っていただいて、「今日はどういうことでいらっしゃいましたか」と自然に話を進められる医師をつくることを私どもはやっています。
これは学生に示すスライドですけれども(図2)、医療の中心に患者さんがいらっしゃる。私ども医師は単なるスタッフの一人にすぎない。看護師さんや薬剤師さん、技師さんや事務の方々と一緒の目線で、医療に当たらねばならない。常に患者さんが中心にいるのだということを徹底します。
インフォームド・コンセントという言葉をご存じかと思います。病気のことですとか、診断のために検査が必要です、その検査には危険があるかないか、どんな治療をしましょうか、他に方法は、副作用は、6カ月後にきちんと病気は治るのかというようなことを、患者さんがわかる言葉で説明いたします。
大事なのは、理解と選択です。患者さんが十分理解をして、ではその検査やその治療にしますと選択していただいて、物事が進むのが今の医学・医療の流れです。十分な説明をして十分な理解を得るためには、十分な時間が必要です。そうなりますと、良いお医者さんほど時間がなくなります。とても時間のかかることを今私どもは地道にやっております。
インフォームド・コンセントの徹底のお話です。例えば産婦人科で「妊娠おめでとうございます」という場面です。このおめでたいお話の後に、「ところでこれから赤ちゃんが生まれるまでに0.006%の確率で死にます」と伝えるのはいかがなものかと、千葉大学の生水先生が書かれています。「おめでとうございます」の後で、「死ぬかもしれません」はいかがなものかということです。日本のお産は非常に安全です。日本のお母さん方が周産期に亡くなる確率は、世界中でも極めて低い。妊産婦の死亡率は10万件当たりで6.3から5.7です。
とても安全ですので「お産の安全神話」が生まれます。お産は平気なもの、安全なものとなりますと、問題が起きることは無い、問題はゼロでなければ許されない。万一何か問題が起きた時には、あの医者が悪かったに違いないと成り得るわけです。それを避けるなら、「おめでとうございます」の後に「0.006%の確率で死ぬことも」と言わなければいけなくなるわけです。
産科医療の崩壊が言われます。桑江先生という産科の先生が書いておられるのですが、医療訴訟が増えて警察が入ったりするという象徴的な事件が、福島県立大野病院の産科で起きました。胎盤が難しい位置にあったお母さんの出血を止められず、不幸にして亡くなられました、すると警察が来て医師を逮捕した事件です。これには確かに驚きまして、その後産科を目指す医師や、分娩を扱う病院が少なくなるきっかけにもなった事件と言われます。長時間勤務と低賃金、モンスターペイシェントの増加などは、産科に限ったことではありません。私ども心臓を扱う教室の人間に言わせますと、産科の先生より心臓を診る我々のほうがよほど長時間働いている。昼も夜も土日もなく、心筋梗塞や心不全の患者さん、不整脈で心臓が止まってしまった患者さんを診ていますと言うと思います。
ハイリスク分娩が増えているそうです。母子手帳をもらって定期的にお医者さんにかかることが無く、生まれる寸前に病院に突然飛び込む。するとその前の様子がわかりませんので、中には大変危険な状態の人もいらっしゃいます。また心臓の病気などを持っているお母さんは、基幹病院など大きな病院の産科にどんどん集まってきます。すると、そこのお医者さんは大変忙しくなります。突然の患者さんの受け入れ要請があっても、手がいっぱいで受けられないと「たらい回し」という大変耳ざわりの悪い言葉の現象が起きます。
先週3月6日の北海道新聞に、札幌で痙攣して意識不明の重体の2歳の女の子が、11カ所の病院に拒否された。週末の金曜日の夜8時と書いてあります。なぜ受けられなかったのかが書かれていますが、専門外だからが五つの医療機関、処置できませんが二つの医療機関等々です。この大札幌で、専門外、処置ができないとは何事だ。皆さん、昼も夜も日曜も祝日も、専門診療、高度な治療がいつでも受けられる医療体制があるはずだ、あるべきだと思われると思います。私もそう思います。ところが、現実はそこまで整備されていないということです。昼も夜も日曜も祝日も、同じ病院で対応するのは同じ医師です。つまり、先ほどの2歳の女の子は、急性硬膜下血腫という脳外科の処置が必要な病気でした。例えば30人お医者さんがいる病院で、脳外科の先生が1人とします。その先生が昼も夜も日曜も祝日もずっと病院にいれば、いつでも脳外科の手術ができる病院です。しかし、金曜日の夜8時です。先生はおうちに帰ったかもしれない。そうなると、残り29人の先生は無力です。脳外科の手術はできないわけです。それは何事だとおっしゃるかもしれません。専門じゃなくても、命にかかわるのだから、ちゃんと診て対処しなさいよ、それがお医者さんでしょうと、おっしゃると思います。それではと言って引き受けたとします。患者さんが運ばれます。状態はどんどん悪くなります。やっぱり脳外科の手術が必要だった。どうしようと言っているうちに最悪のことが起きたら、何が起きるでしょうか。今お医者さんの中には「逮捕されるかもしれない症候群」が蔓延していると言われます。これが蔓延し始めますと、リスクの高いこと、危ないこと、命にかかわることは避けるお医者さんがどんどん増えてきます。これは大変です。安心・安全な医療の危機だと思います。