| NO.7 |
薬を正しく飲んでいますか?
(3−1)
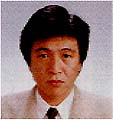
北大医学部附属病院 薬剤部 助教授 井関 健
| 高血圧・心臓疾患は放置すれば生命にも関わる恐ろしい病気ですが、早期に発見して適切な治療を受ければ健康な方と同じ様な生活を送ることも可能です。これらの病気はまず最初に食生活の改善とともに薬物療法がその治療の要になります。しかし、薬はただ飲んでいればよいと言うものではなく、その人の病状に合わせて決められたルールに従って服用することが大切です。 |
どうして「食事」に合わせて薬を服用しなければならないの
「私たちは、ごく当たり前のように食後に、食前にというように、食事との関連で薬を服用しています。しかしなぜそのようになっているのかと疑問に思ったことはないでしょうか。
「食前服用」と薬袋に書かれてあるけれども、うっかり飲み忘れてしまった。食事の後ではいけないのだろうかと考えたことはありませんか。
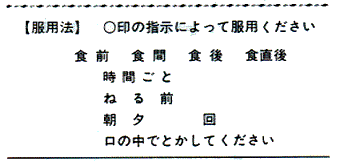
一般に、病院でもらう薬の「服用方法」のところに書かれてある指示をみると図1のようになります。「食後」という指示の他に「食前」「食間」「食直後」という指示があります。
この図から、これらの指示が食事を中心として何時間くらいに服用することを意味しているのかがわかります。この他に「寝る前」「8時間毎」という服薬指示もありますが、これらは時間がはっきりしているので迷うことは少ないと思われます。
このように服用時間は具体的に決められているのですが、「食後」と「食直後」の違いや「食間」の意味を間違えて覚えている人も少なくないようです。
服用時間が決まっている理由
結論から先に述べますと、服用時間は「患者側の状態」と「薬の性質」との兼ね合いで決められます。
「患者側の状態」とは、食事の前は胃の中はからっぽであり、食後には胃液分泌が盛んになっていることを前提としています。
すなわち、胃の運動状態や飲食物の量、胃の内容積、胃酸度や血液量、病気の状態などは食事との関係で変わってきますから、患者それぞれの食事との時間的経過関係を見れば、その患者が今どんな状態にあるか、あるいはいつどんな状態になるかが推測できます。
一方、「薬の性質」とはどのような薬理効果を持つのか、体のどの部位で作用するのか、消化管からの吸収性はどうか、水溶性か脂溶性か、胃腸内で化学変化を受けるのか、どのような製剤か(カプセル、錠剤、持続性等々)などを指します。
例を挙げると、血糖降下剤(経口糖尿病薬)は食事をして血糖値が高くなるときに薬の効果が発現するように計算されてつくられていますから、食事をせずに服用すると低血糖状態を生じてしまいます。
このような血糖降下薬の場合は「食前」よりも「食直後」の方が良いと言われていますが、その理由を図2に示しています。


