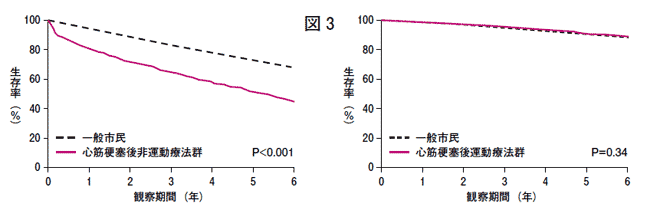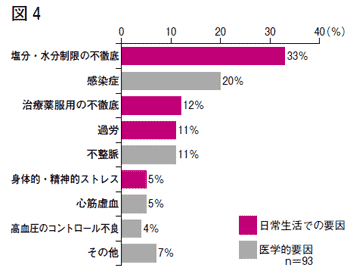| NO.7 |
�S�����n�r���e�[�V�����̖ړI�ƌ���
�i2�|�P�j
�k�C����w��w�@��w������ �z�a�ԓ��Ȋw�@���� �^���Y���A�㓡 ��S��
�͂��߂�
�@�S�؍[�ǂ�S�s�S�̂悤�ȐS���a���҂���̕a���������̒i�K�ł̎��ẤA�u���Áv�ɂ��邱�Ƃ��d�v�ł��B�}���S�؍[�ǂœ��@�����ꍇ�A1940�N�ケ��܂ł́A�U�`�W�T�Ԃ̓x�b�h��ň��Âɂ��邱�Ƃ����i�Ɏ���Ă��܂����B�������Ȃ���A�������É珰���l�X�ȕ��Q�������炷���Ƃ�����A�����̗����E�މ@�E�Љ�A�������߂���悤�ɂȂ�܂����B
�@1960�N��㔼���납��A�S���a���҂���ɑ��ĐϋɓI�ɉ^���Ö@���s����悤�ɂȂ�A���̌��ʂ����炩�ɂ����悤�ɂȂ�܂����B�ߔN�ł́A�u��I�ȐS�����n�r���e�[�V�����v�̍l�������m������A�^���Ö@�����łȂ����ҋ����J�E���Z�����O���ɍs���d�v�����F�������悤�ɂȂ�܂����B����́A�S�����n�r���e�[�V�����Ƃ͂ǂ��������̂�������������Ǝv���܂��B
�S�����n�r���e�[�V�����Ƃ�
�@�^���Ö@����̂Ƃ��āA���ҋ���E�����w������уJ�E���Z�����O�ɂ���I�ȃv���O�����ɂ���āA�g�̓I�E���_�I�f�R���f�B�V���j���O�̐����Ƒ����̎Љ�A��}�邱�Ƃƒ�`����Ă��܂��B
�@ �܂�A�S���a�ɂ���Ēቺ�����̂̋@�\�����߁A�������̏Ǐ���y������ƂƂ��ɁA���S�Ɋ����ł���͈͂�ݒ肵�A�}����s�������������M�������A�S���a�̈����ɂ����@�̗\�h�A�����̎��̌���A����ɂ͎��������������邱�Ƃ�ڎw�������Ãv���O�����ł��i�}�P�j�B���������āA���n�r���e�[�V�����Ƃ����ƁA�^�����邱�Ƃ��C���[�W���܂����A���ꂾ���ł͂���܂���B
�S�����n�r���e�[�V�����̑Ώێ���
�@����20�N�x�f�Õ�V����ɔ����A�{�M�ɂ�����u�S�匌�ǎ������n�r���e�[�V�������v�̑Ώێ����͕\�P�ɋ�����ʂ�ł��B�������S�����ł���S�؍[�ǂ⋷�S�ǁA�l�X�ȐS���a�ɑ����p�i�J�S�p�j��A�����S�s�S�A�匌�ǎ����ł���哮���𗣂���ѕǐ������d���ǂ��Ώێ����Ǝw�肳��Ă��܂��B�K�����Ԃ�150���ԂƂȂ��Ă��܂����A���ꂼ��S���オ��w�I�ɕK�v�ł���Ɣ��f�����ꍇ�ɂ͉������\�ł��B�܂��A�N��̐����͑S���Ȃ��A����҂ł��ϋɓI�ɍs���܂��B
�^���Ö@�̌���
�@�S�����n�r���e�[�V�����ɂ����āA�ł���̂ƂȂ�͉̂^���Ö@�ł��B�^���Ö@�͐S���a�̊��҂���ɑ��āA�l�X�Ȍ��ʂ����邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�傫��������ƁA�@�̂ɑ�����ʁA�A�C��������̎��ɑ�����ʁA�B�a�C�̈�����\�h������ʁA�ƂȂ�܂��i�}�Q�j�B
�i�P�j�̂ɑ������
�@�S���a���҂���͗l�X�Ȍ����ʼn^���\�͂�������x���ቺ���Ă��܂��B�S���a���̂��̖̂��ŁA�y���J��ŋ��̒ɂ݂⑧�ꂪ�o�����邱�Ƃ�����܂��B�܂��A���̋ؓ��ɖ�肪�����邱�Ƃ�����A���₷���������邱�Ƃ�����܂��B���ɁA�S���̎�p��W���I�Ȏ��Âɂ���āA���@���Ԃ������Ȃ����ꍇ�ɂ́A�ؓ��̈ޏk���N����A�S���͗ǂ��Ȃ����̂ɂ��ւ�炸�A�����オ�邾���ł����ꂪ�o�邱�Ƃ�����܂��B
�@�^���Ö@�͂��̂悤�ȉ^���\�͂̒ቺ�����P�������p������܂��B���̂��Ƃɂ́A���̋ؓ��̎���ʂ����P�������p���傫���ւ���Ă��܂����A�S���̋@�\�����߂���ʂ��ւ���Ă��܂��B�܂��A�S�g�̌��ǂ̋@�\�����߂���ʂ��m���Ă��܂��B���S�ǂɂ�鋹�̒ɂ݂�ǐ������d���ǂɂ�鑫�̒ɂ݂��o�ɂ����Ȃ邱�Ƃ�����܂��B
�@ ����ɁA�^���Ö@�͎����_�o�̃o�����X�����P�����p���d�v�ł��B�����̐S���a���҂���ɂ����āA�����_�o�����܂�A�������_�o����܂��Ă��܂����A���̂��Ƃ��S���a�̏d�Ǔx�����������邱�Ƃ��m���Ă��܂��B�^���Ö@���s�����Ƃɂ���āA�����_�o����߁A�������_�o�����߂邱�Ƃ��ł��܂��B��������Ɖ^���Ö@���p������ƁA�S�����▬���������Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂����A����͎����_�o�̃o�����X�����P�������Ƃɂ����̂ł��B
�i�Q�j�C��������̎��ɑ������
�@�S���a���҂���́A�l�X�ȏǏo������������������܂��B���̂悤�ȏŁA�Ⴆ�S���a�̎��Â���肭�������ꍇ�ł��A�u�ǂ̂��炢�����i�^���j���ėǂ��̂��H�v�u�ǏĔ�����̂ł͂Ȃ����H�v�Ƃ������s����������܂ܐ������Ă���ꍇ������܂��B���ʂƂ��āA�O�o���T���A����Œ���̊��������ʼn߂����Ă��܂��Ă��邱�Ƃ�����܂��B�Ђǂ��ꍇ�ɂ͗}����ԂɂȂ��Ă��܂��ꍇ������܂��B �����̎��ɂ́A�P�j�Ǐ�Ɋ֘A���������̎��A�Q�j�C�����Ɋ֘A���������̎��A����ɁA�R�j�Љ�I�Ȑ����̎�������A���������N�֘A�����̎��ƌĂ�ł��܂��B
�@�^���Ö@�͑̂ɑ�����ʂɂ���ďǏ���y�����邾���łȂ��A�C�����ɑ�����ʂ�����܂��B���ۂɉ^�����邱�Ƃɂ���āA��̓I�Ȋ����\�Ȕ͈͂��킩��A���M�����߂����Ƃ��ł��܂��B�܂��A�W�c�ʼn^�����s�����߁A���̊��҂����ڕW�Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B����ɁA�ƒ�������ɂ����鎩����E�ꕜ�A�Ȃǂ̎Љ�I�Ȑ����̎������コ���邱�Ƃɂ��Ȃ���܂��B
�@���̂悤�Ȍ��N�֘A�����̎��ɑ���^���Ö@�̌��ʂ͉Ȋw�I�ɏؖ�����Ă���A�^���Ö@�̏d�v�ȕ����ł��B����A���҂��g����������ƕa�C�A���ÁA�Ǘ����@�Ȃǂ��w�K���邱�Ƃɂ���āA���M�����߂����Ƃ��o���܂��B���������āA�^���Ö@�Ɋ��ҋ����J�E���Z�����O�������ꂽ��I�ȃv���O�����ɎQ�����邱�Ƃ��d�v�ł��B
�i�R�j�a�C�̈�����\�h�������
�@�����̐S���a���҂���ɂƂ��āA�a�C�̈�����\�h���邱�Ƃ����ɏd�v�ł��B���S�ǂ�S�؍[�ǂȂǂ̋������S�����ɑ��āA�^���Ö@�͕a�C�̈�����\�h������ʂ������̌����ŏؖ�����Ă���܂��B
�@�}�R�͕č��̃~�l�\�^�B�ōs��ꂽ�������ʂł��B�S�؍[�ǔ��NJ��҂�����^���Ö@�ɎQ������Q�Ɖ^���Ö@�ɎQ�����Ȃ��Q�ɕ����Čo�߂��ώ@���A���̒n��̑��̈�ʏZ���Ɣ�r�����Ƃ���A�^���Ö@�ɎQ�����Ȃ��Q�ł͖����ɐ���������l�ł������A�^���Ö@�ɎQ�������Q�ł͈�ʏZ���ƑS���ς��Ȃ��Ƃ��������ׂ����ʂł����B
�@ ���̂悤�ɉ^���Ö@�͋������S�����ɑ���ɂ߂ċ����\�h���ʂ�����܂��B
�@����ɁA�������S�������҂���͓����d���̊댯���q�ł��鍂�����E���A�a�E�����ُ�ǂ�\�h�A�R���g���[������K�v������܂��B�����̊댯���q�ɑ��āA�^���Ö@���d�v�ł��邱�Ƃ͂悭�m���Ă��܂��B�܂��A�S�s�S���҂���ɑ��Ă��^���Ö@�͕a�C�̈�����\�h������ʂ����邱�Ƃ��킩���Ă��܂����B
�@���̂悤�ɉ^���Ö@�ɂ��a�C�̈�����\�h������ʂ͒P�Ƃōs�����A�H���w���A�����w���A����w�����ꏏ�ɍs�����Ƃ��d�v�ł��B�Ⴆ�A�����S�s�S���҂���̏�Ԃ������Ȃ��ē��@���錴���͐}�S�Ɏ�����Ă���l�ɁA�a�C�̈������̂��̂��A�ނ���H���E�����E����Ɋւ��邱�Ƃ��������Ƃ��m���Ă��܂��B�����ł���I�ȃv���O�����̏d�v�������炩�ł��B