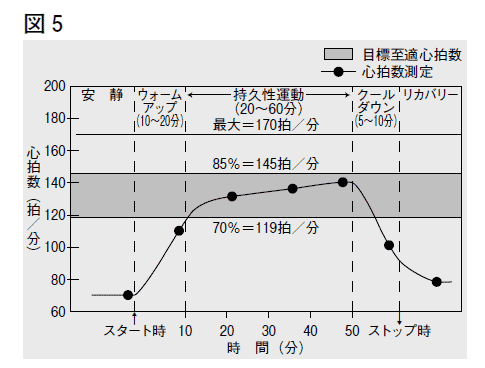| NO.7 |
心臓リハビリテーションの目的と効果
(2−2)
北海道大学大学院医学研究科 循環病態内科学 絹川 真太郎氏、後藤 大祐氏
運動療法の流れと運動処方
運動療法で用いられる運動の種類は大きく分けて、「有酸素運動」と「レジスタンストレーニング」があります。大事な点は、運動療法が効果的である前に安全でなければならず、運動中の心電図や血圧のモニタリングが容易で、運動強度を調節しやすい有酸素運動から始めることが多いようです。一般的に、自転車エルゴメーターやトレッドミルを用いた有酸素運動が行われます。
運動強度は患者さんの運動能力にあわせて決定されなければなりません。事前に運動負荷試験が可能であれば、運動能力を正確に評価し、運動処方を行うことが望ましいと考えられ、嫌気性代謝閾値(最大運動能力の大よそ40〜60%程度で、心疾患に悪影響がない)レベルの強度での運動が推奨されています。
一方、運動負荷試験が出来ない場合には心拍数や自覚症状を元に処方する場合があります。トレーニングの構成は図5の様に、約10分のウォームアップ、20〜60分の持久性運動、5〜10分のクールダウンを行います。運動の頻度は週に3〜5回行うことが推奨されています。また、デコンディショニングを有する者や筋力水準が低い高齢者ならびに女性では運動プログラムにレジスタンストレーニングを取り入れることがあります。
運動時の注意点
体力を効果的に増加させることが重要ですが、安全であることが最も重要です。運動療法時の注意点は以下の通りです。運動療法は注意点を守りながら、処方された運動強度や回数をきちんと守り、長期間継続することが重要です。調子が良いからといって、勝手に運動強度をあげたり、回数を増やしたりすることは、心疾患患者さんにとっては危険なことがあります。
- からだの調子が良い時のみ行う(風邪症状後には、症状がなくなって2日以上経過してから再開)
- 食後すぐに運動を行わず、最低でも2時間は待つ
- 適宜水分補給を行うこと
- 天候に合わせて運動を行うこと(特に暑い気候での運動に注意、常にいつもと同じ程度の自覚的運動強度であるかを意識すること)
- 坂道ではスピードを落とすこと
- 適切な服装と靴で行うこと(ゴム素材や通気性の悪い素材で作られた服装は使用してはならない、直射日光が当たるような場合は、明るめの色の服を着て帽子をかぶること、ウォーキング用にデザインされた靴をはくこと)
- 個人の運動制限因子を理解すること
- 症状の出現に注意すること(運動中に胸部・腕・首・あごの不快感、運動後の脱力、運動中の不快感を伴う息切れ、骨関節に不快感)
- 過度の運動のサインに注意すること(決められたトレーニングセッションを完遂することができない、活動中に会話することができない、運動後にふらつき感や吐き気がある、慢性的に疲労感がある、睡眠不足、関節の痛み)
- ゆっくりと開始し、徐々に強度をあげること
おわりに
今回は心臓リハビリテーションの概要について説明いたしました。心疾患患者さんでもきちんと運動能力を評価し、適度な運動処方に基づいた運動は心疾患の治療として有用であるばかりでなく、体も気持ちも元気になってきます。心臓リハビリテーションは患者教室・生活指導・服薬指導・カウンセリングといった包括的なプログラムによって、「元気に長生きする」ことを目指した治療法です。