| NO.1 |
心臓病の機器診断ことはじめ
(3−1)
北海道女子大学教授 心臓血管センター・ 北海道大野病院顧問 尾山洋太郎
動物の心臓がどれだけ高く血液を送り届けるか胸苦しさや動悸を感じたりして、あるいは自覚症状が無いまでも健康診断の目的で病院を訪れると、先ず胸部のX線撮影や心電図の記録が指示される、また診察に際しては聴打診に加えて血圧が測定される、といったことは、誰でも一度ならず経験することでしょう。
このようなごく日常的で一般的な検査の結果、心臓・血管の病気が疑われる場合は、超音波検査、核医学的検査、カテーテル検査、電気生理学的検査などが行われることになりますが、これらのより専門的な内容と現況は、このシリーズを通じて各担当者により詳細に解説される予定です。
ここでは、すでに1世紀前後を経て現在なお、循環器疾患の診断や治療に欠くことの出来ない血圧計、X線や心電図、心臓カテーテル法の発明・発見のいきさつのいくつかについて述べ、このシリーズの前書きとします。
リヴァロッヂの血圧計
血圧測定の最初の試みは、英国の牧師のヘイルズによる1733年の実験とされています。彼は、馬の頸動脈に青銅の管を挿入し、これと垂直のガラス管を、当時屈曲管としてよく用いられた鵞鳥(がちょう)の気管で接続し、血液がガラス管の中を2.7メートルまでに上昇するのを観察しました。
ヘイルズは元来、液体の流れに関心があり、ことに樹木がどのようにして樹液を梢まで送るのかを研究するなかで、「動物の心臓がどれだけ高く血液を送り届けるか」を測定しようと思いたったのです(図1)。
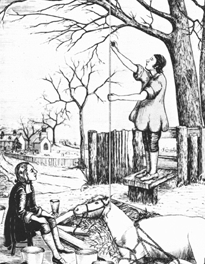 |
| 図1 1733年のヘイルズの実験 (自宅と教会、実験の様子が描かれている) MEDICINE(1978)より |
このような直接的な血圧測定は、人間に対しては容易には適応しがたく実用的ではありませんでしたが、1896年(明治29年)、イタリアのリヴァロッヂによって、より簡便・安全で間接的な血圧測定法が発明されました。
この測定装置は今日広く用いられる血圧計の原型であり、ゴム嚢を布に収めた圧迫帯(マンシェット、カフ)とこれへの送気・加圧のためのゴム球、マンシェット内圧を測定するための圧力計(図2)、並びにこれらを連結するためのゴム管と弁により構成されています。
当初は撓骨(とうこつ)動脈を同時に触診し、マンシェット内圧を加圧・減圧する際の脈拍の状態から最高・最低血圧を求めましたが、1905年ロシアのコロトコフが聴診による血圧測定理論を示して以来現在まで、このリヴァロッヂ・コロトコフ法が、臨床的な血圧測定の標準的な方法となります。
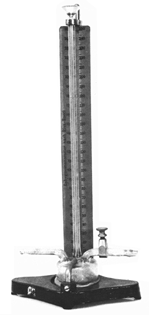 |
| 図2 リヴァロッヂの水銀圧力計 MEDICINE(1978)より |


