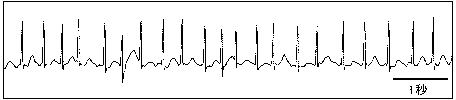| NO.4 |
不整脈
(2−2)
心房細動/高齢者の合併症に注意
自己診断は禁物、変だと感じたら病院へ心臓の4つの部屋のうちの上の2つ(右心房、左心房:図1参照)をまとめて心房と呼びますが、心房細動とは、この心房が、洞結節の命令を全く無視して律動性を失ってバラバラに興奮するという不整脈です。心房の興奮が不整なので、これに引き続いておこる心室の興奮も不整になります。単に不整なだけではなく、一般に脈拍数が1分間100回近く、あるいはこれ以上という速い脈になることが多いようです。これが起こったときの自覚症状は「突然動悸がする」「脈がバラバラである」といったものです。図2に実際の心房細動の心電図を示しました。
図2 心房細動の心電図
心室の興奮(針のように尖った波)は1分間150回以上である、しかも間隔が不規則である心房細動は比較的若い人にもおこりますが、大体「夕べ酒を飲み過ぎた」「下痢で水分が抜けている」「寝不足」「試験前で緊張していた」など、身体の悪条件に伴って一時的に起こるものが多く、これらの条件を是正することにより直ります。
しかし、概ね65歳を過ぎた方の心房細動は少し異なり、動脈硬化による心房の心筋の障害が背景因子として加わってきます。動脈硬化の基盤として高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などが存在していることも少なくありません。すなわち、狭心症などの虚血性心疾患と同様、生活習慣病の一つの現れとみることができます。なお、特定の疾患に基づいた心房細動としては、心臓弁膜症に伴ったものや、甲状腺機能亢進症に伴ったものなどがあげられます。
心房細動は、それ自体は生命が危険なほどの重い不整脈ではありません。1回心房細動が起こったけれど、その後しばらく起こらないといった場合は特に気にする必要はないと思います。しかしながら、回数が多い場合、一回の持続時間が長い場合、特に、通常の脈にきわめて戻りにくく永続的になった心房細動では、以下のような合併症が出現することがあります。(1)心不全:若い人などで、心臓の機能が正常の場合は問題ないですが、比較的高齢の方で、とくに虚血性心疾患などが背景にある場合は、1分間100回以上と速く、しかも律動的でない脈が長時間続くと、心臓は日常生活に必要なだけの血液を供給することができなくなり、心不全という状態になります。
(2)血栓症:心房細動では、単に心房の伸び縮みが律動的でないだけではなく、伸び縮みそのものが不十分であるため、心房の中に、血液の流れが非常に乏しい、つまり「よどむ」部分ができやすくなります。よどんだ血液は必然的に固まりやすくなり、心房の中に血栓をつくります。特に左心房にできた血栓は、その場所に止まっているうちはよいですが、何かの拍子に剥がれて血の中に流れ出すと、動脈に乗って、脳をはじめとする各種臓器に到達し、血管に詰まることがあります。これを「塞栓症」とよび、脳の場合は「脳塞栓」となり、脳梗塞を発症してしまうことになります。これは心房細動の最も困った合併症です。
そこで心房細動の対策としては(a)なるべく正常の脈にもどすこと(b)血栓症の予防をすること、の2つが重要となります。(a)のために用いる薬はいわゆる「抗不整脈薬」とよばれるものです。おそらく半数の患者さんの心房細動はこの薬で正常の脈に戻るでしょう。しかし残りの半数では、抗不整脈薬を2種類、3種類と重ねてもなかなか戻らず、患者さんはもとより、医師も治療に苦慮することになります。このような場合、治療の主眼を「正常の脈にもどす」ことから、「たとえ心房細動であっても脈拍数を正常(1分間60回前後、すくなくとも100回以下)にするという治療へ切り替えざるを得ません。そのための薬剤もいくつかあります。
特に、心房細動がもう永続的になってしまって、正常の脈に戻ることはないと判断された場合は、脈拍数を正常範囲にすることだけが対策となりますが、これは医師の判断によります。なお、ごく限られた施設で心房細動に対する手術やカテーテル治療も行われていますが、まだ一般的とは言えません。
(b)血栓症を予防する薬にはやはりいくつかの種類がありますが、基本となる薬は「ワーファリン」でしょう。この薬は、「これを内服すると納豆が食べられない(理由は、これがビタミンKの止血効果を抑制して作用する薬なのに、納豆はビタミンKを大量に含んでいるので相殺してしまうからです)」ということで御存知の方も多いでしょうが、少しでも足りないと無効であり、一方少しでも多すぎると出血傾向が出るという、調整の難しい薬です。外来受診時にこまめに血液検査をして内服量を決める必要がありますが、この点は医師は十分心得ていると思います。
<おわりに>
今回のポイントをまとめてみます。
(1)不整脈を思わせる自覚症状の代表的なものは「ドキドキ」「ドクン」「脈が抜ける」といったものである。
(2)不整脈の90パーセントは放置してよい。しかし一部に治療を要するものがある。
(3)不整脈の診断は心電図による。通常の心電図で不整脈がとらえられない場合、24時間心電図(Holter心電図)が記録される。
(4)心房細動は比較的頻度の高い不整脈で、若い人などで一時的に起こるものはあまり問題ないが、高齢者などで、反復して起こるもの、持続の長いものでは、心不全や血栓症の合併が問題となることがある。
不整脈が治療を要するものか、そうでないかという判断は御自分でするべきではなく、気になる症状のある方は遠慮せず病院を受診されることをおすすめします。