| �@No.39 |
��g�̐����Ɠ����d��
�i�P�^�Q�j
 |
| �X�|�[�c�h�N�^�[�@�@���c�@�F�ꂳ�� |
| �����w����w���U�w�K�V�X�e���w�����N�v�����j���O�w�ȋ������z��a�w�A�X�|�[�c��w�A�\�h��w�A���N�Ȋw�B�����ȑ�w���ƁB�k�C����w��w�@��w�����ȏz�a�ԓ��Ȋw����B��w���m�B�k�C����w��w�@��w�����ȏz�a�ԓ��Ȋw������u�t�B���{�̈狦��F��X�|�[�c�h�N�^�[�B���{��t��F�茒�N�X�|�[�c�h�N�^�[�� |
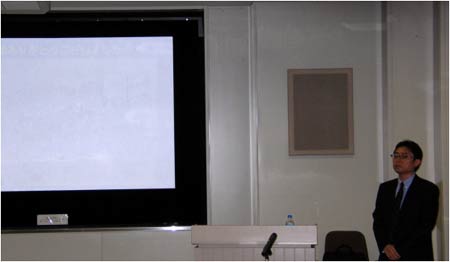
�@���͌��X�z����Ȉ�Œ��N�S��������f�Ă��܂������A�S�؍[�ǂɂ�鎀�S���͂���10�N�A�����ł��B���Õ��@�͔��B���Ă���̂ł����A���S���͕ς��܂���B�Ȃ��ł��傤���B�a�@�ɒ����O�ɖS���Ȃ��Ă��܂��l�̐����S���ς��Ȃ�����ł��B�����Ƀ��X�����Ȃ�����{�I�ȉ����ɂȂ�܂��A���̂��߂ɂ́A�\�h��w�̌��n���炻���Ȃ�Ȃ��悤�ɂ��邵������܂���B
�@�ŐV�̃j���[�X�ɂ��A��N�A���{�Ō��N�f�f���A�ǂ��ɂ��ُ킪�Ȃ������l��12.3���������Ȃ����������ł��B�ُ�Ƃ��đ����̂͊̋@�\�ُ�ł��B����ɂ͓�ʂ肠��A���|GTP�͂���������ł��オ��̂ŁA�債�����Ƃł͂���܂��A����GPT�������Ȃ鎉�b�̂ł��B�R���X�e���[���������̂��ڗ����܂��B�T���ɂȂ�Ǝ��b�̔䗦�������H�ו��łȂ��Ɩ������Ȃ��悤�ɂȂ�A���b�̐ێ�ʂ������A�얞�ɂȂ肪���ł��B�ߋ��̍ł��������ɂ͌��N�f�f����҂�30���������悤�ł����A���݂ł͌��f���ʁu�ُ�Ȃ��v�̐l���}���Ɍ����Ă����Ƃ������Ƃł��B�ɂ�������炸�A���ώ����͐��E1�ł��B�������Ȃ���A���{�ł͐Q����̊��Ԃ�2�A3�N����̂ɑ��A���{�Ɏ����������A�C�X�����h��k���̈ꕔ�ł́A���ώ����ƌ��N�����̍������܂肠��܂���B�܂�A�Q����������i���N�����j�Ƃ���A���{�͐��E1�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B
�@�����ŁA���傤�͉^���s���A���^�{���b�N�nj�Q�̍l�����A�����d���̋N������A���ÁA�\�h�A����Ƌi���Ƃ̊֘A�ɂ��Ă��b���܂��B���{�̈�Ô�͋}���ɑ����Ă��āA��N�͂Ƃ��Ƃ�30���~���z���܂����B����1/3���߂�̂̓��^�{���b�N�nj�Q�Ȃǂ�w�i�ɋN�����������d���ɋN������z��n�����ł��B
�@���^�{���b�N�nj�Q�̐f�f�́A���ɃV���v���ł��B�܂��A�������b�̒~�ς��ʐςɂ���100����cm���邩�ǂ����ł��B�������������ɂ���ƁA�j���Ȃ���85cm�ȏ�A������90cm�ɂȂ��Ă��܂����A�����̊�͌���������Ă��܂��B�얞�^�C�v�Ƃ��Ă̓����S�^�A�܂肨�����o�������Ă���얞�ł��B����ɉ����A(1)�����ُ�(2)�������l(3)��������3���ڂ̓��A2�ȏ�ɊY�����邩�ǂ����ł��B(1)�͒������b��150mg/dL�ȏ�|����͌��\����������܂��|�A�P�ʂƂ�����HDL�R���X�e���[����40mg/dL�ȉ��̂����ꂩ�A���邢�͑o���ɊY�����邩�ۂ��ł��B(2)�̌�����͍ŋߌ������Ȃ���130�^85mmHg�ȏ�B(3)�͋��̌����l��110�r�^dL�ȏ�Ƃ��Ȃ茵�����Ȃ��Ă���A�����N�҂̂��悻3�A4�l��1�l�͊Y������ł��傤�B
�@�����d���������̕�̂ɂȂ��Ă���̂����^�{���b�N�nj�Q�ł��B�ŋ߂ɂȂ��Ă��̕a�����蒅���Ă��܂������A�̂���A������ŁA�����������āA�������b�l�������A���A�a�ł͂Ȃ��������l�Ɉُ킪����l���A���ɍ����ɁA�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ��N�������Ƃ��킩���Ă��܂����B�����A���̂悤�Ȏ����́A���܂��ܑ����Ă���̂��낤�Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪�A���́A��̋��ʂ̌��������邽�߂����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��ŋ߂ɂȂ��Ă킩��A���̂悤�ȕa���ɂȂ�܂����B�Ȃ����킩��Ȃ����A�얞�������āA�����̓�A�O�������ƁA������Ă���l�������{���]�[�ǂȂǂ��N�����Ă��܂��̂Ŏ��̎l�d�t�A�Ƃ��ɂ̓V���h���[��X�ƌĂ�Ă��܂����B�����������킩���Ă��ăC���V��������R���nj�Q���邢�͓������b�nj�Q�ƌĂꂽ����������A���̓��^�{���b�N�nj�Q�ɒ蒅���܂����B
�@���{�̓����l�����̃f�[�^�����Ă��A�S���ǎ������Ǘ��́A�얞�A���������b�A�������A�������̎l�̓��A����Ȃ��l���P�Ƃ���ƁA������5�{�A��Ŗ�10�{�A�O�ȏ�ł���30�{�ɂȂ�܂��B���̂悤�ȃ��X�N�̏d�ςɔ����S���ǎ����͍ŋ߂ǂ�ǂ��Ă���A���Ƃ����Ȃ��ƈ�Ô�͗}�����Ȃ��Ƃ������ƂŁA���J�Ȃ̎��g�݂��ϋɓI�ł��B
�@�����͔牺���b�ł������o�Ă��邱�Ƃ�����A���ꂾ���ł͂킩��܂��A�j���͂������o�Ă���ΊԈႢ�Ȃ��������b�ł��B���b�͂����̂ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��A�̂͗]���ɐۂ����J�����[�����b�Ƃ��Ē��~���A�H�ׂ��Ȃ����ɂ�������G�l���M�[���������Đ������炦���̂ł����A���͒��܂������̂��g���@�����܂���B����ł́A������������Ă���̂��Ƃ����ƁA�����ł͂Ȃ��A���̒~�ς��ꂽ���b����L�Q�ȕ��������傳���Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂����B
�@���b�g�D���c���ł���ƁA���A�a���N���������A�������グ�镨���ȂǗL�Q�ȕ������S�g�ɂ�T����A����̂悤�Ȃ��Ƃ��N���邱�Ƃ��ŋ߂̌����ł킩���Ă��܂����B�����Ȃ��}���Ɍ������i��ł��܂��B����玉�b�g�D�R���̐������������̑��̂��A�f�B�|�T�C�g�J�C���ł��B�A�f�B�|�T�C�g�J�C���̈ꕔ����ӂɈ��e�����A�����d�����������A������Z�����邱�ƂɂȂ�̂ł��B
�@�����������������̂��H����͐����K���ł��B������Ɣ��A��������b���炢�낢��Ȃ��̂��o�Ă��ē��A�a�C���ɂȂ�A�������オ��A�������ɂȂ�A�������ǂɂȂ�A���A�a���������t�ǂœ��͂Ɏ���B�Ԗ��ǂŎ����A�r�̌��ǂ��l�܂�A�]�[�ǁA�S�؍[�ǂɂȂ铙�X�A�܂��Ƀh�~�m�|���ł��B
�@�j���͑̎��b�v�Ōv��K�v�͂���܂���B�������o����ԈႢ�Ȃ��������b�^�̔얞�ł��B�����̔얞�͓�ʂ肠��A�牺���b�^�̐l�͌��N��Ԃɂ��܂��肪����܂���B�������A�ߑ̏d���̂������ŕG������������A�������������肷�邱�Ƃ�����̂ŁA���������Ӗ��ł͂�����ɂ��Ă��K���̏d�������ł��傤�B
�@�얞�̍����ǂƂ��ẮA���ɓ��{�l�͓��A�a�ɂȂ�₷���l��Ȃ̂ŁA���Ȃ荂�������œ��A�a�ɂȂ�܂��B����ƍ������A�������ǁA�A�_�����R�����Ȃ�܂��B�]�[�ǁA�S�؍[�ǁA���������ċz�A�t���A�_�A���b�̓��X�ł��B����̈ꕔ�͔얞�Ɋ֘A���������K���a�ł��B��\�I�Ȃ̂͑咰����A�x����A������ŁA�^���K����얞�x�Ɉˑ����Ă��܂��B���̑��̍����ǂƂ��Ă͐����s���A�s���Ȃǂ��������܂��B���v�w�I�ɁA�얞�̐l�͌�ʎ��̂��L�ӂɑ����Ȃ��Ă��܂��B
�@���{�����łȂ��A�����J�A���[���b�p���X�ł��A�S�ʓI�ɉ^���s���ɂȂ��Ă��܂��B�^�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�̗͂������Ă���Ƃ������Ƃł��B�K�i�ƃG�X�J���[�^�[��ڂɂ�����ǂ����I�Ԃ��B������ƊK�i���g�����瑧����A�C�������畨�ɂ��܂��Ċy�����Ă���Ƃ������Ƃ͂���܂��B������15��������̂ł���ΎԂ�o�X�𗘗p����B15���������ꓹ�ł��B�d�Ԃ�o�X�ł͋�Ȃ�{���Ă��܂����A�x���͉Ƃʼn������Ȃ��ŃS���S�����Ă���B���ݓI�ɑ̗͂������Ă���؋��ł��B
�@�^�����Ȃ��͎̂��Ԃ��Ȃ�����A�d����Ǝ��Ŕ��Ă��邩��A�ȂǁA���R�͗���ňႤ���A���܂��܂ł��傤�B�ł��A�l�K�e�B�u�Ȏv�l�͂悭����܂���B�{�݂��Ȃ�����ł��Ȃ��A�Ȃ�Č����Ă�����ꐶ�ł��܂���B�����K���̒��ɉ^����������Ȃ��ƁA1��300kcal�̉^���͂ł��܂���B�Ƃł̎��ԁA�ʋE�ʊw���Ԃ𗘗p���Ȃ��ƁA�܂Ƃ܂����^���͂ƂĂ��ł��܂���B
�@��g�̐l�������^���s���ɂȂ�A�a�C�ɂȂ�₷���̂ł��B�����Ă����l�����Ȃ���A�����ʼn����H�v��������B�V�������̂ɒ��킷�邱�Ƃ��̗v�ł��B�{�݂ɒʂ��A�s���A��̕��s���^���ɂȂ�܂��B�|�W�e�B�u�ɍl���Ď�g�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��Ȃ��ƁA�m�炸�m�炸�̓��ɉ^���ʂ������A�̗͂������܂��B�̗͂�������ƁA�����Ɖ^���s���ɂȂ��Ă��܂��܂��B
�@���X�͎����������āA���߂ĐH�ו��ɂ�������̂ł��B�G�l���M�[���g���Ċl�����Ƃ�|�o�����X���Ƃ�Ă��܂����B�Ƃ��낪�A�������i�ނƁA�����Ȃ��Ă������܂ōs����悤�ɂȂ�A�����ōޗ����W�߂Ē������Ȃ��Ă��A�������������A���J�����[�ȕ�����u�ɂ��Ď�ɓ���悤�ɂȂ�܂����B����߂܂���w�͂����Ȃ��Ă��A������Ƃ����̂��H�ׂ��܂��B�ҏb���傫�ȓ�����|���̂͑�ςȂ��ƂŁA���x����Ɏ��s���āA����Ɗl��B�����ȃG�l���M�[���g���āA����ł�3���ɂP�炢�����H�ׂ��܂���B�����l�Ԃ͖����H�ׂ���̂ł��B���Ȃ������s�v�c�ł��B
�@�ق�̈��ł����A���X�x�K�X�̊X���̕������͐^�����K�i�ŁA�����̓G�X�J���[�^�[�ł��B�w�ǂ̐l���G�X�J���[�^�[���g���܂��B��`�Ȃǂɂ��铮�������ɏ���ė����~�܂��Ă���l�B��̂��G�l���M�[�������̂ł��傤���B���ǂ͔얞�ɂȂ�A�������ꂵ�ނ��ƂɂȂ�܂��B
�@�Ⴂ���͑̈�̎��Ƃ���������A�X�|�[�c�̃N���u���������ł����̂ł����A�d���ɏA�����肷��ƁA�܂��^�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�Ƃ��낪�A�^�����ł��Ȃ��Ă��ȑO�Ɠ������炢�H�ׂ܂��B�H���ʂ͌��炵�ɂ������̂Ȃ̂ł��B�^�����Ȃ��Ȃ��Ă��ԈႢ�Ȃ��H�ׂ܂��B���R�G�l���M�[�͗]��܂��B
�@���̓��{�l�́A3�A4�l��1�l�͔얞�ł��B�ϋɓI�ȁA�O�����Ȑ������K�v�ł��B�l�Ԃ͓����Ȃ��Ƃ��߂ɂȂ�܂��B�u���v���A�̂ɂ�ꂠ��v�ɕ���āu��ꓮ���A�̂ɂ�ꂠ��v�Ƃ������l�����܂����A�����Ȃ��Ɛl�ԓI�ȋ@�\���p�₵�A�����d���ɂȂ�l�ԂƂ��Ă̋@�\���������ƂɂȂ�܂��B
�@���{�l�̎O�厀���̕M���͑S�N���ʂ��Ă���ł��B60���߂����3�l��1�l�ŁA�������������قǁA����̊댯�x��������܂��B����ɐS�����A�]���Ǐ�Q�A�x���Ƒ����܂��B�j���ł͔x�������̂ł����A�i������80�����������オ����ɂȂ��Ă��邩��ł��傤�B�ŋ߂̋i������50�����܂����̂ŁA�x����͂����ꌸ��ł��傤�B
�@�咰����͑����A�݂���͌����Ă��܂��B�݂���͉����ێ�Ɗ֘A������A�①�ɂ��Ȃ����������ʂ���������ɂ͍��Z�x�̉���ۂ��Ă������߈݂���ɂ�鎀�S���͋ɂ߂č��l�ł������A�①�ɂƔ��������y���A�����Ă��܂����B�N�������Ə����̂���͖��炩�Ɍ����Ă���̂ł����A����A�얞�������Ă��邱�Ƃő咰����Ɠ��������Ă��܂��B������̜늳��30�l��1�l�ł��B
�@�Q������̐l���x���ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ŏ����ɂȂ�P�[�X�����X����܂��B�Q������̗��R�͔]���Ǐ�Q�ł���A���e���傤�ǂł���ŁA���̈Ӗ��ł͍���҂̔x���͐����K���a�ɋ߂��Ƃ����܂��B
�@�����̂��Ȃ�ȕ������߂�z�펾���ł́A�S���̓����d������ł���Ί������d���ɂ�鋕�����S�����A�]�̓����d������ł���A�]�[�ǁA�]�o���A�l�܂��Ē����n����Έ�ߐ��̋�������ł��B���ɂȂ��Ă���͓̂����d���ŁA���ǂ����܂��ܐS���ł�������A���ł������肵�Ă��邾���ł��B��������̐l�����܂��B�����z����Ȉ�ɂȂ������ɂ́A�S�؍[�ǂ̐l�͔]�[�ǂɂȂ�Ȃ��Ƃ����Ă��܂����B���̂��炢�������Ă���l�����Ȃ��āA�Ǘ�����ꂽ�قǂł��B���͓��R�̂悤�ɗ�������܂��B
�@�}���ɉh�{��Ԃ��悭�Ȃ�A�R���X�e���[���̍����l�������Ă��܂��B20�A30�N�O�̋��ȏ��ł́A���A�a�͓��{�l�ł͋H�ȕa�C�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����A���͕��ʂɂ���a�C�ł��B
�@�����d���͂ǂ��N����̂ł��傤���B�e���r���̉e���ŁA����������d���Ȃ��Ē����ׂ��Ȃ�A���炳�猌�t�łȂ��Ƌl�܂��Ă��܂��Ƃ����C���[�W���������̕��������̂ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͂��܂�Ȃ��Ƃ������Ƃ��ŋ߂킩���Ă��܂����B���ՂȂ��ׂ��Ȃ�̂ł͂Ȃ��A���鏊�ɃR���X�e���[���Ȃǂ���̂ɂ����v���[�N�Ƃ��������d���̕a�����ł��A����オ���Ă��܂��B�����͔��Ɏア�g�D�ŁA�₷���̂ł��B��ƌ��ǂ̒��Ɍ��̉���`�����ċl�܂��Ă��܂��A�S�؍[�ǂ�]�[�ǂ��N�����܂��B�����ɒ��ڂ��ĕa�C��\�h���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�v���[�N���ł��Ă��܂��A�܂蓮������d�����N���Ă��܂��A���炳����ǂ�ǂ���W�Ȃ����A�Ӗ�������܂���B
�@���炳�猌�t�������Ƃ������R�ɁA�ǂ�ǂ낾�Ɩэ��ǂɋl�܂��ĕa�C�ɂȂ邩�炾�Ƃ����܂����A�э��ǂ͓����Ƒg�D���Ⴄ���߂ɓ����d���͂���܂���B����Ȃ���̖����ȂǁiDIC�j�������A�э��ǂ��l�܂�a�C�͂���܂���B���炳�猌�t���������ǂ̍d���̗\�h�ł��B�R���X�e���[���𑝂₳�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�������͌��Ǖǂɏ������₷���Ȃ�܂����A���A�a�����ǂ���Q���܂��B���̌��ɂȂ�̂��얞�ł��B�i���͌��ǂ̓����ɏ��Q���N�������A���ǂ��z�������܂��B�R���X�e���[���������邾���ł��A�։����邾���ł��S�؍[�ǂ͋N���ɂ����Ȃ�܂��B���Ǖǂ����ꂢ�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
|
�@ 
|
