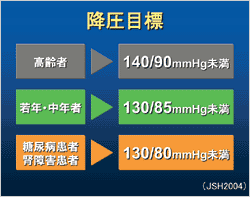 血圧をどの程度まで下げるか。日本高血圧学会のガイドラインによれば、高齢者は140/90未満、若年・中年者はそれより少し下げて130/85未満、糖尿病患者や腎障害がある人はもっと下げて130/80未満にコントロールします。他にリスクがある人は、その分余計下げます。それほど血圧は心臓血管病にとってのリスクだということです。高齢者で140/90未満にコントロールすることはなかなか大変です。150くらい当たり前じゃないかと思っている人がまだ非常に多いと思いますが、目標には高齢者であってもこれ未満にしなさい、といっております。
血圧をどの程度まで下げるか。日本高血圧学会のガイドラインによれば、高齢者は140/90未満、若年・中年者はそれより少し下げて130/85未満、糖尿病患者や腎障害がある人はもっと下げて130/80未満にコントロールします。他にリスクがある人は、その分余計下げます。それほど血圧は心臓血管病にとってのリスクだということです。高齢者で140/90未満にコントロールすることはなかなか大変です。150くらい当たり前じゃないかと思っている人がまだ非常に多いと思いますが、目標には高齢者であってもこれ未満にしなさい、といっております。
NIPPON DATAと呼ばれる循環器病基礎調査、栄養調査の成績を14年間追跡した脳卒中死亡率のデータがあります。収縮期血圧140以上は現在高血圧といわれていますが、死亡率は65歳以上で格段に上がります。180以上ですとものすごくリスクが高くなります。65歳未満でもリスクは階段的に上がっています。非常に血圧の低いレベルで脳卒中が多いのはどういうことか説明がまだよくつきませんけれど、心臓病のような脳卒中のリスクを持っていることが影響しているのかも知れません。これだけが例外ですが、65歳以上になると階段的にリスクが上がり、140以上になるとリスクが明らかに高いという成績になっております。これは滋賀医大の上島教授がまとめられた日本人についての非常に貴重なデータです。140に線をおいてコントロールを厳重にするためにも、正常かどうかの判断も140でという考え方を持つためにも、これは非常に重要なデータだと思います。
次のデータも同じことです。これは福岡県・久山町の脳出血と脳梗塞のデータで、青が脳出血、グリーンが脳梗塞です。140を超えると段々上がってきて、高ければ高いほど男女とも事故が多く起こっています。あらゆるデータが140以上になるとリスクが高くなることを指しています。外国でも同じようなことをいっております。
高血圧と糖尿病が合併すると非常にリスクが高くなります。しかも糖尿病の人はそうでない人に比べて高血圧の頻度が2倍です。また高血圧の人は血圧が高くない人に比べて糖尿病の頻度がやはり2倍で、しかも両方合併している人の数は多いのです。これに高コレステロール血症等のリスクを加えていくと、重なれば重なるほどリスクが多くなります。このようにいくつも危険因子が合併した状態をメタボリック シンドロームと呼んでいます。
糖尿病は特に最近増えており、注意が必要です。空腹時の血糖は110、75gのブドウ糖を飲んだ場合は140までが正常で、200を超えると明らかに糖尿病です。空腹時に126以上ある場合も糖尿病です。こういう基準で糖尿病の予防や管理治療を厳密に行うべきです。血圧の平均値は以前より少し下がってきましたが、糖尿病は大幅に増え、高脂血症も昔に比べるとだいぶ増え、お酒はなかなか減ってないし、たばこは最近だいぶ減ってきましたが、リスクがこのように重なってくると危険性が高くなります。
高血圧それ自体で死ぬことはありません。血圧が高くても血管が丈夫であれば、直接の事故は起こりません。心臓が肥大して大きくなり、血管がやられるので事故が起きるのです。事故を防ぐのが血圧治療の目的で、他のリスクを念頭において、生活習慣をコントロールすることが大切です。生活習慣に個人差があるように、病気の性質にも個人差がありますから、自分の健康状態をよく知って、記録して、それをもって医師や健康管理をする人と相談し、長生きを考えることが必要だと思います。
日本人の寿命はこれ以上伸びるかどうか。このまましばらく続くかもしれませんが、そのうち沖縄の男性みたいに短くなるのではないか、と私は心配しています。10年、20年先はどうなるだろうか。若い人の健康状態が昔の人よりよくないのではないか。いろいろなリスクが増えていることを考えると、健康管理は従来よりも厳密に行う必要があります。本日はひとつの具体例として血圧を取り上げてお話をさせていただいた次第です。少しでも皆様方の健康管理の参考にしていただければ非常にありがたいと思います。