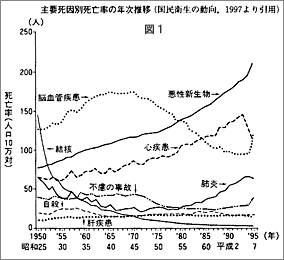| NO.17 |
心臓血管病と薬の正しい知識を得るために
(7−1)

札幌医科大学医学部第2内科 中田 智明
薬を使わないで直すのが一番良い

「生活習慣病」は最近新聞等でよく目にする言葉ですけれど、実際どういう病気なのか、どういう背景があるのか、その為にはどうしたら対応したら良いのでしょうか。
病気をなおす1つの方法として薬がありますが、薬の服用とは"外来の物質"を体に入れることで、それで100%治せるわけではありません。ですから、薬を使うということは、薬を使う正当な理由も必要ですし、また正しく使わなくてはいけません。当たり前のことですけれど、本来なら薬を使わないで治すのが一番良いわけです。ですから、そういう薬を使う背景と言いますか、病気の根本的な原因と言うか、自分の病気あるいは健康がどういう状態かを理解していただければ、薬も正しく飲まなければいけないとか、薬を飲む必要がない、その前の段階で病気を防ごうとか、あるいは治そうということが重要だということを皆さんにも理解していただけると思います。「ただ薬を飲めばいいや」という考えでやると、十分有効な作用が出ずに、逆に不都合な副作用だけが出てしまうような、非常に具合が悪いことがおこります。このことを理解していただきたいということで、今回私はこの後に話す薬剤師の清水先生の前座みたいな形で、生活習慣病について皆さんにお話しようと思います。
生活習慣病というのは、今までは成人病と言われていた病気とほぼ同じですね。でもこの病気は生活習慣が原因となって発症したり、あるいは悪くなったりしますから、厚生労働省は生活習慣を改善すれば予防できる、あるいは治療にも有効であるという意味で、生活習慣病と言い換えたわけです。また最近では、いわゆる成人に限ったとではなく、子供のうちの生活習慣も関与し、時には子供のうちから発症しうる病気という意味合いもあります。この場合の生活習慣とは、食習慣、運動、睡眠、飲酒、喫煙、あるいは日々のストレスなどが含まれます。生活習慣病は、広い意味では癌も入ります。癌にも遺伝子が関係しますが、食習慣、例えばタバコだとかアルコール、あるいは肝炎ウイルスなどの外的因子が加わって、癌細胞ができてきます。今日お話する生活習慣病−脳卒中(脳血管障害)、心臓病、大血管病があります−も、それと同じように、ある程度の遺伝因子は関与しますが、色々な悪い習慣、あるいは生活習慣、環境因子が加わって病気とういう形になって発症していきます。したがいまして、生活習慣病のひとつとして、心臓血管病もとても重要なわけです。
では、生活習慣病としての心臓血管病とはどういうものか具体的にお話します。良く聞かれる言葉に"危険因子"と言うのがあります。この危険因子とは、生活習慣病としての心臓血管病を引き起こす影響の大きい因子のことを言います。危険因子が多いほど病気になる可能性が高く、逆に少ないほど病気の予防にも有効です。既に病気が発症している場合には、危険因子を減らすことは治療にも結びつきますから、自分の危険因子をチェックすることはとても重要です。
定義がだんだん厳しくなる高血圧
よくご存知の危険因子の一つである高血圧は、その定義がだんだん厳しくなってきました。つまり、「より低く下げよう」という時代になって来ています。140/90mmHg以上あれば高血圧です。どちらかの数値を満たせば、高血圧です。上の血圧が150mmHgで下の血圧が80mmHgでも高血圧ですし、上の血圧が130mmHgで下の血圧が96mmHgでも高血圧です。上の血圧、下の血圧どちらか一方を満たしたら、高血圧です。やはり重要な危険因子に、糖尿病や高脂血症、いわゆる悪玉コレステロールが高いという病気、があります。中性脂肪が高いこと(高中性脂肪血症)も最近では危険因子と認識されつつあります。それから家族歴−つまり血のつながりのある肉親の方に生活習慣病の方がいるか、これは2親等以内です−も危険因子になります。おじいちゃん、おばあちゃんまでさかのぼって、家族歴(血縁関係の方にこういう病気)があった場合には、自分も同じ生活習慣病になる確率が高いということです。以前に心血管病、脳血管障害を起こした人は、再び同じ病気になりやすいと言われています。この既往歴も、危険因子になります。過去にそういう病気を1度発症した人は、もう1度なりやすい、初めての人よりはずっとなりやすい、だから再発の予防もとても大事になります。年齢も危険因子として重要で、年齢とともに生活習慣病になりやすくなります。性差でいえば男性が生活習慣病になりやすいのですが、女性も月経があるうちはホルモンが守ってくれますが、更年期を過ぎ女性ホルモンが消えていきますと、男性なみに、生活習慣病になりやすくなります(女性では65歳以降、と男性より10年近く遅れます)。
善玉コレステロールという言葉を聞いたことがあると思いますが、HDLコレステロールと言います。これが低い場合にはやはり生活習慣病になりやすい。つまり、動脈硬化を引き起こす悪いコレステロールが増えて(いわゆる高脂血症)、体を守ってくれる善いコレステロールが減ってしまう(低HDL血症)。これが脂質代謝異常といわれるものです。それから肥満、喫煙、運動不足、ストレス、これらはすべて重要な危険因子でやはり生活習慣病になりやすくします。肥満は、ボディー ・マス・インデックスと言って、身長と体重から簡単に計算できます。体重を身長の2乗で割って計算できます[ 体重Kg÷(身長m)2)]。これは26.4以上を一応肥満と定義しています。先ほど言いましたが、このような多くの危険因子が生活習慣病の発症に関係しており、1つより2つ、2つより3つ、3つより4つある人のほうがずっと病気の発症の危険性が高くなるということが知られています。
生活習慣病の中身は何かというと、虚血性心臓病、いわゆる心筋梗塞、狭心症。あるいは脳血管障害、いわゆる脳卒中ですね。それから、虚血性心臓病が原因となって出てくる心不全という病態もあります。また、動脈硬化のために動脈自体が瘤のように大きくなる動脈瘤、逆に詰まってしまう閉塞性動脈硬化症という病気もあります。
図1は死亡原因の経年変化を見たものです。昭和25年から平成7年まで、癌はこのように増えています。ですから、癌対策にお金が沢山使われているわけですけど、これには、肺癌、胃癌、乳癌、子宮癌、骨の癌などすべての癌を含みます。心疾患は、最近少し減ってきていますけど、戦後ずーっと増えてきています。脳血管障害は、減塩食と高血圧の治療がうまくいったため、昭和45年位をピークにして、ずっと減ってきましたが、最近また増えてきています。動脈硬化を基盤として発症する心疾患と脳血管疾患を足してみたら、その死亡率は癌と同じか、もしくはより多くなります。ですから、政府は癌対策にお金をより多くかけていますが、心臓病や脳血管障害の対策も極めて重要だということが分かります。
 |