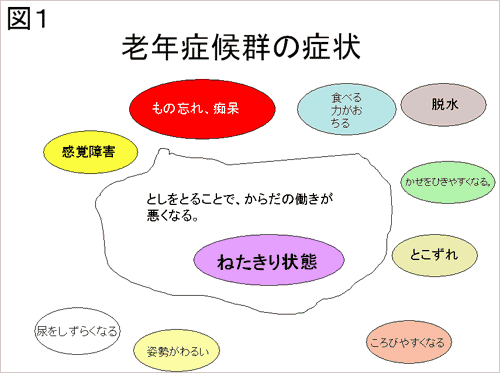| No.35 |
高齢者の体と心〜元気に老(ふ)けたい〜 (1/6)
十勝の杜病院副院長 佐藤篤司先生
とかち健康フェア2004の講演から(平成16年11月21日・帯広市とかちプラザ)
ちょうど1年前、私はこの会場で講演させていただき、肥満について講演いたしました。肥満は生活習慣病になりやすい状態であり、肥満を防止することは生活習慣病の予防はもちろんですが、その究極の目標は生涯を通じて健康に生活することだ、というお話をしました。今日の話題はその続きのようなもので、それでは生涯を通じて健康に生きていくとはどういうことか、ということについてお話しいたします。
皆さんご存知のように、私たちの生涯は大きく小児期、成年期、老年期に別けられます。小児期から成年期への変化はドラマチックです。性徴期があり、性の芽生え、妊娠、出産と大きく体が変わります。みなさんは、大人になっていくのがどういうことかを学校で行われた性教育で教わったと思います。それに対して成年期と老年期の違いを明確に知らされる機会は少ないのではないでしょうか。成年期の延長線上に老年期があるとばくぜんと考えている方が多いのではないかと思います。しかし、実際には老年期と成年期は明確に異なるものです。
きょうの講演の狙いは、老年期特有の体と心の変わりようについて、老年医学の立場から解説することです。老年医学とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、お子さんに対して小児科があるように、最近、大学などで老年医学といって高齢の方の医学を専門に扱う科が見られるようになってきました。まだ発展途上の学問ですが、高齢者とはこういうものだ、という意味付けがされてきていますので紹介します。この講演をきっかけに、元気に老けるとはどういうことなのか、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
増加する高齢者と老年症候群
65歳以上の方を高齢者と呼びます。日本も含め、先進国では高齢者の割合が段々と増えてきております。日本では20世紀初頭は高齢者の割合が他の先進国にくらべて非常に少なかったのですが、戦後、急速に高齢者の方が増え、2000年で15%を超えました。14%を超えると高齢社会と言われますので、21世紀になって、日本はまさに高齢社会に突入しました。あと20年も経つと、日本の国民の4人に一人は高齢者になる時代になると予想されています。このように急速に高齢者が増えているのは、戦後、生活環境が改善され、また医学も発達してきたせいではないかと考えられます。
高齢者の体の状況を簡単に説明します。まず、老化で心臓、肺、脳、腎臓など臓器の働きが悪くなってきます。また、体を動かさなくなるので筋肉の働きが悪くなってきます。よく言われる生活習慣病には高血圧、糖尿病、高コレステロール血症などがありますが、これらは体の老化を後押しします。このような病気を予防することは、臓器の老化速度を遅くすることでもありますから、若い時から生活習慣病は一生懸命治療しましょう、と言われているわけです。
今申し上げたような身体状況の結果、多くの方が老年症候群という状態に陥り、そのうちの何割かは寝たきりになります。そういう過程で体や心に現れる老化の症状を総称した言葉が老年症候群です。老年症候群は糖尿病であろうが、血圧が高かろうが、持病のいかんに関係なく、あるいは持病がなくても何らかのきっかけでなることがあります。
具体的に言うと(図1)、まず歳をとることで体の働きが悪くなり感覚障害が出てきます。物忘れ、痴呆、食べる力の低下、脱水等々です。高齢の方は風邪をひいて具合が悪くなっただけで、すぐ脱水状態になり点滴が必要になることがままあります。免疫力が落ちているので風邪をひきやすくなります。転びやすくなるし、歩行障害も出てきて姿勢も悪くなります。おしっこもしづらくなります。これらもろもろの症状が進んだ結果、寝たきりになる方も出てきます。この寝たきりに伴って床ずれが起こりやすくなります。この図に示した症状はいずれも特別なものではなく、高齢者を介護しているとよく目にする状態だと思います。こういった諸々の症状をひっくるめて老年症候群と呼びます。こういった症状は、本人もまわりも年だからしょうがないと何となくあきらめられがちな傾向があると思われますが、これらをしっかりとていねいにケアをすることで、高齢者の日常生活の質をある程度改善することが十分可能です。
本日の講演では老年症候群の中から、まず転倒について、次に痴呆(演者注:現在は認知症と名称変更を推奨されていますが、まだ一般的ではないと判断し、本講演中は痴呆の名称を用いました。)について、そして寝たきりとはどういう状況かというお話をし、最後に老年度について触れます。老年度というのは高齢者のいろいろな機能、具体的には体の働き、頭の働き、気持ち、心の問題といったことを評価する方法です。
高齢者の転倒について
まず転倒についてお話します。転ぶこと、これがどうして問題になるのか不思議に思われるかもしれませんが、非常に大きな理由があります。高齢者の不慮の事故の種類別死亡割合をみると、およそ5人に1人は転倒、転落で亡くなっています。ですから、転倒といっても、それで命を落とされる方が多数いらっしゃいますので決してあなどれないとお考えください。
なぜ高齢者は倒れやすいのでしょうか。皆さんは多分、足腰が弱いからだと思われるでしょう。実際そういうことを調べた人がいます。20歳〜80歳、男女別に膝を伸ばす力と曲げる力を調べた結果、これが80歳位になると、男女ともに膝を伸ばす力曲げる力が20歳台の半分から1/3程度まで落ちてしまうことがわかりました。
次に筋肉の量が高齢になると減っているのではないか確認しようと、歩くのに必要な大腰筋の大きさを計ってみた人がいます。その結果80歳になると大腰筋の大きさが20歳台の半分以下になってしまうことがわかりました。これらの結果から、歳をとると筋肉の力が減るだけではなく、筋肉の量そのものが減り、その結果歩く速さも段々遅くなり、機敏に早く歩けなくなるのです。
我々は歩行の際、筋肉以外に体のどういったものを使っているのでしょうか。目で見て障害物を避けるために視覚が必要です。目で見えたものをもとに脳の中で場所や方向を判断しています。耳の後ろに三半規管があり、そこで体のバランスを保つようにしています。大腿四頭筋や大腰筋をはじめとした筋肉が足を動かします。また、足の裏でものを感じ何か危ない物の上に乗かったらそれを避ける、などといった動作を行います。その他、耳で聞こえる音によって危険を察知することもあるし、皮膚で風や温度を感じ、それも歩く上で情報にします。要するに、五感をすべて利用して人間は歩いているのです。高齢者の方はこれらの働きがすべて低下しますので、歩行をサポートするための五感を通した情報を得られなくなり、若い人に比べて不利な状況に置かれることがわかります。
また、一般的に高齢者は足を開いて歩きます。恐らくバランスを保つ為だと思われます。さらに、若い人に比べると歩幅が小さくなります。さらに、歩き始め、立ち止まり、方向転換がうまくできません。そういった状況の結果、転倒が非常に多くなります。