| No.78 |
心臓拍動のしくみ ―心臓自動能の解明―
(1/1)
北海道文教大学 健康栄養学科教授 札幌医科大学名誉教授
當瀬 規嗣 氏
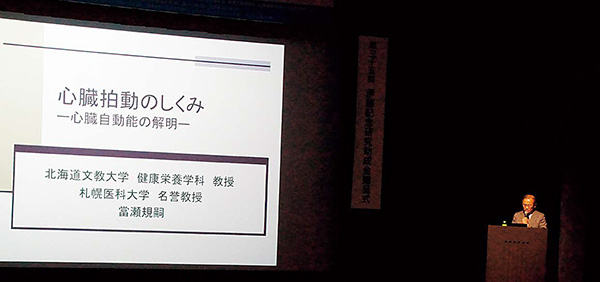
本日のテーマの「心臓拍動のしくみ」とはどうやって心臓が動いているのかを解明することなのです。心臓は縮んで、血液を全身に送り込む。縮むと血液がなくなるので、一旦拡張して、静脈側から血液を導いてもう一度心臓から血液を全身に送り出す。この収縮と拡張を繰り返すので、ポンプと言うわけです。
心臓は体から離れても、自分で動く力を持っています。この動く能力のことを自動能と言います。心臓の動き方を神経が調節して、早くなったり遅くなったり心臓の中に心臓が動くための一種リズムを作る場所があると考えます。それが洞房結節と呼ばれている場所で、その細胞の集団がリズムを取っているので歩調取り細胞とかペースメーカー細胞と呼びます。場所がわかると、今度は電気がどうやって起こるのかという話になります。そこでイオンチャネルというのが出てきます。細胞の一番表面に、細胞膜という薄い膜があり、そこに埋め込まれているタンパク分子には穴があってイオンだけ通過させることができます。イオンは電気を帯びているので電気が流れたという考え方です。
電気が通ったらどうなるのかと言うと、心臓は電気が伝わっただけでは動かないことがわかってきました。外からカルシウムが入ってこないと心臓って動かないんです。
そのカルシウムはいつ入るかというと、先ほど言った活動電位の信号が来ると、その信号をタイミングにして、細胞の外側からカルシウムが入ってくる。そして、入ってくるルートがイオンチャネルなんです。そこを通って、細胞の中にカルシウムという関係にあるから、心臓に電気が起きると実は心臓が収縮するのです。
ペースメーカー電位ですが、心臓が動くためのリズムが早くなったり遅くなったりするのは、洞房結節に存在するはずの、ある種類の細胞の中の方に入ってくる電流がその犯人なんだろう。つまりイオンチャネルが犯人なんだろうっていうのはわかってたんですが、どのチャネルなのかがどうしてもわからない。
私の兄弟子の野間先生がペースメーカー電流の元になるイオンチャネルを通過する電流ではないかと言うことを発見しましたがこれに大反対するグループがイタリアにいて、以来ずっと30年ぐらい喧嘩状態が続いて、まだ結論が出てないんです。
それで僕も結論が出ないのは悔しいので、別な方法からアプローチをしました。心臓は生まれる前から動いているが、受精してから、赤ちゃんになるまでの間のどこかのタイミングで心臓が動き出すのでそのタイミングをはっきりさせたらわかるんじゃないかなと思い調べ始めました。そしてカルシウムチャネルが有力候補だと分かりました。
まとめますと、これまで、心臓が自分で動くしくみというのは不思議だなと思って散々やってきましたが、洞結節細胞に自動能があって、それがペースメーカー電位です。それはイオンチャネルによってできるんですよっていうわけで、心臓が一番初めに動き出すときも先に起こることは細胞の中にカルシウムが増えることだということで、結局いろんな理由でカルシウムチャネルがすごく大事だということをお伝えして本日の話を終わります。

