| No46 |
命あるもの みな美しく
(1/6)
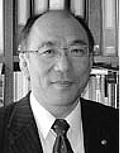
小菅 正夫氏
先程筒井先生の講演でAEDの話がありましたが、多くの人が旭山動物園に来ますので、救急救命の事については、救急隊による研修を受けたりと色々とやっています。3年前でしたか、AEDが配置される事になり職員皆でその使い方を練習しようと、消防署に依頼して研修に来てもらい、何班かに分けてやりました。
あれは冬、雪が降っていた時のことです。私もかなり太っていますけど、名古屋からみえられた私よりもう少し体格のいい方が突然バタっと倒れました。もう顔には血の気が全く無い状態で、あっと思ったのですけど中々やっぱり自分ではスっと出来なくて、常駐している看護師がすぐにAEDを持っておいでと指示して、そして先ほどの筒井先生がお話した通りに対応したのです。そのうちに救急車が来て旭川医大に搬送され、ひと月位入院されていたと聞きました。その後名古屋に帰られて無事元気にしていますというお手紙を頂きました。本当に人は一人の命をこういう事で救えるのかと、そこに居た人皆がすごくありがたいような幸せな気分になったのを今もまだ覚えています。本当にいつどうなるかわからないという意味では、先ほど突然死の話がありましたけど、まさにその通りです。
ご講演を聞いていて平成6年にうちのゴリラのゴン太というのがエキノコックスで死亡した時のことを思い出しました。エキノコックスでゴン太が死亡したというのは、全国ニュースになりましたから、皆さんよく知っていると思います。その1年後にメスのマリが、それこそ何の前触れも無く倒れました。前日どころか当日の朝まで食欲もあり何ら問題も無く、部屋から外に出て行きました。そして午前中普通通り暮らしていたのですが、11時頃でしたか、職員から通報が来て「マリが倒れている!」と聞いてダーっと走って行ったのですけれど、もうつ伏せになって絶命していました。その時、全く肉眼的には何もなくて、もうとにかく何で死んだのかまったく判らなかったので病理解剖をし、その後病理標本を作成し、病理専門の先生に見てもらいました。最終的に旭川医大の病理の先生に見てもらいましたがやっぱり心臓系の突発死だというような診断でした。もしかしたらあの時にAEDがあればな、とチラっと思いながら先ほどのご講演を聞いていました。本当に「いつ」というのがわからないというのが、生きている限り何ともしようがない事なのだと思います。とは言っても、それだけを恐れて云々と言っていてもこれは詮無い話で、一応出来ることだけはしっかりと頭の隅でも良いからおさえておきながら、やはり命ある限りしっかりと生きていくというのが生き物の定めなのかなというような気がします。
今日の演題ですけれども「命あるものみな美しく」、こういうきれいな演題を作れる人は私じゃないですね、絶対に。これは北海道心臓協会の方に付けてもらったのですけれど、私がこれを喋るにも関わらず、私がこの演題を見て「いやー素晴らしい演題だな」と思ったのです。では命無いものは美しくないのかというと、そういえばそうだなと思うのです。命あるものというのは、皆美しい姿形をしているんです。これは後ほどお話しますが、やっぱり命があるというのはそういう事なんだろうなと。例えば命の無いもの、石ころだとか色々命の無いものがありますが、あれは美しくしなければ美しくなりません。命あるものは何もしなくても美しい。そういう事を全部含めて、これはきっと生きているというのは美しいものだなというような事を話せよという意味なんだなと思いました。それでは今日のお話、美しいという事、今生きている事はこういう事なんだという事を具体的に話をしたいと思います。
 |
|
|
進化の過程で獲得した特有の形態と能力
私は北大を出てからずっと旭山動物園にいて、二百数十種類の動物とずっと付き合ってきましたが、どの動物も皆本当に凄いなと感心させられるのです。先程の生きているものは凄いというのはそういう事なんですが、動物というのはその「種」ごとに皆姿形が違うわけです。人間はこういう形をしているし、オランウータンはこういう形をしている、ヒトデだってこういう形をしている、タコは8本足でこういう形をしている、皆その種類ごとに特殊な形をしているのです。見た目ですぐわかるわけです。ではその姿形というのは何かというと、これはその動物にとってそれが最も優れているからなのです。オランウータンがああいう形をしているのも、タコが8本足でああいう形をしているのも、タコがタコとして生きるにはあの形が一番美しくて、一番有利で、一番自分の能力を発揮できるその姿形なのです。その姿形というのを彼等はどうやって獲得したのかというと進化の過程─皆様も進化というのはご存知でしょうが、要するに地球の歴史の中で長い長い時間をかけてその種が形成されていく。その進化の過程で獲得したものなのです。私はよくジグソーパズルと言うのですが、自分がああしようこうしようというのではなく、生態系というジグソーパズルの中にピタっと当てはまるような姿形に基本的に形作られていった。その美しさが生きている美しさではないかと私は思います。
では、この生きていくためとは何かという事ですが、これは究極的に生きていくためというのはこれしかありません。生きていくというのは毎日食べる事、食べなければ死んでしまいますから食べるというのは自分の中で命を永らえる事、これは食べる事だけです。それから繁殖する事、個体というのはゆくゆくは死んでしまう。誰でもこれはわかっている事で、この命を継続させる為には繁殖させて次にバトンタッチするしか無いので、生きていくというのは要するに食べていつも健康に自分の体を維持する事。それから繁殖をしてその命をバトンタッチする事。この二つを貫徹するためにその有利な姿形や能力というものを、進化の過程で生物というのは獲得してきたのだろうと思います。
非常にわかりやすい話をしますと、キリンというのは皆さん動物園で見た事が一回はあるでしょうけど、首が長く背が高い生き物です。非常に特殊な生き物です。しかしただそれだけではありません。長い首、長い頭をしていますが、40センチもの長い舌を自由に口先に出して、なおかつ小さな木の枝をクルっと舌先で巻いて食べる。こういう能力を持っているんです。こういう能力を持っているから、キリンは他の動物が利用できない高い木の葉っぱを自由に獲得することが出来る。だから地球上で今も生き残っているわけです。こういう能力を獲得出来なかったら多分キリンというのは出てきても、進化の中で消えていってしまうと思います。
それからクモザル。これは中央アメリカや南アメリカのジャングル地帯に棲んでいますが、尾っぽが長い。クモザルという位ですからクモの様なサルという意味です。尻尾で自分の身体を完全にぶら下げる事が出来ます。要するに両手両足を全く自由に使えるということです。彼等は中南米のジャングルで、尻尾だけで自分の身体を固定して両手両足でその辺にある餌を取って食べる事ができる。このような尻尾を身に付けて、能力を身に付けたから彼等は今も地球上に生存する事が出来ているわけです。
それからキツツキ。キツツキの舌は長いです。これは皆さん良く知っています。しかしキツツキは舌をどうやって使っているのか。これは今まで誰も見た人はいませんでした。なぜかというと、木の中に巣食っている虫をキツツキは食べているわけですから、これは絶対見えません。解剖してキツツキの舌を引っ張ってみたら長いと、きっとこれはこうやって使っているのだろうという事は想像できました。しかし実際にキツツキがこうやって餌を食べるっていうのは、多分誰も見た事がなかったはずです。クマゲラもアカゲラも、長い舌を出して虫を引っ張り出し、吊り上げて食べます。この長い舌の先5ミリ位には細かなトゲが内側に向けて生えています。それから唾液まで使って、とにかく虫の作った道の中に居る虫を引っ張り出して食べる。この舌、この能力を身につけなければキツツキはとてもこの厳しい自然界では生きていけない訳です。

