| NO.10 |
「ストレス」
(1−2)
北海道大学大学院医学研究科
予防医学講座公衆衛生学分野
岸 玲子
西條 泰明
生理的、心理的…多様な影響/自助には限界も、周囲の目こそ
1 はじめに
現在はバブル経済崩壊後の長い不況の中にあり、終身雇用制の崩壊、成果主義賃金制の導入、リストラなど雇用状況も大きく変化しているので、仕事に関するストレスはかってないほど大きくなっています。人員削減等のため、過労状態も多いと考えられます。働く人々の虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)や脳出血など、仕事上のストレスが関係したと認定されるいわゆる「過労死」については、平成13年度の脳・心臓疾患による業務上認定件数は143件と前年度(85件)に比べ68%の大幅増となっており、厚生労働省の認定基準の緩和もありますが、過労やストレスへの関心が高くなっていることも背景にあると思います。ここでは、その仕事などによるストレスの心臓・血管病への影響をとりあげます。
2 ストレスの心臓・血管系への影響
ストレスと心臓・血管系との関係については、(1)ストレスがストレスホルモン(ストレスが強い状態で多く産生されるホルモン)を介して心臓・血管へ直接作用する、(2)ストレスが心臓・血管病の危険因子である高血圧や糖尿病の原因となる、(3)ストレスによるライフスタイルの変化、が考えられます。
ストレスにより交感神経が刺激され、ストレスホルモンであるカテコールアミン(アドレナリン、ノルアドレナリン)の産生が増加します。カテコールアミンは、心臓に対して心拍数(脈拍数)や心臓の収縮力を増加して心臓の負荷を増やします。また、心臓を栄養する血管である冠動脈の交感神経受容体を刺激して冠動脈の収縮をきたす可能性があります。また血液の凝固能が亢進することも知られています。以上の、心臓の負荷の増加は心筋への必要血液量を増やし、また冠動脈の収縮や血液の凝固はそのまま、冠動脈を狭窄・閉塞させて心臓への血液の供給を悪くして、虚血性心疾患の原因となる可能性があります(図1)。
そのほか、ストレスは心臓・血管病の危険因子である高血圧、糖尿病にも関係します。交感神経刺激やカテコールアミンは心臓の収縮力を増して、全身の血管を収縮させて血圧を上昇させます。また、カテコールアミンの他にストレスホルモンとしてコルチゾールがストレス時に増加しますが、両者とも血糖を上昇する働きがあり糖尿病にも関係します。また、ストレスは過食、過度の飲酒、喫煙といった行動の変化も介して動脈硬化の可能性を高くします。
3 仕事のストレス
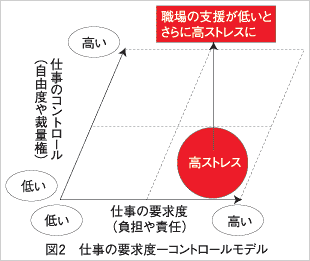
仕事のストレスは心疾患のほかに、同じく動脈硬化性疾患である脳血管障害(脳梗塞や脳出血)の発症に関係し、その他にもうつ病を介しての自殺の増加(1999年には日本で33,000人が自殺でなくなっています)に関係するなど社会的な問題でもあります。その仕事のストレスの評価には「仕事の要求度・コントロールモデル」が有名です(図2)。具体的には仕事の負荷・責任などの仕事の要求度と仕事の自由度・裁量権(コントロール)を指標として、仕事の要求度が高くてコントロールが低い場合にストレスが高くなり健康問題が生じやすいと考えられます。さらに、職場での上司・同僚の支援も重要でそれらが低いとさらに問題が生じやすくなるとされています。


