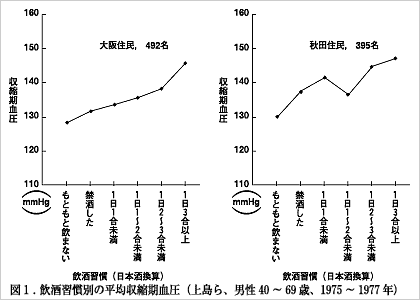| NO.8 |
�A���R�[��
�i�P�|�P�j
�s�������a�@����
�H���c�@�r�A���@�Y��A��@�p�Y
�D���ʐ��ޓK�x�Ȉ����^�ő�֖̊�͐ߎ��̓��
�A���R�[���͐S���E���Ǖa�̊댯���q
�@�������������㏸�����邱�ƁA���ʈ������������S������]�����Ȃǂ̐S���E���Ǖa�Ɉ��e���������炷���Ƃ͗ǂ��m���Ă��܂��B�t�ɁA�A���R�[���͍D�e�����L���Ă���Ƃ������Ă��܂��B�Ⴆ�A�@���ʈ����҂͔�����҂ɔ�ׂ�Ɠ����d�����y�x�ł���A�A���R�[���ێ�ʂƋ������S�����Ƃ̊Ԃɂ͂t�^�̊W�����菭�ʈ����҂͔�����҂�莀�S�����Ⴂ�A�Ƃ���������Ă��܂��B�����͓K�x�̈����ɂ��A���_�I�ْ����ɘa����邱�Ƃ��W���Ă���ƍl�����Ă��܂��B
�j���̐ߎ�ڈ��͓��{���P���^���ȉ�
�@2000�N�ɓ��{�������w��쐬�����u���������ÃK�C�h���C��2000�N�Łv�̐����K���̏C�����ڂ̒��ł́A�O�q�̗��R�ō��������҂���ł͈��𐧌��̎w����K�v�Ƃ��܂����A�������ւ���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ���Ă��܂��B��̓I�ɂ́A�A���R�[���̓G�^�m�[�����Z�Œj����20�`30���^���i���{���P���j�A������10�`20���^���ȉ��ɂ��ׂ��Ɗ������Ă��܂��B�������j�����A���R�[���ێ�ʂ����Ȃ��̂́A�����̓G�^�m�[���̋z�����悭�A�܂��̏d�̌y���l�̓A���R�[���̉e�����₷�����Ƃ��l���������ʂł��B
����ʂ������قnj����l�������Ȃ�
�@���A�H�c�̏Z�������ł́A����ʂ̑����l�قǍ��������҂���̕p�x�������A����Ɏ��k������ъg���������������Ƃ������ʂ��o�Ă��܂��i�}�P�j�B���ɁA�����R���ȏ��������l�́A���Ƃ��ƈ������Ȃ��҂ɔ�ׂĎ��k��������17mmHg�����l�ł����B�z�펾����b�����ł́A�}�Q�Ɏ����܂��悤��30�Α�̎Ⴂ���ォ��70�Έȏ�̍���҂ɂ킽��܂ŁA������������l�ł͂��Ƃ��ƈ�������K���̂Ȃ��l�ɔ�ׂĎ��k�������͖��炩�ɍ��l�ł����B�܂��A���̉e���̋����́A������������l��10�ΔN��̍������Ƃ��ƈ��܂Ȃ��l��荂���A10�̉���ɑ������錌���l��L���Ă��܂����B �@
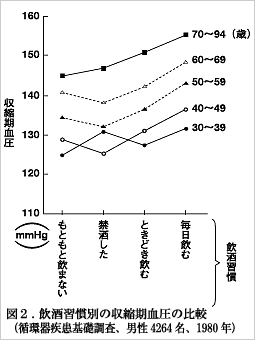
�A���R�[�������̎�ނƂ͖��W�ł�
�@���ۋ��������ɂ��A�A���R�[�������̎�ނɊւ�炸����ʂƍ������Ƃ̊֘A���F�߂��܂����B�����ŁA�����ɂ̓A���R�[���̐ێ�ʂ��̂��̂��֗^���Ă��āA���{���A�r�[���A�Ē��A���C���ȂǂƂ����A���R�[�������̎�ނɂ��Ⴂ�͂Ȃ��ƍl�����Ă��܂��B
�����㏸�ɂ̓A���R�[����ӌn��`�q�I�f�����֗^�H
�@�A���R�[�����̂��̂̍�p�Ō������㏸�����邱�Ƃ͋^���̗]�n������܂��A���̋@���ɂ��Ă͗ǂ��킩���Ă��܂���B�A���R�[����ӌn��`�q�ł���܂��A���f�q�h�E���f�y�f�Q�^�����̌����҂����{�l�ł�40�`50���ƍ����ɂ���A���ʈ������ɂ͂����̈�`�q�I�f�����֗^���A�S������S���o�ʂ������Č������㏸������\��������܂��B�܂��A�A���R�[���͑S�g�̌��ǃg�[�k�X�ْ̋������߂Č������㏸������ƍl�����Ă��܂��B
�ߎ��̍~�����ʂ͒��������
�@�ߎ��ɂ�錌���l�̒ቺ�����҂���A�����̕���A�s���̗ǂ����Ƃɂ͐ߎ��̌��ʂ�1�A2�T�Ԃ̂����Ɍ���邱�Ƃ����炩�ɂ���Ă��܂��B�}�R�Ɍy�Ǎ��������҂���ŕ�������Ă��Ȃ��l��ΏۂƂ��āA�ߎ��ɂ�錌���̒ቺ�ׂ����т������Ă��܂��B���{���ɂ��ĕ��ςQ�����x�������Ă���30�`59�̒j���ɂP�����x�ɂȂ�悤�ɐߎ����Ă��炢�܂����B�ŏ���3�T�Ԃ͂`�Q�ɂ͐ߎ��܂��͋֎����A�a�Q�ɂ͕���̈����K����ۂ悤�ɁA������3�T��ɂ́A�t�ɂa�Q�ɐߎ����A�`�Q�ɂ͕���̈����K���ɖ߂��悤�Ɏw�����Ă���܂��B���̌��ʁA�ߎ��ɂ��1�`2�T�ԂŎ��k����������TmmHg���傫���ቺ���邱�Ƃ��ώ@����Ă��܂��B
�~����p���̑��ʈ����҂͐ߎ��������ł�
�@�~����̍��������҂����Ώۂɂ��������ŁA����ʂ����炷�ƌ������ቺ���A�Ĉ����ɂ�茌�����㏸���邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B���̂悤�ɑ��ʈ����͍~����̌��ʂ����コ����̂ŁA���ʈ����𑱂��Ă��܂��ƍ~����̌��ʂ��\���Ɍ���܂���B�����ŁA�~����p���Ă��鑽�ʈ����̊��҂���́A�ߎ����邱�Ƃɂ��{���̖������������A�~�����ʂ����܂ł������ǂ�����邱�Ƃ����҂���܂��B
���N���ł��A���ɂ́u�R�����ցv�̊���肪�K�v�^
�����A�c�O���傤�͐����ƕʂ̖�����܂��āc�{���Ɏc�O����
�ߎ��ɂ͉ƒ�ł̊����P���d�v
�@�ߎ��̃R�c�Ƃ��Ă͕\�Ɏ��������̂�����A�F�X�ȍH�v�����Đߎ��i�w���j���s���K�v������܂��B�܂��A���ʈ����҂ɂ͐ߎ����S���E���Ǖa�̗\�h�Ǝ��Â̏�ŏd�v�ł��邱�Ƃ�F�����Ă��炤���Ƃ���O��ƂȂ�܂��B�������A���ʈ����K���̂���l�͖{���������D���Ȑl�ł���A��`�I�ɂ��A���R�[���̕��������₩�ɍs����l�ł���̂ŁA�ߎ��w���͂Ȃ��Ȃ�����Ȃ��Ƃ������悤�ł��B�܂��A�u�قǂقǂɁv�Ƃ����ߎ��w�����s�����Ƃ��悭����܂����A�A���R�[���̍D���Ȑl�͎�����������Ɉ���ł���ʂ��u�قǂقǁv�̗ʂƍl���Ă���̂ŁA���ӂ��K�v�ł��B
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||