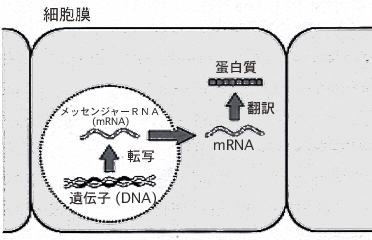| NO.6 |
動脈硬化と遺伝子治療
(2−1)

北海道大学医学部 循環病態内科学 浦澤 一史
2.病気と遺伝子動脈硬化とは、血管壁(特に一番内側にある内膜)にコレステロールやカルシウムなどが蓄積した結果、血管内腔が狭くなり、血液の流れが妨げられた状態を言います。動脈硬化が進行すると、高血圧、狭心症、心筋梗塞、脳血管障害(脳梗塞・脳出血)、腎機能障害、下肢の閉塞性動脈硬化症など様々な病気の原因となります。
本来、動脈硬化は加齢に伴い誰にでも認められる老化現象のひとつですが、その程度は個人差が大きく、生活習慣や環境要因に大きな影響を受けます。なかでも、高脂血症、高血圧、喫煙、糖尿病、肥満、運動不足などが、動脈硬化の進展と密接に関連していることが知られています。
先に述べた動脈硬化が原因となる各種の疾患を予防するためには、日頃からこれらの動脈硬化促進因子(危険因子)を減らすための努力が重要です。まずはじめに、適切な食事、禁煙、適度な運動といった生活習慣の改善を行い、必要に応じて内服薬による血圧、血清脂質、血糖の調節などが必要となります。
人間の身体は約60兆個もの細胞から構成されています。それぞれの細胞の中には細胞核があり、核の中には膨大な数の核酸(DNA)が連なって形成された23対(46本)の染色体が存在します。そして、この染色体の中には人体を構成する重要な成分である蛋白質の設計図(遺伝子)が記録されています(図1)。
ある設計図(遺伝子)に間違いがあると、その部分に対応する蛋白質が全く作られなかったり、あるいは、本来あるべき機能を持たない異常な蛋白質が作られるために病気になる場合があります。これが遺伝病と呼ばれるものです。
例えば、貧血を来す病気の一つとして鎌状赤血球症と呼ばれる遺伝病がありますが、この病気を持つ患者さんの赤血球に含まれるヘモグロビンは、わずかにアミノ酸1個が正常のものと異なるために赤血球が壊れやすくなり貧血となることが知られています。
一方、動脈硬化が原因となる高血圧・狭心症・心筋梗塞などは、単一の遺伝子の異常から生じるものではなく、親から受け継いだ遺伝的な背景(動脈硬化が進行しやすい体質)に加えて食生活など生活環境の影響を強く受ける多因子疾患と考えられます。
|
|
| 図1 遺伝子と蛋白質の関係 核内の染色体にある遺伝子(DNA)を鋳型としてメッセンジャーRNA(mRNA)が作られる(転写 Transcription)。 核外に出たmRNAはリボゾームと呼ばれる細胞内小器官に結合し、mRNAの配列情報に対応するアミノ酸が次々に結び付けられ蛋白質が作られる(翻訳 Translation) 。 |