| NO.5 |
血栓とその予防
(2−1)
北海道大学医学部 循環病態内科学 講師 藤井 聡
血栓と塞栓ができるまで
みなさんは寒い冬に自宅の水道が凍らないように様々な工夫をされているでしょう。また、排水がつまらないように、トイレットペーパー以外の紙はトイレで使用しない、定期的にパイプクリーナーを使うなど注意を払っているでしょう。同じように、体のすみずみまで血液を運ぶチューブである血管をつまらないように大事に維持管理することが必要です。
人間の血はもともと血管から外に出ると固まりやすく出来ています。これは人間が昔食料確保のために狩猟などでけがをしたときに、出血を防ぐためには大変重要なシステムでした(図1)。
しかし現在のライフスタイルでは狩猟などでけがをすることは少なくなり、逆に動脈硬化症や肥満、糖尿病などを背景として人間の血が固まりやすい傾向が血管をつまりやすくしています(図2)。
血液は通常さらさらで心臓の中や血管の中を流れており体内で固まる(凝固=ぎょうこ)する事はありません。しかし動脈硬化症のように血管が細く堅くなる病気になったり、血液中の脂質レベルが上昇したり肥満や糖尿病などになりますと血液の成分が変化して、血液が血管の中で固まって血の固まり(血栓=けっせん)を作りやすくなります。
いったん血栓が生じると血の流れるチューブである血管の血液の流れを途絶させます。その結果、脳血栓や心筋梗塞など重大な病気が起こります。
また血栓が、出来た場所を離れ血管内を流れて別の大切な臓器の血管や手足の血管に栓としてつまると(塞栓=そくせん)、臓器障害や手足の血流障害がおこります。
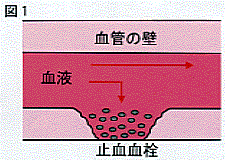 |
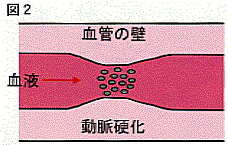 |
| 血管がやぶれたところで血が固まって栓を作り、出血を防ぎます。 | 動脈硬化などで細くなり表面の荒れた部位で血管内に血が固まって血の流れが止まってしまいます。(血栓) |
血栓の危険因子
血栓が出来やすくなるには血管の一番内側で血液に接している細胞(内皮細胞)が障害を受けたり、血液の流れが乱れたりよどんだり、血液の成分が変化する事で起こります。血管内皮が抜け落ちたりはがれたりする動脈硬化症では血栓が生じ易くなります。心臓を栄養する血管では必ずしも高度に狭くなっていない部分でコレステロールを覆っていた血管内膜が破れて血栓が出来て心筋梗塞が生じることが分かっています(図3)。
また動脈硬化で血管が狭くなるとその部位から先で血流が乱れ血栓が出来やすくなります。
下肢に静脈瘤があったり、妊娠、長期臥床で血液が停滞すると血栓が出来やすくなります。静脈の血栓ははがれて静脈を流れて肺に詰まることがあります。心房細動では心房内の血流停滞により血栓が生じやすくなります。心筋梗塞で心臓の壁の動きが低下したり、拡張型心筋症でび漫性に壁の動きが低下して血液が停滞すると左心室に血栓が生じ易くなります。
また高脂血症、インスリン抵抗性では血液成分が変化して血栓が出来やすくなり、血栓を溶かすシステムの働きが低下することが最近明らかとなりました。血栓が出来やすい主な病気を表1にまとめました。
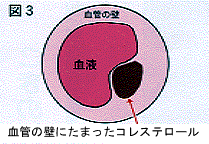 |
| 血管の広さはまだ保たれていますが、コレステロールを覆う内膜は薄く、破れると血栓ができて心筋梗塞になりやすい血管。 |
| 表1 血栓ができやすい主な病気 |
| * 心房細動 |
| * リウマチ性心疾患 |
| * 心筋梗塞 |
| * 拡張型心筋症 |
| * 人工弁置換術後 |
| * 糖尿病 |
| * 高脂血症 |
| * 静脈瘤 |
| * 妊娠 |
| * 長期臥床 |
| * 一部の血液疾患 |


