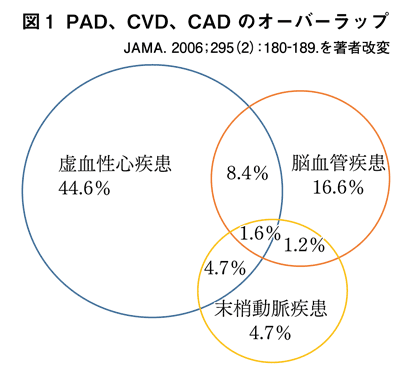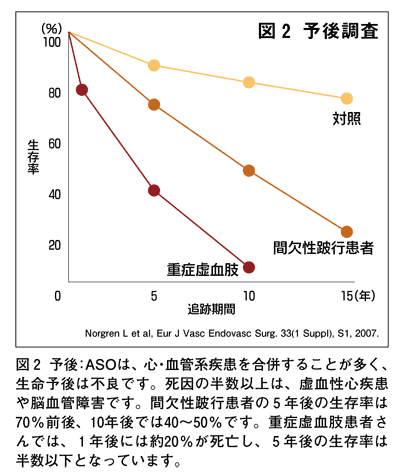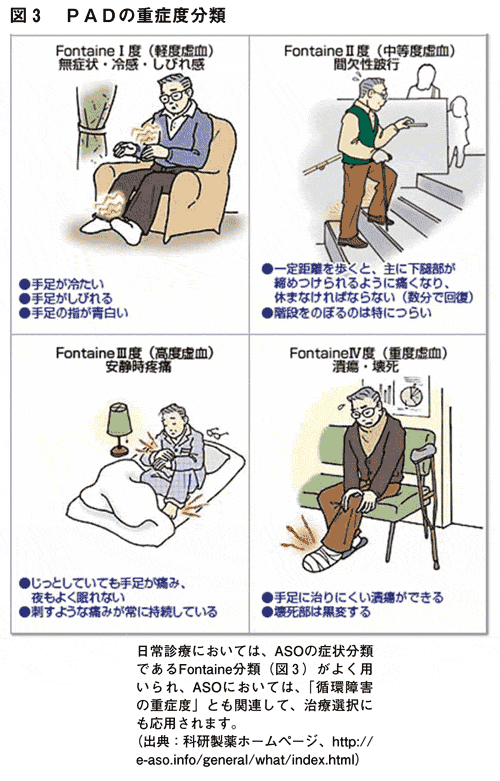|
|
NO.9 |
末梢動脈疾患について
(1/3)
旭川医科大学
循環呼吸医療再生フロンティア講座
特任准教授 住友 和弘氏
1 末梢動脈疾患(PAD)とは
我が国の65歳以上の高齢者人口の割合は、2013年10月1日現在25.1%となり、急速な高齢化が進んでいます。
食生活の欧米化や車社会を中心とした生活様式の変化により、メタボリックシンドロームの罹患率が増え疾病構造も高齢化を反映して変化しています。
特に動脈硬化性疾患が増え、虚血性心疾患の増加とともに末梢動脈疾患(PAD)も増加しています。
1970年前半以前は、閉塞性血栓血管炎(バージャー病)が多かったのですが、1970年半ばを境にPADが多くなっています。
以前は、下肢に限局した疾患として閉塞性動脈硬化症(ASO)と呼ばれることが多かったのですが、ASOのマネージメントに関する国際的なガイドラインであるTASC(Trans-Atlantic Inter-SocietyConsensus)の発表後、PADという呼び名が一般化しています。
本来PADは、下肢動脈以外の頸動脈、鎖骨下動脈、上肢動脈、腹部臓器への動脈など末梢動脈も含んだ概念ですが、日常で頻度の多い下肢閉塞性動脈硬化症と同義に使われることが多くなりました。
PADは、動脈硬化により動脈に狭窄や閉塞病変を起こす病気と考えると分かりやすく、PAD、脳梗塞、心筋梗塞は、異なる臓器で発生するものの動脈硬化の進展と破綻、そこでの血栓形成という共通のメカニズムが働いています。
そこで近年、PAD、脳血管疾患(CVD)、冠動脈疾患(CAD)を包括したアテローム血栓症(ATIS)という概念が提唱されています。PAD、CVD、CADを有する患者67,888名を対象にした前向き疫学研究REACH(Registry Reduction of Atherothrombosisfor Continued Health)Registryによると3疾患の間には高頻度にオーバーラップがあり(図1)、特にPAD患者では他の動脈硬化を有する割合が61.5%と高くなりました。1年間の予後調査(図2)では、動脈硬化病変数が多い人ほど心血管イベントの発生率が高く予後不良でした。