| NO.19 |
動脈硬化性疾患予防のための脂質異常症管理
― 動脈硬化性疾患予防ガイドライン2012年版より―
( 2/2 )
国立病院機構北海道医療センター循環器内科
竹中 孝さん
脂質異常症の診断基準(表2)
血中のLDL-C、トリグリセリド(TG、中性脂肪)が高いほど、またHDLコレステロール(HDL-C、いわゆる善玉コレステロール)が低いほど、冠動脈疾患が起こりやすくなります。
これらを脂質異常症と診断する基準は、表2のように設定されています。なお、以前は「高脂血症」という診断名が使われていましたが、HDL-Cは高い方が良いので、2007年版のガイドラインから「脂質異常症」に変更されました。
空腹時の総コレステロール(TC)、TG、HDL-Cを測定し、計算式からLDL-Cを算出します。また、他の危険因子があると、LDL-Cはより低いレベルでも治療が必要となるため、本ガイドラインでは120~139mg/dLを境界域高LDL-C血症としました。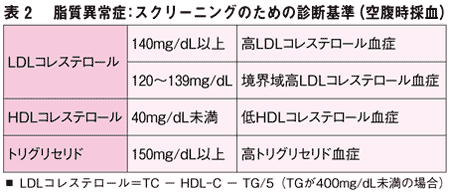
動脈硬化性疾患発症の絶対リスク評価
本ガイドラインの大きな変更点は、リスク評価に絶対リスクを導入したことです。
これまでは、「糖尿病があると冠動脈疾患は健常者の2~3倍発症しやすい」とか、「危険因子が3つ以上あると発症率が8倍高くなる」などと、健常者に対する相対リスクで評価していました。
これでは実際にどの程度危険なのか分りにくいと思いますが、絶対評価では「あなたが10年以内に冠動脈疾患で死亡する確率は2~5%です」というように、個人のリスクが具体的に表現されます。
一次予防対象者の絶対リスクは、日本人の疫学調査をもとにしたNIPPON DATA 80の冠動脈疾患絶対リスク評価チャート(図2に一部を示す)から割り出します。
動脈硬化性疾患に対してより悪影響を及ぼすのはLDL-Cですが、ここではデータがないためTCを用います。
例えば糖尿病のない55歳男性で、喫煙、収縮期血圧145mmHg、TC 250mg/dLであれば、絶対リスクは1以上2%未満(図2の○)となります。
※すこやかハート119号では上記文中で「非喫煙」と記載していましたが、「喫煙」の誤りでした。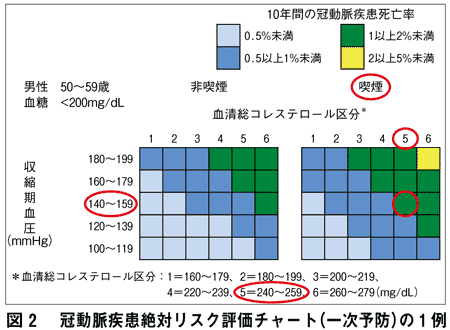
絶対リスクに基づく管理区分の決定
本ガイドラインでは、今後10年間の冠動脈疾患死亡率2%以上を高リスク群、0.5以上2.0%未満を中リスク群、0.5%未満を低リスク群と規定しました。脂質異常症と診断後、以下のように管理区分(リスク分類)を決定します。
①冠動脈疾患の既往があれば、その再発予防のため最も厳しい治療目標が設定されます(二次予防)。
②一次予防では糖尿病、慢性腎臓病、脳梗塞、末梢動脈疾患のいずれかがあれば、管理区分Ⅲ(高リスク)となります。なければ③に進みます。
③冠動脈疾患絶対リスク評価チャートから10年間の冠動脈疾患死亡率を求め、管理区分Ⅰ(低リスク)、Ⅱ(中リスク)、Ⅲ(高リスク)に分類します。
④管理区分ⅠかⅡの場合は、NIPPON DATA 80に含まれない追加リスクを確認します。低HDL-C血症、早発性冠動脈疾患の家族歴、耐糖能異常(いわゆる糖尿病予備軍)のいずれかがある場合、一段階上の管理区分に変更します。脂質異常症の管理目標値
リスク別の管理目標値を表3に示します。目標達成の基本はあくまでも生活習慣の改善です。一次予防ではまず3~6カ月間は生活習慣を改善した後でお薬の開始を考え、二次予防では生活習慣改善とともに薬物療法を考慮します。
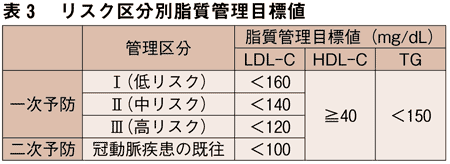
脂質異常症の治療

以下の生活習慣の改善が、動脈硬化性疾患予防の基本です。
①禁煙し、たとえ短時間でも受動喫煙を回避する。
②食べ過ぎない、標準体重を維持する。
③肉の脂身・乳製品・卵黄を少な目にし、魚類・大豆製品を多く摂る。
④野菜・果物・未精製穀類(玄米や大麦など)・海藻を多く摂る。
⑤塩分制限(6g/日未満)
⑥アルコールの過剰摂取を控える(日本酒なら1合、ビールなら1本、ワインならグラス2杯まで)。
⑦有酸素運動(速歩やゆっくりしたジョギングなど)を1日30分以上、週3回以上(できれば毎日)行う。今日では非常に良く効くお薬があり、実際に冠動脈疾患発症予防効果が証明されていますが、副作用が全くない訳ではありません。
上記のような生活習慣改善が第一です。ただし、高リスク群や二次予防の場合は、早くからLDL-Cを下げるお薬を併用して管理目標値を達成することが重要です。


