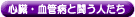| NO.7 |
 |
第2回伊藤記念研究助成を受けた
北海道大学 医療技術短期大学部
衛生技術学科
助教授 三神 大世
<第2回伊藤記念研究助成の対象となった先生のご研究を教えてください>
私の専門は超音波を使って心臓の動きをみる心エコー法(注1)という診断法です。私たちは、これを肥大型心筋症(注2)という遺伝性のある病気の家族検診に用いて、早期発見に努めてきました。しかし、どこまでが正常でどこから異常かという線引きは難しく、悩むこともしばしばでした。
そこで、患者さんの血液中のリンパ球を用いた遺伝子解析の結果と心エコー検診の画像とを照らし合わせ、その成果を、心エコー検診による早期診断に結び付けようとする研究を行い、これに対して伊藤記念研究助成を頂きました。
助成を励みに、欧米には見られないタイプの遺伝子異常や、この病気の初期病変の心エコー所見などについて、大いに知見を得ることができ、その後の実地臨床にも役立たせることができました。
<先生が現在進めている研究の内容を教えてください>
まず、心エコー法の一種であるカラーMモードドプラ法についてお話します。私は以前、心不全の患者さんにこの方法で特異な所見が得られることを発表していましたが、その後、北大循環器内科・北畠顕教授のアドバイスを得て、左室の広がりが悪いためにおきる心不全(注3)の診断法として大変役立つことを明らかにすることができました。現在、この方法のいろいろな心臓病への応用に取り組んでいるところです。
3次元心エコー法の研究にも取り組んできました。1次元から2次元へと進化して爆発的に普及した心エコー法ですが、その3次元化がどんなメリットをもたらすか、あるいはコンピューターネットワークを用いた特殊な画像処理法の研究などを進めています。
今後、遺伝子レベルでの基礎的研究が循環器病研究の進歩の原動力となるでしょうが、これに用いる小動物の心臓を検査する研究にも取り組んでいます。
<21世紀は目前ですが、21世紀になると循環器疾患の診断・治療はどのようになるとお考えですか>
多くの先生方がお考えの通り、遺伝子工学を中心に据えた心臓病の原因解明や治療法の開発が大いに進むと考えます。例えば、動脈硬化の危険因子と各遺伝子との関係がより明確になり、遺伝的背景に基づく最適な予防が可能になるのではないでしょうか。
画像診断面では、心エコー法やMRIで、冠動脈やその微小循環の非侵襲的画像化が進むと思います。血管内エコー像の分析からは、心筋梗塞をもたらす冠動脈の粥腫(じゅくしゅ)破裂の予測や、その予防法の開発が進むものと期待しています。
また、私たちがいま力を入れている心臓の拡張障害の研究が、心不全のより合理的な治療の確立に結び付くことを念願しています。
<ご自身のこれからの研究の夢を教えて下さい>
ひとことでいえば、基礎的研究と臨床現場との橋渡しとなるような研究でしょうか。分子レベル、遺伝子レベルでの研究の有効性は確かですが、その半面、実地医学との乖離が進むことをおそれます。
先進的な基礎的研究成果を実地に生かすための臨床研究、あるいは、臨床的な手法とノーハウを実験的研究に生かすような立場から研究を続けていければと思います。