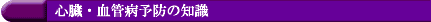 |
NO.13
|
老化と心臓・血管病−健康長寿実現のために−
札幌医科大学医学部内科学第二講座 講師
丹野 雅也さん
はじめに
世界最長寿である日本人の平均寿命は2010年には男性79.6歳、女性86.4歳となりました。1880年(明治13年)には平均寿命は男性36歳、女性38歳でしたので、過去130年間で飛躍的に伸びたことになります。このようにヒトが「長寿」となったのはごく最近のことであり、誕生以来の数十万年間、人類は若年期を何とか生き残るために進化してきました。よって私達の遺伝子は老化による病気に対抗する進化は遂げておらず、老化と戦うためには人為的な工夫に頼らざるを得ません。
高齢者は老化に伴う体機能の低下のため、いったん病気にかかると治りにくく、また多くの病気を併せもつという特徴があります。
しかし「寝たきりにならずに元気で自立した状態で長生き(健康長寿)」したいと願うのが人の常ですね。本稿では老化のしくみと老化への対抗策、つまり「アンチエイジング」について特に心臓、血管に焦点をあて概説します。
血管の老化
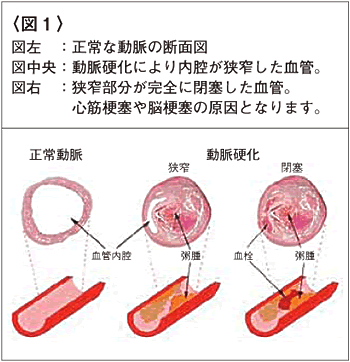
19世紀の内科医William Oslerが「人は血管とともに老いる」の名言を残したように、血管の老化は全身の老化の根本的な原因となります。血管の内側には動脈硬化抑制作用をもつ血管内皮細胞という一層の細胞があります。加齢とともに血管内皮細胞機能が衰えると動脈硬化が進み、血管は硬くなり内腔は狭くなります図1。加齢は動脈硬化の最大の危険因子であり、年齢とともに進行する動脈硬化を完全に停止させることは残念ながらできませんが後述の他の危険因子を是正することによりその進行を遅らせることはできます。
つまり「喫煙」「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」「肥満」「男性」は動脈硬化の進展を加速し、心筋梗塞や脳梗塞など動脈硬化関連疾患のリスクを高めます。
実際に糖尿病患者や喫煙者は、非糖尿病患者、非喫煙者と比べて平均寿命が約10年短くなるというデータがあります。逆に禁煙、糖尿病の予防だけでも血管の老化を10年間遅らせることができると解釈できるかもしれません。狭心症や心筋梗塞、脳梗塞は生命だけではなく社会的自立、活動にも大きく影響します。健康長寿を目指すためには生活習慣を見直しこれらの病気を是非とも予防したいものです。
さて、危険因子に「男性」と述べましたが、血管内皮細胞の機能は男性では40歳頃から低下する(血管老化)に対して女性では50歳以降まで維持されることが知られています。この差は、女性ホルモンであるエストロゲンの血管保護作用に起因しており、女性も閉経後は血管の老化が進み心筋梗塞、脳梗塞などの病気が増加する傾向にあります。
血管の老化と同じように平均寿命も女性の方が約7年長くなっており、血管の老化が寿命を大きく左右していることが伺われます。
心臓の老化
加齢とともに心筋細胞の数は少しずつ減少します。喪失された心筋細胞は線維細胞で置き換わり、心臓は徐々に柔軟さを失い硬くなります。
また、残存する個々の心筋細胞自体の拡張、収縮の機能も加齢とともに低下します。こうなると全身を巡って戻ってきた血液を心臓がポンプとして汲み上げる機能(拡張能)と全身へ拍出する機能(収縮能)のいずれもが低下します。
また、心臓の規則正しい拍動のリズムを司る機能も加齢とともに徐々に衰え、不整脈も増加し突然死の原因となることもあります。こういった心臓自体の老化に前述の血管の老化により起こる狭心症や心筋梗塞が併存すると心臓はさらなるダメージを受けます。このようにして起こる心臓の機能低下により発症するのが心不全で様々な症状が出現します図2。
心不全は加齢とともに増加する疾患であり、心臓老化の一形態といえます。しかも一度心不全を発症すると入退院を繰り返さざるを得ず、本人のみならず家族へも多大な負担を強いることになってしまいます。心不全に対する治療は確実に進歩してきておりますが、現在の最新の治療を用いても重症の心不全は胃癌や肺癌と同じくらい予後の悪い病気です図3。
心筋細胞再生による治療の研究も行われており将来は新しい治療となるかもしれませんが、残念ながら現時点では衰えてしまった心臓の機能を回復させるまでには至っていません。さて、それでは心臓、血管の老化と心不全の発症進展を何とか予防するいい方法はないでしょうか?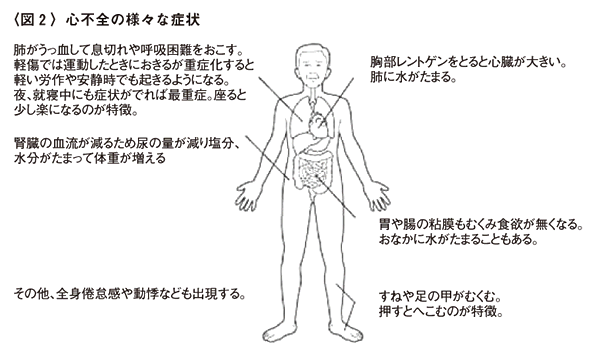
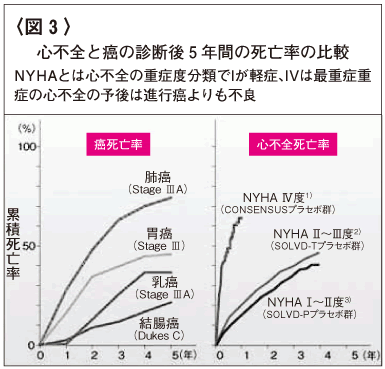
カロリー制限による心臓血管アンチエイジング
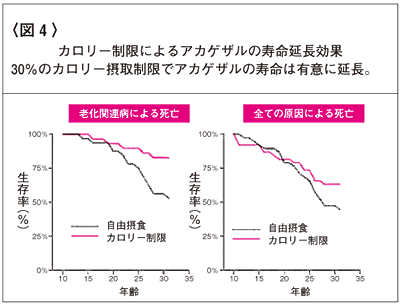
昔から「腹八分目に医者いらず」などと過食を避けることが健康に良いことはいわれてきました。近年、ライフスタイルの変化に伴い過食や肥満を基盤とするメタボリックシンドロームやそれに伴う心臓血管病が増加の一途をたどっている現実を考えると「腹八分目」の重要性は皆さん実感できることと思います。
最近になって科学的にも「腹八分目」の効果が証明されました。2009年Science誌に発表された論文ではヒトと同じ霊長類のサルにおいて、20年間カロリーを3割制限(つまり腹七分目)し、自由に餌を食べたサルと比較しました。すると生存率はカロリー制限した場合が80%、カロリー制限をしない場合が50%となり、カロリー制限により寿命が明らかに延長しました図4。特にカロリー制限をしたサルでは心臓、血管の病気が減少しており、カロリー制限が心臓、血管の老化を遅らせ寿命を延長させることを証明した衝撃的な結果です。
カロリー制限が心臓老化を遅らせることはヒトでも証明されています。米国ワシントン大学の研究では1日1400〜2000Kcalまたは2000〜3000Kcalの栄養バランスのとれた食事をした成人を約6年間観察しました。1400Kcal〜2000Kcalは我々日本人よりも体の大きなアメリカ人にとってはかなりのカロリー制限です。カロリー制限をした人たちは、カロリー制限をしなかった人と比較して心臓の機能が約15歳若かったという結果が得られました。
しかし困ったことに実際にカロリー制限を実行するためには相当の自制心が必要です。そこでカロリー制限と同じような効果を得るための薬の開発が研究されています。
これまでの研究でカロリー制限による長寿にはsirtuin(サーチュイン)という蛋白が大きな役割を果たすことがわかっています。薬でサーチュインを活性化できればアンチエイジングにつながり、カロリー制限をしなくても長生きできるかもしれません。実際、何種類かのサーチュイン活性化薬が開発され糖尿病による血管障害などに対して臨床試験が進行中で、結果が待たれるところです。
サーチュイン活性化作用があるレスベラトロールという成分は赤ワインに多く豊富に含まれていて、フレンチ・パラドックス(フランス人は高脂肪食の摂取が多いにもかかわらず心臓血管病による死亡が少ない。)の理由はフランス人のワイン消費量が多いから、という説もあります。
カロリー制限による老化防止に焦点を当ててお話ししましたが、心臓血管の老化の予防には他にも1日30分〜1時間程度の適度な有酸素運動(散歩、ジョギングなど)ももちろん有効ですし、禁煙は非常に大切です。「腹八分目」「適度な運動」「禁煙」で、是非、健康長寿を目指してください。

