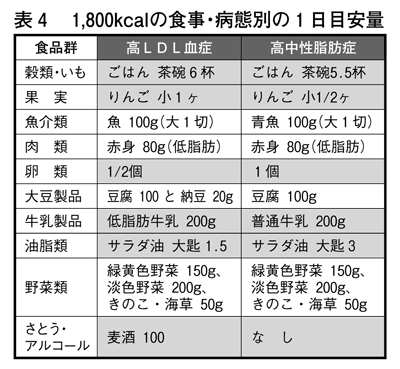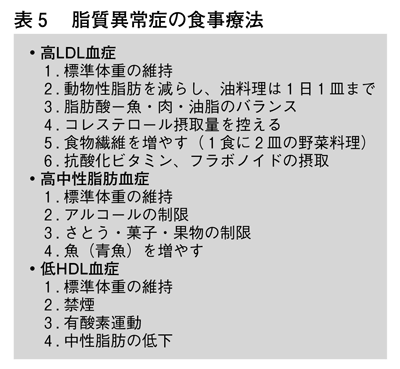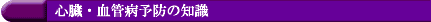 |
NO.12
|
心臓血管病と食事療法 - 脂質異常症
天使大学 看護栄養学部栄養学科教授
伊藤 和枝さん
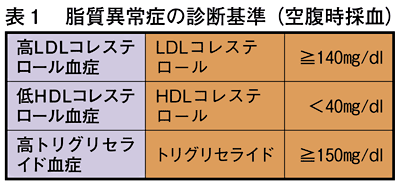
動脈硬化性疾患、特に心筋梗塞を中心とした心臓血管病、脳梗塞を中心とした脳血管疾患のいずれの予防・治療にも脂質異常症の治療が禁煙と共に重要であることが認知されています。日本動脈硬化学会では、「動脈硬化性疾患予防ガイドライン2007」で、動脈硬化の危険因子である高脂血症に加え、低HDLコレステロール血症がむしろ危険因子であることから、高LDLコレステロール血症、高トリグリセライド(中性脂肪)血症、低HDL血症を脂質異常症と改変しました。脂質異常症の診断其準は表1(及び2頁掲載の「リスク別脂質管理目標値」参照)に示すとおりで、LDLコレステロールの治療目標値は個人のリスクにより異なり、LDLコレステロールは次式で求めます。
LDLコレステロール=総コレステロール-HDLコレステロール-(中性脂肪÷5)
血液中の脂肪の主な物は、コレステロールと中性脂肪です。脂肪は水に溶けないため、血液中では周囲を水と脂肪の両方になじみ易くするためにたん白質で覆われたリポ蛋白として存在しています。コレステロールには、主にたん白質の割合が少なくコレステロールの割合の多いLDLコレステロール(LDL)と、たん白質の割合が多くコレステロールの割合の少ないHDLコレステロール(HDL)があります。LDLは脂肪を全身の組織に運び、血管壁に蓄積して動脈硬化を進めます。一方、HDLは血管壁に蓄積した過剰なコレステロールを取り出し、肝臓へ取り込み動脈硬化を抑制します。LDLが180㎎/dl以上の場合、100mg/dl未満に比べ心臓血管病の発症リスクは約3.8倍に増加すると言われています。
血液中のコレステロールの約80%は肝臓で作られ約20%は直接食事からとった物です。過剰なエネルギーは肝臓で中性脂肪を合成しますが、食事の量が多くなくても、脂肪の量が多ければ血液中の脂肪が増え高中性脂肪血症となります。また、1回の食事の脂肪量が極端に多いと食後高脂血症を起こします。中性脂肪は、食後4~6時間まで上昇し、レムナント(RLP-C)となり、長時間にわたり代謝されずに血中に淀みます。さらに小粒子LDLとなって血管内皮に浸潤し易くなり、プラークを作るため超悪玉コレステロールと言われています。私達の研究でも脂肪量が多いほど、また飽和脂肪酸が多いほど食後4時間のRLP-Cが高くなることを認めました。
近年多く見られる脂質異常症による動脈硬化は、加齢によるものとは異なり、血中の脂肪が多いためLDLが酸化変性し短期間に血管内膜に脂質プラークや血栓が作られます。血栓は血管を塞ぎ心筋梗塞などが突然起こります。糖尿病・高血圧・肥満などを合併しているとプラークの形成は加速度的に進みます。最近の心筋梗塞の増加は、食事の欧米化即ち高脂肪食が原因と考えられています。
食事療法のポイントは
1 エネルギーの適正摂取
余分のエネルギーは血液中の脂肪を増やします。エネルギー摂取量を減らすことで、内臓脂肪(腹囲)が減りインスリンの働きが改善し中性脂肪が減りHDLが増加します。体重が1kg減ると、腹囲は1cm減り、LDLが10㎎/dl下がるという報告もあります。
2 脂肪の量と質に注意する
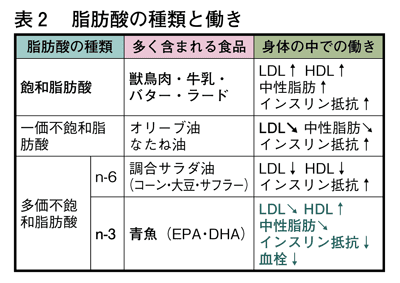
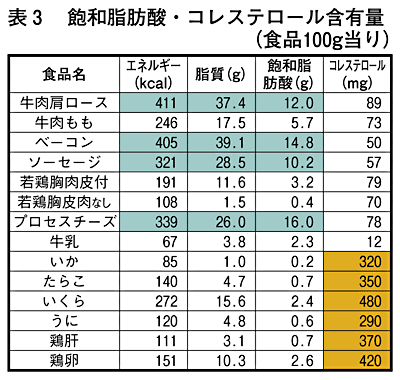
私達が摂取する脂肪は、穀類・豆・種実などから25%、肉・卵・乳類・魚介類から47%と見えない脂肪が多く、油脂などの見える脂肪は28%程度です。脂肪の大半を占める脂肪酸により、身体の中での働きが異なります。獣鳥肉類、乳製品に多く含まれる飽和脂肪酸はLDLの肝臓への取り込みを阻害して血中のLDLを高くします。飽和脂肪酸とコレステロール含量の少ない食品を摂取しましょう。挽き肉、鶏皮、レバーなどの摂取は要注意です。調理に使う油は1日10~20gまで、油料理は1日1皿程度です。飽和脂肪酸の多いバター・ラードは血中LDLを高くし、多価不飽和脂肪酸の多い大豆油・菜種油などに多く含まれるリノール酸はLDLを低下させます。一価不飽和脂肪酸の多いオリーブ油にかたよらず、バランスよく取りましょう。ショートニングやマーガリンに多く含まれるトランス脂肪酸は、市販の菓子・パンに多く含まれLDLを高くします。(表2・表3)
3 肉より魚や大豆を
魚に多く含まれる多価不飽和脂肪酸はLDLを低下させ、特に青魚のn-3系脂肪酸は中性脂肪の上昇を抑えます。肉より魚・大豆を取るようにします。
4 食物繊維の摂取量を増やす
食物繊維はコレステロールの吸収を阻害し、LDLを低下させます。緑色野菜・きのこ・海草・大豆・雑穀などの摂取を心がけましょう。(前頁図1)
5 アルコールは中性脂肪を高くします
アルコールは肝臓で中性脂肪の合成を促進します。中性脂肪の高い人はアルコールの制限が大切です。適量のアルコール摂取は、HDLを増やして心筋梗塞の発症リスクを抑えますが、過剰摂取は中性脂肪を高くします。男性の適量は1日25g程度で、日本酒では150ml、ビールでは500ml、焼酎では60mlに当たります。女性は1/2量です。
6 蔗糖(さとう)や果糖を控える
糖質の過剰摂取は肝臓で中性脂肪を合成し、血中の中性脂肪が高くなります。清涼飲料水、菓子、果物は、アルコールと共に取り過ぎに注意が必要です。
7 抗酸化ビタミンを摂取する
金属は酸化するとさびてもろくなり、人間も同様に、体内で酸化が起こるとさまざまな悪影響が出てきます。動脈硬化も、血液中のLDLが酸化され変性した酸化LDLが血管壁に沈着して起こります。ビタミンC、ビタミンE、ベータカロチンが酸化を阻止してくれるビタミンです。ビタミンCやベータカロチンは野菜や果物に多く含まれています。ビタミンCは水溶性で、大量にとっても余分は尿に排泄されるため、毎日の摂取が大切です。(前頁図1)
8 禁煙
喫煙はLDLの酸化・変性を進め、動脈硬化を促進するだけでなく、血管を収縮させるため心血管病には大敵です。
症例別の食事と適正な脂肪酸摂取(表4・表5)
①高LDL-C血症(高コレステロール血症)の場合
・脂質摂取の制限強化:脂肪由来のエネルギーを総エネルギーの20%に。
・コレステロール摂取量の制限:1日200㎎まで。
・飽和脂肪酸:一価不飽和脂肪酸:多価不飽和脂肪酸を3:4:3②中性脂肪が高い状態が続く場合
・アルコールは禁止
・炭水化物の制限:主食や芋などの炭水化物の摂取を総エネルギーの50%まで。
・単純糖質の制限:1日80kcalまでの果物を除き、さとう・菓子・清涼飲料の制限③低HDL血症の場合
・有酸素運動
・禁煙
・中性脂肪の低下④高コレステロール血症と高トリグリセライド血症が共に持続する場合
・①と②で示した食事療法を併用する⑤高カイロミクロン血症
・脂肪摂取量を15%以下に制限