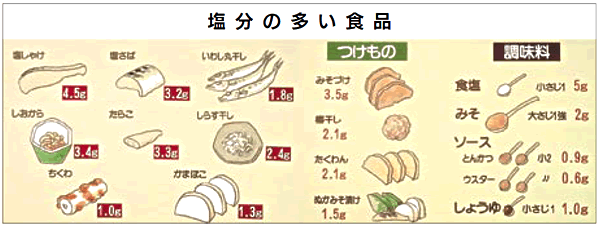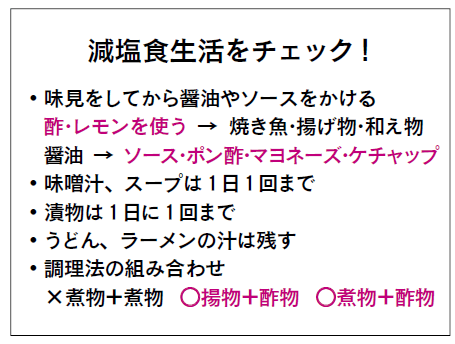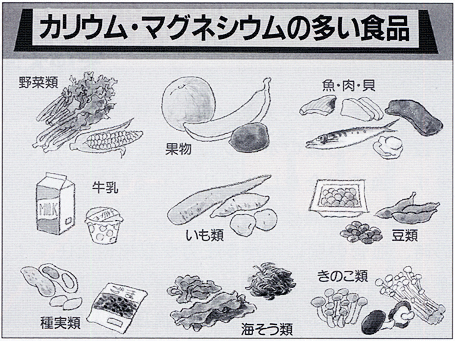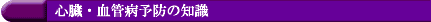 |
NO.10
|
心臓血管病と食事療法 - 高血圧
天使大学 看護栄養学部栄養学科教授
伊藤 和枝さん
身体のすみずみまで酸素と栄養素を届けている血液は、心臓のポンプによって調整されています。血液が全身に送り出される時に心臓は強く収縮し、血液は大動脈に押し出されます。この時、血管の壁にかかる圧力が収縮期血圧です。全身をめぐってきた血液が拡張した心臓に流れ込んでくる時の血圧が拡張期血圧で、血管の弾力で決まります。血圧が高いというだけで何ら影響を及ぼさなければ問題はないのですが、血圧の高い状態が続くと血管が障害され、脳・心臓・腎臓などに障害を起こし、脳卒中、高血圧性心臓病、腎不全を促進します。高血圧は血管の内膜を傷つけ、そこに血液中の脂質(LDLコレステロール)が沈着して血管壁を厚くし、動脈硬化を引き起こします。さらにはプラーク(粥腫)を作って血管を塞ぎ、心血管病(心筋梗塞・狭心症)や脳血管障害(脳梗塞・脳出血)を引き起します。血圧を常に正常範囲に保っておくことが心血管病の予防・治療に大変重要なのです。
高血圧の発症には、遺伝的因子と環境因子が関っており、中でも、肥満、食塩やアルコールの過剰摂取、ストレス、運動不足など、環境因子による生活習慣が大きく影響しています。そのため、生活習慣を修正することが、軽度の血圧低下をもたらすだけでなく、降圧薬服用者では薬の効果も現れやすく、薬を減らすことも可能になります。生活習慣の修正は高血圧だけでなく、肥満、糖尿病、脂質異常症、痛風にも効果的で、特に食生活の果たす役割は大きいのです。
1. 生活習慣の修正には、食塩摂取量を1日6g未満に
塩分の取り過ぎは、高血圧を招く最大の原因です。塩分(ナトリウム)は水分を取り込むため、心臓から押し出される血液(心拍出量)を増加させ、血圧が高くなります。また、ナトリウムは血管の収縮を強めて血圧を上昇させます。私達が生きるために必要な食塩量は1日1.5g程度ですが、平成19年度国民健康・栄養調査の平均食塩摂取量は50代・60代の男性1日12.7g、女性は10.8gでした。高血圧治療ガイドライン2009では、第1に食塩1日6g未満を推奨しています。1日6g未満は、食品中の塩分も含めた数値です。従って調味料として使える塩分量は約4gで食塩なら小さじ1杯弱、しょうゆに換算すれば20㏄(大さじ1杯強)に相当します。現在、食塩摂取量の44%を漬物、ハム・ちくわ・即席めん・塩鮭などの加工品から、56%を調味料から摂取しています。減塩には加工品を減らし、調理法を変えることです。汁物を控え、具沢山にして吸汁を少なくします。麺料理も1食で食塩5g含んでいます。煮物も甘みに隠された塩分が多いので注意します。揚げ物、蒸し物、和え物、酢の物は低塩で美味しい料理です。調理法で塩分は異なるので、料理の組み合わせに注意します。調理には①新鮮な食材を用い、②味は表面に集中させる。すべて薄味にするのではなく、てんぷらのようにつけ汁で舌にしょうゆ味を直接感じさせる。③レモンやカボス、酢などを食卓に置き、揚げ物、焼き物、煮物にも使いましょう。④辛子・わさび・生姜・ゴマ・ロリエなどの香辛料やケチャップ・ソースなど低塩調味料を上手に使い、かけしょうゆは出汁で割って使います。
2. 野菜でカリウム・マグネシウム・食物繊維の摂取を
野菜や果物に多く含まれているカリウムは、ナトリウムの尿中への排泄を促進し、さらに血管を拡張させて血圧を下げる働きがあります。食事摂取基準(健康人)では、カリウム3.5gが推奨されていますが、平均カリウム摂取量は1日2.4gと不足気味です。しかし、腎臓の悪い人はカリウムの摂取は控えなければなりません。
カリウムは、緑色野菜・果物・豆・きのこ・海藻・肉・魚・牛乳などに多く含まれていますが、特に1日350gの野菜、すなわち1食に2皿の野菜料理を目標にしましょう。果物の取り過ぎは血糖を高めるので注意します。緑色野菜や豆、海藻には、カリウムだけでなくマグネシウムも多く含まれています。マグネシウムは、血管の収縮を抑えて血圧を下げ、マグネシウム欠乏では突然死も報告されています。さらに脂質代謝を改善する働きがあります。カリウムはインスリンを増やして中性脂肪を低下させ、マグネシウムはLCATを増やし善玉のHDLを介してLDLを下げることを私達はヒトの研究で明らかにしました。野菜には食物繊維も多く、血糖やLDLコレステロールを下げて相乗的に動脈硬化を予防し血圧管理にも有効です。
3. 魚の摂取推進とコレステロール・飽和脂肪の制限
高血圧は血管壁に傷をつけて動脈硬化を促進しますが、細胞に回復力があれば、多少の傷は修復できます。そのためには、良質のたんぱく質をバランスよく取る必要があります。コレステロールや飽和脂肪(獣鳥肉脂肪)の摂取は動脈硬化を進め、魚はEPAやDHAを含み動脈硬化を抑えます。獣鳥肉より魚・大豆を中心に摂取することが心血管病に有効です。
4.適正体重の維持
体重だけでなく腹囲(内臓脂肪)の減量が重要です。内臓脂肪には食事の量だけでなく、脂肪が関与しています。飽和脂肪の多い獣鳥肉、油脂を控えます。遅い時間の夕食、夕食での過食には特に注意が必要です。余分のエネルギーは脂肪に変わります。
5.運動
中等度の有酸素運動を1日30分行うことは血圧低下に繋がります。毎日の歩行を無理なく継続したいものです。
6.節酒
長期にわたる飲酒は血圧上昇に繋がるだけでなく、大量の飲酒は高血圧に加えて、中性脂肪を増やし脂質異常症が起こります。一方、少量の飲酒は降圧がえられます。男性ではエタノール換算で20〜30mlまで(日本酒1合、ビール中ビン1本;500ml、焼酎では100mlに相当)、女性は男性の半分までにします。
7.禁煙
煙草は、血管を収縮させて血圧を上げるだけでなく、LDLコレステロールを酸化して動脈硬化を促進し、心血管病(虚血性心疾患)・脳血管障害の強力な危険因子です。
★
減塩・減量・運動・節酒に加え、さらに野菜・魚の摂取、飽和脂肪(動物性脂肪)・コレステロールの摂取制限などの複合的な修正がより効果的です。