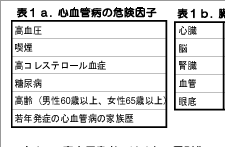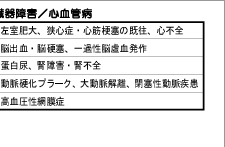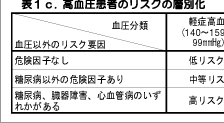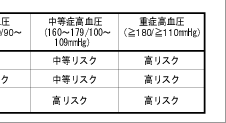| NO.1 |
崅寣埑
乮侾亅侾乯
嶥杫堛壢戝妛堛妛晹戞擇撪壢丂懞忋丂塸擵
帺妎徢忬側偔曻抲偝傟偑偪乛姵幰悢偼栺3,300枩恖
崌暪徢杊巭偵椡揰乛擼懖拞傗嫊寣惈怱幘姵
崅寣埑偼側偤帯椕偟側偗傟偽偄偗側偄偐丠
丂変偑崙偺崅寣埑姵幰偼3,300枩恖偲傕偄傢傟丄幘姵偺拞偱傕偭偲傕懡偄昦婥偲偝傟偰偄傑偡丅崅寣埑偼丄帺妎徢忬偑側偄偺偑摿挜偱丄偦偺偨傔彮乆寣埑偑崅偔偰傕曻抲偝傟傞偙偲偑懡偄昦婥偱偡丅偟偐偟丄崅寣埑傪曻抲偟偰偍偔偲抦傜偸娫偵擼丄怱憻丄恡憻側偳偵忈奞偑婲偙傝傗偡偔側傝丄惗柦梊屻偵廳戝側塭嬁傪棃偨偟偆傞偙偲偑抦傜傟偰偄傑偡丅偙偺偨傔丄帺妎徢忬偑側偔偲傕廫暘偵寣埑傪娗棟偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅杮峞偱偼丄擔杮崅寣埑妛夛偐傜弌偝傟偨崅寣埑帯椕僈僀僪儔僀儞 (JSH2000) 傪拞怱偵丄擔忢恌椕偱偳偺傛偆側崅寣埑帯椕偑峴傢傟偰偄傞偐奣愢偟傑偡丅
JSH2000偲偼
崅寣埑傪巜揈偝傟偨傜偡偖偵栻傪弌偝傟傞偺偱偟傚偆偐丠丂1990擭偵岤惗徣偲擔杮堛巘夛偐傜乽崅寣埑恌椕偺偰傃偒乿偑嶌惉偝傟丄椪彴揑偵嶲峫偵偝傟偰偄傑偟偨丅傑偨丄悢擭偛偲偵夵掶偝傟偰偒偨暷崙崅寣埑崌摨埾堳夛偵傛傞僈僀僪儔僀儞乽JNC-VI乿(1997擭)偲悽奅曐寬婡娭乛崙嵺崅寣埑妛夛偵傛傞僈僀僪儔僀儞乽1999 WHO/ISH乿 (1999擭) 傕変偑崙偱峀偔棙梡偝傟偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄墷暷偲変偑崙偱偼恖庬嵎丄惗妶條幃偺堘偄傗崅寣埑惈崌暪徢偺庬椶傗昿搙偑堎側傞乮擔杮恖偼敀恖傛傝擼懖拞偼3乣4攞懡偔丄嫊寣惈怱幘姵偼3暘偺1偵偡偓側偄乯偙偲偐傜丄変偑崙撈帺偺僈僀僪儔僀儞偑昁梫偲偝傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅2000擭6寧偵擔杮崅寣埑妛夛偐傜乽崅寣埑帯椕僈僀僪儔僀儞2000擭斉乿(JSH 2000)偑敪峴偝傟傑偟偨丅
丂崅寣埑偵偼尨場偺傢偐偭偰偄傞傕偺乮俀師惈崅寣埑乯偲尨場偺暘偐傜側偄傕偺乮杮懺惈崅寣埑乯偺俀庬椶偁傝傑偡丅擔杮恖偺崅寣埑偺栺95%埲忋偼乽杮懺惈崅寣埑乿偑愯傔偰偄傑偡丅JSH 2000偱帵偡崅寣埑傕乽杮懺惈崅寣埑乿傪庡偨傞懳徾偲偟偰庢傝埖傢傟偰偍傝傑偡丅
丂JSH 2000偱偼崅寣埑偺婎弨傪丄廂弅婜寣埑傪140mmHg丄傑偨偼奼挘婜寣埑傪90 mmHg埲忋偲愝掕偟偰偄傑偡丅偦偟偰丄寣埑偺僐儞僩儘乕儖偵偮偄偰丄庒擭丒拞擭幰偍傛傃摐擜昦崌暪偺崅寣埑姵幰偵懳偟偰偺崀埑栚昗抣偼130乛85 mmHg枹枮偵愝掕偟偰偄傑偡丅傑偨丄崅楊幰偵偍偄偰偼丄婛偵廳梫憻婍傊偺弞娐忈奞偑擣傔傜傟傞偙偲偑懡偔丄栚昗抣偼140乣160 mmHg 埲壓乛90 mmHg 枹枮偲愝掕偟偰偍傝傑偡丅
丂崅寣埑偺帯椕偼扨偵寣埑傪掅壓偝偣傞偩偗偱側偔丄擼懖拞傗嫊寣惈怱幘姵側偳偺崅寣埑惈崌暪徢傪偄偐偵杊巭偡傞偐偑廳梫偱偡丅偦偺偨傔偵偼丄崅寣埑偺掱搙偲婋尟場巕偍傛傃崅寣埑偵婎偯偔憻婍忈奞傪峫椂偟偰崀埑栻傪奐巒偡傋偒偐偳偆偐傪敾抐偟傑偡丅傛偭偰丄崅寣埑傪巜揈偝傟偨姵幰偼丄寣埑應掕偺嵞専丄俀師惈崅寣埑偺娪暿偲偲傕偵昞侾倎丄侾倐偵帵偡婋尟場巕偺桳柍偺妋擣偲彅憻婍忈奞乛怱寣娗昦偺桳柍偵偮偄偰専嵏傪恑傔傑偡丅
丂嬶懱揑偵偼丄寣塼専嵏丄擜専嵏丄嫻晹儗儞僩僎儞幨恀傗怱揹恾丄怱僄僐乕丄娽掙専嵏側偳偲偄偭偨専嵏傪峴側偄傑偡丅偙傟傜偺専嵏偺寢壥傪傕偲偵丄昞侾們偵帵偝傟傞傛偆側姵幰偺儕僗僋偺憌暿壔傪峴側偄丄偦傟偵廬偭偰帯椕曽恓傪寛掕偟傑偡丅偡側傢偪丄掅儕僗僋孮偱偼惗妶廗姷偺廋惓傪庡梫側帯椕朄偲偟丄6儠寧屻偵寣埑偑140乛90 mmHg枹枮偵壓崀偟側偄応崌偼栻暔帯椕傪奐巒偟傑偡丅拞摍儕僗僋孮偱偼傑偢惗妶廗姷偺廋惓傪峴偄丄3儠寧屻偵寣埑偑140乛90 mmHg 枹枮偵壓崀偟側偄応崌偼崀埑栻椕朄傪奐巒偟傑偡丅崅儕僗僋孮偱偼惗妶廗姷偺廋惓偲崀埑栻椕朄傪摨帪偵峴偄傑偡丅
昞侾
惗妶廗姷偺廋惓
1. 怘墫惂尷7g/擔乮偙偺偆偪挷枴椏側偳偲偟偰揧壛偡傞怘墫偼4g/擔乯埲壓 2. 揔惓懱廳偺堐帩 丂 仏昗弨懱廳乮22 亊乵恎挿乮m乯乶亊 乵恎挿乮m乯乶乯偺亄20%傪挻偊側偄 3. 傾儖僐乕儖惂尷丗僄僞僲乕儖偱 丂 抝惈偼20乣30g/擔乮擔杮庰栺1崌乯埲壓
彈惈偼10乣20g/擔埲壓4. 僐儗僗僥儘乕儖傗朞榓帀朾巁偺愛庢傪峊偊傞 5. 塣摦椕朄乮桳巁慺塣摦乯 丂 仏怱寣娗昦偺側偄崅寣埑姵幰偑懳徾 6. 嬛墝
昞俀丏惗妶廗姷偺廋惍崁栚丂崅寣埑帯椕偼惗妶廗姷偺廋惓偑婎杮偱偁傝丄JSH 2000偱傕擔杮恖偺惗妶忬嫷傪廫暘偵峫椂偟偰丄昞俀偵帵偡惗妶廗姷偺廋惓崁栚傪採帵偟偰偄傑偡丅
丂擔杮恖偺怘惗妶傕墷暷壔偵敽偄丄怘墫愛庢検偼13g乛擔慜屻偵憹壛偟偰偄傑偡偑丄崅寣埑偵偼墫暘偺愛傝偡偓偑戝揋偱偡丅偦偺偨傔丄崅寣埑姵幰偱偼侾擔偺墫暘愛庢検偼俈g埲壓傪栚昗偲偟偰偄傑偡丅旍枮偺掱搙偑崅搙偵側傞傎偳怱寣娗昦偵傛傞巰朣棪傕憹壛偡傞偲偄傢傟偰偍傝丄懱廳傪昗弨懱廳偺僾儔僗20亾埲撪偵曐帩偡傞廳梫惈偑嫮挷偝傟偰偄傑偡丅
丂塣摦椕朄偼丄怱攺悢110乣120夞乛暘掱搙偺寉傔偺塣摦傪1帪娫掱搙丄廡2乣3夞懕偗傞偲岠壥揑偲尵傢傟偰偄傑偡丅媔墝偼丄擼懖拞媦傃怱嬝峓嵡偺婋尟惈傪偄偢傟傕栺3攞偵偟傑偡丅偙偺傛偆側惗妶廗姷偺廋惓偼丄崀埑栻偺搳梌偑奐巒偝傟傞慜偵峴側偆偩偗偱側偔丄崀埑椕朄偑奐巒偝傟偰偐傜傕宲懕偟偰偄偔昁梫偑偁傝傑偡丅
栻暔椕朄
丂
丂惗妶廗姷偺廋惓傪峴側偭偰傕側偍140乛90 mmHg埲忋偺崅寣埑偑帩懕偡傞応崌丄偁傞偄偼丄180 mmHg埲忋乛110 mmHg埲忋偺崅寣埑傪擣傔傞傛偆側崅儕僗僋孮姵幰偱偼丄崀埑栻偺搳梌偑昁梫偵側傝傑偡丅
丂JSH2000偱偼丄僇儖僔僂儉(Ca)漢峈栻丄傾儞僕僆僥儞僔儞曄姺峺慺(ACE)慾奞栻丄傾儞僕僆僥儞僔儞嘦(俙嘦)庴梕懱漢峈栻丄棙擜栻丄兝幷抐栻偍傛傃兛幷抐栻偺6庬椶偺崀埑栻傪戞堦慖戰栻偲偟偰嫇偘丄偙傟傜偺偄偢傟偐傪奺姵幰偺昦懺偵崌傢偣偰巊梡偡傞傛偆悇彠偟偰偄傞(昞俁)丅傑偨丄掅梡検偐傜奐巒偟丄彊乆偵憹検偟丄媫懍偵寣埑傪掅壓偝偣傞偙偲偼旔偗傞傋偒偲偟偰偄傑偡丅
丂傑偨丄崀埑岠壥偑晄廫暘偩偐傜偲偄偭偰丄堦嵻傪忢梡検偺俀攞埲忋偺崅梡検傪梡偄傞偙偲偼旔偗偰丄憡忔丒憡壛嶌梡偑婜懸偱偒傞栻嵻傪暪梡搳梌偡傞偙偲傕悇彠偟偰偄傑偡丅
崀埑栻偺奐敪恑傒丄寣埑娗棟偼偟堈偔偼側偭偨偑乧
婎杮偼惗妶廗姷偺廋惓乛怘帠丒塣摦丒懱廳丒嬛墝
崌暪徢傪敽偭偨崅寣埑姵幰偺帯椕
丂嬤擭丄擔杮偺崅寣埑姵幰偱偼丄摐擜昦丄崅帀寣徢丄崅擜巁寣徢側偳偺戙幱忈奞傗丄擼寣娗忈奞丄嫊寣惈怱幘姵丄怱旍戝丄恡忈奞傗枛徑弞娐晄慡傪崌暪偡傞応崌偑懡偔丄偙傟傜偺崀埑帯椕偵傕昦懺偵墳偠偨怲廳側懳墳偲崀埑栻偺慖戰偑昁梫偲側傝傑偡丅椺偊偽丄摐擜昦傪崌暪偡傞崅寣埑偱偼丄摐擜昦傪埆壔偝偣偢丄摦柆峝壔偺恑揥傪梷惂偟丄偝傜偵摐擜昦惈恡忈奞偺敪徢傪梷偊傞偨傔偵丄俙俠俤慾奞栻丄俙嘦庴梕懱漢峈栻丄Ca漢峈栻偍傛傃兛幷抐栻偺巊梡偑悇彠偝傟傑偡丅偦偟偰丄偙傟傜偺崀埑栻偺扨撈搳梌傗暪梡搳梌偵傛傝寣埑傪130乛85 mmHg枹枮偵僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偑戝愗偱偡丅
丂擼寣娗忈奞偵偮偄偰偼丄挊偟偔寣埑偑崅偄応崌偼崀埑椕朄傪峴偄傑偡偑丄偙偺嵺丄揔妋側昦宆恌抐傪峴偭偨偆偊偱丄怲廳偵峴側偆昁梫偑偁傝傑偡丅偨偩偟丄堦斒揑偵擼懖拞媫惈婜偵偼愊嬌揑側崀埑帯椕偼尨懃偲偟偰峴偄傑偣傫丅崀埑帯椕偼丄捠忢敪徢侾儠寧埲崀偺枬惈婜偐傜Ca漢峈栻丄俙俠俤慾奞栻丄俙嘦庴梕懱漢峈栻傪梡偄偰彊乆偵崀埑傪奐巒偟傑偡丅嵟廔栚昗偼丄寣埑140乣150乛90 mmHg枹枮偑懨摉偲偄傢傟偰偄傑偡丅
丂怱幘姵崌暪偺崅寣埑帯椕偼丄嫊寣惈怱幘姵丄怱晄慡偍傛傃怱旍戝偲偱揔偡傞崀埑栻偑堎側傝傑偡丅嫊寣惈怱幘姵偱偼Ca漢峈栻傑偨偼兝幷抐栻偑揔偟丄怱晄慡傪敽偆嫊寣惈怱幘姵偱偼俙俠俤慾奞栻偑揔偡傞偲偝傟偰偄傑偡丅怱晄慡崌暪崅寣埑偱偼丄俙俠俤慾奞栻丄棙擜栻偍傛傃俙嘦庴梕懱漢峈栻偑悇彠偝傟偰偄傑偡丅怱旍戝偱偼帩懕揑偐偮廫暘側崀埑壜擻側戞堦慖戰栻傪慖戰偡傞傛偆偵側偭偰偄傑偡丅
丂恡忈奞偱偺崀埑栻帯椕偵娭偟偰偼丄崀埑栚昗傪130乛85 mmHg枹枮偲偟偰偄傑偡丅崀埑栻偲偟偰偼丄俙俠俤慾奞栻丄俙嘦庴梕懱漢峈栻丄Ca漢峈栻丄偦偟偰棙擜栻偑慖戰偝傟傑偡丅偝傜偵丄擜抈敀侾g乛擔埲忋偺傕偺偱偼125乛75 mmHg枹枮偑栚昗偵偝傟偰偄傑偡丅
偍傢傝偵
丂丂埲忋丄崅寣埑帯椕偵偮偄偰丄JSH2000傪傕偲偵帯椕曽恓丄昦懺暿偵傒偨崀埑栻偺慖戰偵偮偄偰弎傋傑偟偨丅崀埑栻偺奐敪偺恑曕偱丄寣埑偺娗棟偼斾妑揑梕堈偵側偭偰偒偨偺偱偡偑丄崅寣埑帯椕偼偁偔傑偱傕偦偺崌暪徢偺敪徢梊杊偵偁傝丄婎杮偲側傞惗妶廗姷偺廋惓傪戞堦偲偟偰屄乆偺昦懺偵崌傢偣偨崀埑栻偺慖戰偑側偝傟傞昁梫偑偁傝傑偡丅乮俈夞楢嵹偺梊掕乯