| NO.23 |
市民フォーラム「願いは健やかハート」
主催:北海道心臓協会/北海道新聞社
後援:北海道看護協会/北海道薬剤師会/北海道栄養士会 協賛:武田薬品工業株式会社
緊急パネルディスカッション―道民の心臓を守るために
(1/1)
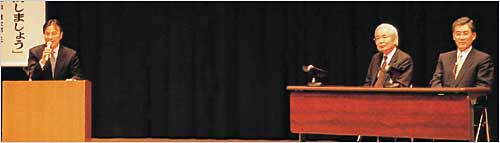
| パネリスト | 北畠 顕氏 | (北大循環病態内科教授・北海道心臓協会副理事長=写真中央) |
| 菊池 健次郎氏 | (旭川医大第一内科教授・北海道心臓協会理事=同右) | |
| コーディネーター | 島本 和明氏 | (札幌医大第二内科教授・北海道心臓協会理事=同左) |
島本 柳田先生がお着きになるまで、菊池先生のお話をベースにパネル討論会を開きます。北大、旭川医大、札幌医大の循環器専門の教授が顔を揃えるのはめったにないことですので、道民の心臓を守るための有意義な討論会にしたいと思います。
まず私から両先生にお聞きします。菊池先生、外来で高血圧の患者さんを診ておりますと「血圧の薬は一回飲むと生涯飲まないとだめと聞いている。少し位血圧が高くても飲むのは嫌だ。もっと上がったら諦めて飲む。もう暫く出さないでくれ」と言う方が時々いるのですが、高血圧の薬は一回飲んだら止められないものなのでしょうか。
菊池 まず、本当に高血圧なのか確認する。一度だけ血圧が高いからといって、直ぐ薬を飲むことは避けた方が良い。何度か測って常に140−90以上あるのかどうか。140−90以上でも即、薬というわけではありません。脳、心臓、腎臓、眼底検査をして全く異常がない、コレステロールも高くない、糖尿病の傾向もない、太ってもいない、タバコも吸わない、しかし血圧が150−90位ある場合は、まず減塩です。運動不足の方は運動を一生懸命やる。カリウムの多い生野菜、有色野菜をたくさん食べる。マグネシウムの多いもの、海草類などを多目に摂る。それでも血圧が高い時に主治医の先生と相談していただきます。
高血圧の他に糖尿病、コレステロールが高いなど危険因子を持っている、特に糖尿病の人は上の血圧が130〜140、下が85〜90でも薬を飲んで治療した方が良い。何回測っても高血圧で危険因子を持っている方は、原則として薬を生涯飲んでいただきます。
家と病院では血圧正常値が違うことにご注意ください。外来では140−90が高血圧ですが、家庭では130−80、甘くしても135−80が高血圧です。家で測ると正常なのに、病院で測ると高血圧ということがあります。「白衣性高血圧」と言って、白衣の人を見るとストレスが上がって血圧が高くなります。薬を飲み始めてから家庭での血圧が120−80未満をコンスタントに保ち、肥満もなく、血糖も大丈夫という方は、主治医と相談して薬を減らし、それで血圧が上がらないなら薬を止めることも不可能ではありません。
島本 次に北畠先生に伺います。心電図で異常があるから狭心症かもしれない、または、異常がないから狭心症はないのかもしれない、と言えるのでしょうか。検診時の心電図で狭心症はどこまで分かるのでしょうか。
北畠 狭心症は一定の心臓の状態で起こるのではなく、ある条件下で心臓に非常に負担がかかって、それが心電図に出てきます。その負担が胸痛という形で現れるのが狭心症の病態です。安静時の1枚の心電図に変化があるからと言って、それで狭心症と診断できません。狭心症と診断がつくのは、何か心臓に負担がかかった時に、心臓に血液が少なくなることが心電図の変化で現れ、それがまた胸の痛みという症状になって現れるということです。
安静時の心電図の変化だけで狭心症とは言えません。必ず、階段の上り下りの検査をするとか、あるいはある種の薬を注射して心臓に負担をかけ、心電図の変化を見て診断することが医学的に正しい方法です。安静時狭心症と言って、動脈硬化によってではなく冠血管の一種のこむら返りで起こることがあります。この狭心症は色々な負荷をかけて変化を起こすということはできませんので、別な方法で診断しますが、大部分の狭心症すなわち労作狭心症は負荷をかけた時に新たに変化が起こるかどうかで診断します。ですから1枚の安静時心電図だけで狭心症と言われても、決して悲観することはありません。改めて診断を受けることをお勧めします。
会場から質問 過日、特急列車の運転手がなんとか無呼吸症で、新聞には充分気をつけなければならないという記事が載りましたが、このメカニズムはどうなっているのか。また、どういうことを注意すれば、注意したことになるのでしょうか。
菊池 睡眠時に呼吸が止まる病気で「睡眠時無呼吸症候群」と言います。太っている方に多く、ある程度以上の肥満体の方は体重を減らすと良くなると言われています。太っていると喉の呼吸をする通り道が狭くなり、意識がある時は呼吸しやすい体位をとりますが、睡眠時はそれができなくて、空気の通り道が閉塞するか極めて狭くなってしまいます。その為に呼吸が10秒、20秒、長い人は30秒位止まり、血液中の酸素濃度が低下し、二酸化炭素、炭酸ガス濃度が高くなると脳の中枢を刺激し、再度呼吸するようになる。これが眠っている間に繰り返されます。こういう人は動脈硬化になりやすいとも言われています。夜間、睡眠時無呼吸の程度が強いと日中に強い眠気がさし、車などを運転している時に居眠り運転をするリスクも高くなるということで、注目されています。
会場から質問 ここ10年ほど、朝と夜寝る前に血圧を測っているが、両手で測ると左手の方が10〜20高いのですが、どちらで測るのが良いのでしょうか。また、パンフレットには平均をとれと書いてありますが、これは右手と左手を足して2で割るのか、それとも何回か測ってその平均を出すのでしょうか。
島本 非常に重要な質問です。血圧測定は1回でいいのか、何回か測って平均をとるのか。時間帯はどうなのか。また、家庭で血圧を測るようになってきましたが、家庭血圧と病院で測る血圧の意義の違いはあるのでしょうか。
菊池 右手と左手では血圧は少し違います。ただ、右手と左手の血圧差は上の血圧で20mmHgを超えないのが普通です。何度測っても20以上差がある時には腕の血管に異常がある可能性があるので、主治医、循環器の先生にご相談ください。
家庭血圧を測ることは非常に重要です。家庭用血圧計は指で測る、手首で測る、腕で測るなど出ていますが、世界的に血圧は上腕で測ることになっています。どうしても上腕がだめな方は手首でという場合もありますが原則として腕で測ります。指の血圧は動脈硬化が強い方、ある程度のお歳の方は当てになりません。指で測る血圧計は買わないでください。自分で測る時には右利き、左利きがあるので、両方測ってあまり差がないことを確認しておくのも重要です。
家庭で測る血圧と病院での血圧は違います。偉い先生の所に行けば行くほど血圧は高くなるというデータもあります。家庭での血圧、特に朝方の血圧は重要ですので、測ることをお勧めします。
島本 2回目に測ると下がる。3回目に測るとまた下がるということもありますが、どういう条件で平均をとればいいと考えればよろしいでしょうか。
菊池 5分間ほど同じ体位でいてから血圧を測定し、数回測ってその平均値をとることが勧められています。雑念を捨てて測ることも大切です。
会場から質問 現在77歳です。6年前に脳底動脈瘤になり、脳外科で股からカテーテルを入れて瘤をワイヤーで埋め、今も半年に1度CT及びMRI・MRA検査をし、異常はありません。ところが、今年2月にトイレでめまいがしました。心配になって担当医に電話したら「なんでもない」ということでした。私の環境は、トイレと部屋は5、6歩、トイレの中はセンサー付電気ストーブで常に暖かく、便座は温度調整されています。そういう状態でのめまいだったので、翌日担当医に行ったら「三半規管関係でそうなったので、あなたの瘤は依然としてワイヤーが詰まっていてCTもMRIもMRAも必要ない。その歳になれば1回や2回はめまいがする。神経質にならないように」というお諭でした。それでよろしいのでしょうか、いまだに心配です。
北畠 めまいの種類にもよります。大別し、周りがぐるぐる回る回転性のめまいと、ふわふわして体が安定しない動揺性のめまいと2種類ありますが…。
質問者 両方のめまいがしました。
北畠 両方ともあるとなると、原因が三半規管にあるのか、あるいはもっと別にあるのか難しい。三半規管に起因しないめまいなら、心臓からの血液量が一時的に少なくなって脳に虚血が起こった状態が考えられます。その原因としては動脈硬化であることもあるし、不整脈のようなものが起こって心臓から出て行く血液量が少なくなり、ふっとしためまいが起こる可能性もあります。いずれにしても、両タイプのめまいが起こるのはかなり複雑ですし、年齢のせいではありません。専門医に行かれた方が良いと思います。
質問者 脳外科に6年かかっていて、担当医がそう言うのです。
島本 両方の可能性があるわけで、一過性であれ脳虚血発作があるかないかをMRIやCTで確認した方が良いですね。それがなければ、前庭神経炎とか良性頭位性のめまいという三半規管からくるめまいということになります。
質問者 何の検査をすればいいのでしょうか。
北畠 耳鼻科に原因があるめまいの可能性もあるようですので、主治医を通じてそちらの先生に診てもらうのも、ひとつの方法かと思います。
島本 学校の健診で脚ブロックと言われたら心配しなければならないものなのか、あるいは放っておいてもいいものなのでしょうか。
菊池 学校健診でなら、多分右脚ブロックが多いと思います。右脚ブロックだけなら、弁膜症などの心臓病がない人でも普通あり得ます。右脚ブロックが90%くらい出やすい先天性心疾患もありますが、心臓に雑音があれば内科検診で見分けはつきます。このような疾患がなく右脚ブロックだけなら心配はいりません。左脚ブロックは専門的なので省略します。
会場から質問 血圧の薬を飲んでいます。副作用が出やすい体質で、ある薬を飲んだら脈拍が40位まで下がり、主治医に言ったら別の薬になり、今度は120〜150突然上がりましたので、薬は変えないで欲しいとお願いしました。カルテにも書くとのことで安心しておりましたら、突然変えられて苦しみました。電話をしたら、医師も看護師も冷たい言葉で悲しい思いをしました。気のせいもあるのか、よく副作用が出て咳や筋肉痛で薬を止めることがあるので、βブロッカーについてお聞きしておきたいのです。
菊池 冷たい対応とのこと、同じ医療を担う者として申し訳ございません。β遮断薬は血圧の薬でもあり、狭心症の薬でもあり、不整脈の薬でもあります。一般的に脈の数を少なくしますが、減りようは患者さんによります。恐らく脈が速くなることがしばしばあるので使っているのではないでしょうか。
質問者 α・β遮断薬に変えてもらったら60位で大変よい状態です。
菊池 先生はよく病状を診ていると思います。ブロッカーは種類が多く、α・βブロッカーは比較的脈の数の抑え方が少なくて済むし、血圧もβブロッカーだけよりも上がらなくて済みます。
北畠 前半は菊池先生と同意見で、セカンドオピニオンをお聞きになることを勧めます。別の先生に意見を聞くと言うと嫌がる医者もいます。パターナーシップと言って、父が子を諭す関係で医療を行うのが日本の伝統的なやり方でしたが、最近は患者さんと相談しながらベストな治療を捜すパートナーシップが医療の基本になっています。疑問をもったら別の先生に相談するのは、勧められるべきことです。
βブロッカーは急に止めると反作用があり、使いづらい薬のひとつです。止める時はゆっくりと減らします。種類が多く、患者さんに一番合ったものを選択することになりますが、基本的にβブロッカーは利く薬ですが、使うのに注意が必要な薬ということです。
会場から質問 冠動脈撮影にカテーテルを使うが、脳のMRAのように、心臓を外から見る検査はないのでしょうか。
北畠 核医学的検査で、注射するだけで画像として表わす方法がありますし、超音波を使うと、感度が良くなったので心臓表面の血管の血流が像として出るなどの方法があります。まだ一般的ではありませんが、かなりな箇所で使えるようになっています。
会場から質問 狭心症の治療でワーファリンを飲んでいます。一生続けなければならないのでしょうか。納豆は食べられないし…。
菊池 ワーファリンは血液を固まり難くする薬で、狭心症や心房細動などに用います。どうしても飲まなければならない疾患があり、主治医の先生はそのような病態にあるので出しているのでしょう。定期的にトロンボテストやPT-INR検査値をお聞きになっているはずですね。納豆を食べると納豆菌がビタミンKの生成を増やし、ビタミンKはワーファリンの作用を抑えてしまい、急に血液が固まりやすくなります。どうしてもワーファリンが必要な病態なら飲み続けなければなりません。病態がどうなのか、もう一度主治医の先生に確認することをお勧めします。
島本 柳田先生がお着きになりました。討論会はこれで終わります。

