| NO.5 |
性・ホルモン
(1−1)
北海道大学 大学院医学研究科 循環病態内科 講師 佐久間 一郎
女性は男性よりも心臓病になり難い
課題は50代以降 生活習慣完全が鍵/好結果期待できるホルモン充填療法
エストロゲンが動脈硬化を抑制
閉経後急増するコレステロール女性は男性と比べ、狭心症や心筋梗塞など動脈硬化性疾患が15〜20年遅れて発症します。これは、女性では生理が正常にある期間は、卵巣からエストロゲンという女性ホルモンが産生されているからです。
エストロゲンには悪玉コレステロール低下作用があります。また、血管の種々の細胞で動脈硬化を抑える作用を発揮します。
たとえば「図1」は、日本人男女における年齢による血清脂質値の変化ですが、女性では男性と比べ20〜40歳代までは総コレステロール値が低値となっています。このようなエストロゲンの作用により、女性は心臓病から守られているのです。
しかし、「図1」で女性は50歳を過ぎると急に総コレステロール値が増加しています。これは平均50歳頃に女性が閉経を迎えるためで、生理が止まると卵巣からのエストロゲン産生も止まる結果、エストロゲンの効果がなくなるからです。
現在、たとえば札幌市の50歳代、60歳代の女性は2人に1人が、総コレステロール値が高脂血症の基準である220mg/dlを越えています。
また、「図1」の中性脂肪の年齢別変化をみると、女性では20歳以降徐々に増加しています。これは生活の西欧化や家事労働の省力化に伴い、わが国では妊娠を契機に女性の体重が年齢とともに徐々に増加することを反映したものと、いわれています。
コレステロールと中性脂肪が共に高いと動脈硬化が起こり易くなるとされていますので、女性では閉経後に動脈硬化が急に進むことになるのです。
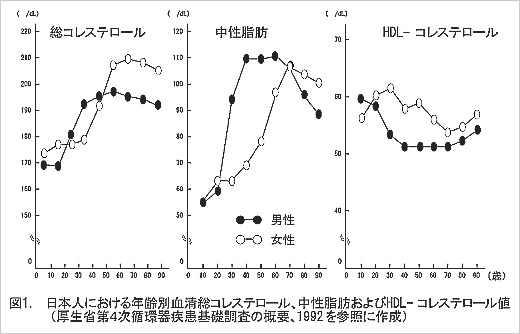
青壮年期こそが男性の警戒期間
一方、「図1」では、男性は20歳代より中性脂肪値は上昇し、30歳から50歳代で最大となり、60歳代以降低下しています。これは就業年代には飲酒の機会が多く、カロリーの摂り過ぎと運動不足になるためと考えられています。
善玉コレステロールであるHDL-コレステロール値は、中性脂肪値に反比例した変化を示します。従って、男性では青壮年期にHDL-コレステロール値が低下傾向となっています。
日本人男性ではHDL-コレステロール値が低いことが動脈硬化発症に最も悪いとされていますので、食事に気をつけ、運動を励行して中性脂肪値を下げることが重要となります。
動脈硬化が起き易くなる危険因子には、年齢、喫煙、肥満、高血圧、糖尿病、高脂血症などがありますが、女性では喫煙している場合、さらに高血圧や糖尿病があると、男性よりも数倍、動脈硬化の進展が早くなるとされています。
年齢と高脂血症因子を是正する
一方、閉経後の女性にエストロゲンを少量投与するホルモン補充療法を行うと、年齢と高脂血症の因子が是正され、動脈硬化になりにくくなると考えられています。
ホルモン補充療法では骨塩量が増して骨粗鬆症が改善し、お肌や粘膜も若返り、さらにアルツハイマー病にもなりにくくなるとされているので、欧米では数多くの閉経後女性が受けています。しかし日本ではまだ受けている女性が少ないので、厚生労働省ではその普及をめざして研究を行っています。札幌では、北海道大学医学部附属病院循環器内科で受けることができます。
米国で看護婦さんを対象に行った研究によれば(図2)、1990〜1992年では1980〜1982年と比べ、冠動脈疾患が31%低下しており、その間喫煙率は41%低下し、ホルモン補充療法が175%増加、そして肥満が38%増加していました。計算すると、喫煙率の低下は冠動脈疾患の発症を13%減少させ、ホルモン補充療法の増加は8%の減少、肥満増加は8%の増加をもたらし、さらに、食生活の改善は16%減少させたことになりました。
生活習慣の改善とホルモン補充療法が、女性の冠動脈疾患発症減少に重要なことが分かると思います。

