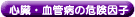| NO.1 |
肥満
(1−1)
旭川医科大学第一内科 平山 智也
はじめに
肥満の成因肥満は脂肪細胞が過度に蓄積した状態であり、医学的見地から減量治療が必要なものは、肥満症という病気として扱われます。
具体的には、理想体重のプラス20%以上のものを肥満症としています。理想体重(kg)は、身長(m)の2乗×22で計算できます。
例えば、身長170cmの方であれば、標準体重は1.7×1.7×22=63.58kgと計算されますので、63.58×1.2=76.3kg以上の場合は、肥満症として扱われることになります。
さらに、最近の研究では、肥満の程度のみならず、肥満の型が疾病の発生と強い関連を有することが明らかにされています。
肥満は、エネルギーの摂取と消費のバランスがくずれ、摂取過多になることによって生じます。
年齢や性別、生活活動の強度によって、エネルギー所要量(Kcal/日)は変化しますが、65歳で、生活活動強度の軽い方では、 男性で1,800Kcal/日、女性で1,500Kcal/日とされています。
食事摂取過多や運動不足により、容易に肥満はひき起こされます。
また、運動不足は、内臓脂肪を増加させる大きな要因の一つになっています。内臓脂肪の増加は、血糖値や血清コレステロール、トリグルセリド値の上昇に関与し、高血圧や心血管合併症と関連します。
肥満の大部分(95%以上)は、このようなライフスタイルを反映して発生すると考えられ、原発性肥満(単純性肥満)と呼ばれていますが、 肥満を惹起する何らかの病気の症状として肥満を呈する2次性肥満(症候性肥満)により発症することがあります。このような例では、肥満の陰に病気が潜んでいることがあり注意が必要です。
2次性肥満(症候性肥満)をきたす代表的な疾患には、糖尿病、甲状腺機能低下症など比較的よくみられる疾患をはじめ、 クッシング症候群、インスリノーマ、脳腫瘍などの病気があり、その症状として肥満をきたします。
肥満に合併しやすい疾患と病態
肥満を治療せずに放置しておくと、種々の疾病を合併する恐れがあります。
具体的には、血糖のコントロールが不良となり、耐糖能異常や糖尿病を合併したり、 高脂血症、痛風、脳血管障害、冠動脈疾患、高血圧を併発します。
さらには、呼吸が障害される睡眠時無呼吸症候群の原因になったり、卵巣機能障害や月経異常、不妊症の合併も考えられます。
女性に多い、下肢静脈瘤の悪化の原因にもなりえます。
肥満症の治療
おわりに肥満症治療の基本は、食事療法と運動療法です。
食事療法の基本は、1日の必要エネルギー以下の食事を摂取して、エネルギーバランスを負にするとともに、 必須栄養素である蛋白質、脂肪、ビタミン・ミネラルなどをバランス良く摂取することが重要です。
栄養士に食事指導をしてもらうことは、一人よがりになりがちな食事内容の是正に多いに役立ちます。
運動療法は、激しい運動を短時間するのではなく、比較的軽めの運動を長時間することが重要で、 これによりインスリンの感受性が高まり、代謝率が高まるのでより有効となります。
肥満は、虚血性心疾患、脳血管障害や肝障害などが関連し、これらの合併症は、内臓脂肪蓄積とより強い相関がみられますので、 肥満の改善とともに、内臓脂肪蓄積の忌避が今後の生命予後改善のための課題といえます。