| NO.128 |
第51回 日本放射線技術学会秋季学術大会
旭川医科大学病院診療技術部
診療放射線技師 森 直人 氏
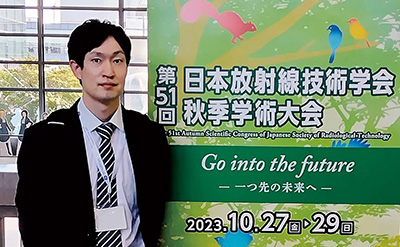
この度愛知県名古屋市の名古屋国際会議場で開催された2023年度(第51回)日本放射線技術学会秋季学術大会に演者として参加させて頂きました。
本学術大会は「Go into the future-一つ先の未来へ-」というテーマで放射線技術学の最新の情報提供や、研究発表をすることを目的として10月27日(金)〜10月29日(日)の計3日間で実施されました。
放射線技術学において、今やどのモダリティでも導入しているAIを組み込んだ演題や講演が多数発表されており、技術の進歩を感じるとともにそれを生かす術を学ばなければいけないと感じました。
私も本学会におきまして「心臓T1マッピングにおける脈波同期がT1値に及ぼす影響について」と題した口述発表を行いましたので、ここに概略を書かせていただきたいと思います。
心臓T1マッピングとは基本的に心電図を体に張り、心臓の拡張期に合わせて心臓を撮像(この方法を「心電同期法」といいます)し、心筋の性状を表す定量値を得る撮像方法です。非侵襲的かつ短時間で撮像でき、心臓のアミロイドーシス、ファブリー病等の診断ができる技術の一つです。
現在は高磁場のMRI装置で心臓の検査をする施設が増えていますが、自施設では高磁場が原因で心電図をうまく認識せず、T1マッピングの撮像に困ることをしばしば経験しました。
そこで磁場の影響を受けない指の脈波と同期させて撮像する「脈波同期法」という技術がありますが、心電波形と脈波波形では心臓の拡張期を示すタイミングが異なります。しかし当院で使用している5s(3s)3sMOLLI法というT1マッピングのシーケンスは脈波同期法で目視ではありますが、特別に設定を変更しなくても拡張期で撮像できていました。そこで心電同期法は脈波同期法で代替可能かを検討することにしました。
心電同期法と脈波同期法で取得した心筋のT1値(心筋の変化の度合いを定量的に算出した値)を級内相関係数にて一致度を検証しました。またMRI装置画面上の心電波形と脈波波形の波形解析をし、拡張期のタイミングで撮像されているかを検証しました。
結果は対象とした48名の患者すべて拡張期で撮像されており、級内相関係数では心筋全体で0.97と一致度も非常に良好でした。このことから心臓T1マッピングにおける心電同期法は脈波同期法で代替可能であると示唆されました。
本研究で得られた知見は、高磁場が原因で心臓のT1マッピングが上手く撮像できない場合があると困っている施設の一助になれば幸いです。
最後になりますが、この度は本学会参加にあたり助成をしていただきました、北海道心臓協会の関係者の皆様、選考委員の先生方に深く御礼申し上げます。

