| NO.129 |
2023米国心臓協会年次学術集会
北海道大学大学院医学研究院 循環病態内科学教室
大学院生 立田 大志郎 氏
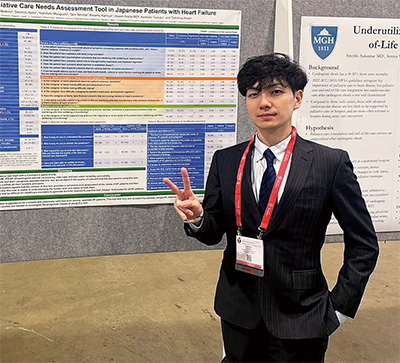
この度、米国フィラデルフィアにて2023年11月9日から13日に開催された、米国心臓協会(American Heart Association:AHA)年次学術集会で「Validity and Reliability of a Palliative Care Needs Assessment Tool in Japanese Patients With Heart Failure」という演題発表させて頂きました。
心不全患者とその介護者(ケアギバー)は、がん患者同様に緩和ケアの提供を求めており、ガイドラインでは積極的治療に並行した早期の心不全緩和ケアの提供が推奨されております。しかし、現状では心不全患者とケアギバーが望むほどの緩和ケアは提供されておりません。この問題を解決するためにニーズアセスメントツールを用いることで、緩和ケアに精通していない医療者であっても包括的な苦痛・ニーズ評価が可能となり、その結果を医療者間で共有することで苦痛やニーズへの対応を容易にし、専門的緩和ケアチーム介入の必要性をスクリーニングすることが可能となります。
今回は、NAT:PD-HFというツールに注目致しました。ニーズアセスメントツールの大部分はがん患者を対象に作成されておりますが、このNAT:PD-HFは心不全患者さんを対象に作成された数少ないツールの一つです。本ツールの特徴は、身体的苦痛だけでなく全人的苦痛の包括的な評価が可能であることと、ケアギバーの苦痛評価に非常重点を置いていることです。そこで、このNAT:PD-HFの日本語版の作成を行い、日本人の心不全患者さんとそのケアギバーが抱える苦痛やニーズを明らかにすることを目的として研究を開始いたしました。入院した心不全患者107例、そのケアギバー95例、NAT:PD-HFを用いる医療者17名を対象とし検証を行いました。得られたCronbach’s α係数やCohen’s kappa係数から、日本語版NAT:PD-HFの信頼性(内的整合性、検者間信頼性、再検査信頼性)は非常に高いものでした。本ツールの使用後に患者とケアギバー、医療者へアンケート調査を行い、本ツールの妥当性(表面的妥当性、受容性、関連性、適用可能性、実現可能性)も確認出来ました。ツール結果から、多くの患者が身体的苦痛だけでなく、精神的苦痛や経済的な問題・家庭での問題等を抱えていることが明らかとなりました。そのケアギバーもまた、患者の身体的・精神的苦痛により負担を感じ、介護に関わる様々な問題やケアギバー自身の全人的苦痛が存在することが明らかとなりました。患者とケアギバーのほぼ全員が本ツールを用いたニーズアセスメントに満足した一方で、医療者側には日常診療における「時間的な問題」があることも分かりました。
末筆ではございますが、本学会の参加にあたり研究開発助成を賜りました一般財団法人北海道心臓協会に心より厚く御礼申し上げます。

